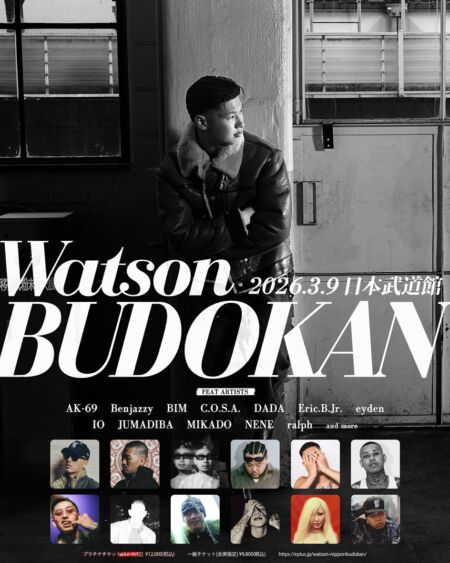Kevin MartinがThe Bug(ザ・バグ)の名義でアルバムをリリースするのは、2008年の『London Zoo』以来、6年振りのこと。とはいえ、6年の間には、Kiki Hitomi(キキ・ヒトミ)とRoger Robinson(ロジャー・ロビンソン)と組んでいるKing Midas Soundとしての活動があり、そこからRoger Robinsonを抜いたKikiとの2人組ユニットBlack Chowとしても活動し、The Bugとしては2012年より〈Ninja Tune〉傘下のレーベル〈Acid Ragga〉から7インチのリリースをスタートさせた。さらには、ロンドンからベルリンに拠点を移したそうだ。なので、潜伏をしていたわけでは一切なく、寧ろ彼はさらに頭を回転させながら、6年間も新たな音楽と、ロンドンと、社会と向き合っていたということだ。
The Bugとしての6年振りの最新作『Angels & Devils』が、これまでのアルバムと変わらないのは、善からぬものたちによって塗り固められた良からぬ社会に対する怒りと悲憤を表現の基調としていて、The BugのトラックはMC、シンガー、ダブ・ポエットたちの煮えたぎった内情をより赤裸々にし、彼らの詩がThe Bugのトラックをよりエモーショナルにしている部分だ。しかし本作がこれまでと違うのは、社会で日々喜怒哀楽する私たちの感情をより鮮明に描き、えぐっていくような妙な生々しさがあるところで、オープニング「Void feat. Liz Harris」からの数曲は、あと数時間で夜明けを迎えそうな深夜に襲いかかる何とも言いがたい虚無感に近いものがある。アルバムの後半は立ち向かうことを辞さないアグレッシヴさ、壁を打ち砕いて突き進んでいくような力強さに満ちあふれているが、呆れているという前提の怒りのようでもあり、それはそれで感情を掻き乱される。
『Angels & Devils』の雰囲気をベースにしたトラックにサポートMCのFlowdanが言葉を重ねて客を煽り、モッシュとダイヴ(?)が起きるほど盛り上がった代官山UNITでのライヴから遡ること6時間ほど前、和やかな表情のKevin Martinにアルバムと音楽制作の話を聞いた。
The Bug Interview
(Interviewer & Header Photo by Hiromi Matsubara, Interpreter by Emi Aoki)

—今回のジャパンツアーを含め、最近のライヴでは機材は何を使っているんですか?
えーと、まずたくさん使うのはカオスパッド。俺はカオスが好きだからね(笑)。あとはシンセサイザーと、Tone Generatorと、サンプラー。ライヴ用の、基礎的な(ヴォーカルなど)何も入っていないただのトラックに、いま挙げた機材たちを使ってノイズをたっぷり足していくっていうスタイルのライヴをしているよ。
—ライヴセットはどういうことを意識して組んでいるのですか?
音楽を作り始めたばかりの頃は、会場に来ているお客さんを全員帰らせることができたら良いと思ってたね(笑)。でも大分前に考えが変わったから、いまはそんなこと一切ないよ。やっぱりより多くのお客さんにライヴを観てもらうことが重要だと思ってる。ただ、俺がプレイしているサウンドは決して全ての人には魅力的ではないと思うから、特に誰にでもにアピールしているつもりはないね。やっぱり特別なモノや素晴らしいモノは万人受けしないし、無難ではないと思うんだ。俺も昔、Public Image LimitedやPublic Enemyを初めて聴いた時に、彼らの音楽が自分の好みかどうかはすぐにはよくわからなかったんだけど、そこに特別な何かが潜んでいるということはすぐにわかったんだ。俺の作っている音楽も、そういう風に受け入れられていきたいと思うんだよね。
ライヴっていうのは、アーティストにとってもリスナーにとっても、チャレンジでなければいけないと思うんだ。正直言って、最近は当たり障りのない音楽が多い。だから、俺は自分の音楽にできる限りの情熱を反映させたいんだ。その表現は、より大きな音を鳴らすことでするかもしれないし、より低い音だって、痛々しい音だって、美しい音だってありえる。境界線のギリギリまで迫っていくことが重要だと思うよ。
—The BugのライヴにはMCも欠かせないですよね。今回共にツアーを回っているMCのFlowdan(フロウダン)は『London Zoo』をリリースする前後からThe Bugの楽曲に参加しているので、もう彼とはそれなりに長い付き合いになると思います。コラボレーションのきっかけや彼との出会いについて教えてください。
俺がもともとRoll Deepの大ファンで、実は最初はRikoとコラボレーションしたかったんだけど、Roll Deepの他のメンバーにFlowdanを薦められてね。それから一緒に仕事をするようになったんだ。Roll Deepのメンバーはみんな情熱的で、態度の悪さもパンクっぽくてカッコイイんだよ。雰囲気はWu-Tang-Clanに似てると思う。でもRoll Deepはラガ、ガラージ、ジャングルを好んでいるから、ヒップホップ・ヘッズではないけどね。Flowdan、Riko、Wiley、God’s Gift、みんなパワフルで素晴らしいクルーだよ。特に、Flowdanはプロ意識が強くて、頭の回転も速くてスマートだと思うよ。初めて彼と一緒にパフォーマンスしたのはMary Anne Hobbsの番組で、その時は12人のヴォーカルと一緒にパフォーマンスしたから、彼からしてみればアウェイな空間だったと思うんだ。無難にその場をしのぐこともできたと思うけど、彼は違ったね。臆することなく一歩踏み出してあの空間で冒険していたよ。
俺とFlowdanは見た目は全然違うと思うんだけど(笑)、人間的には結構似ている部分があってね。もう長年の付き合いになるからお互いに尊敬し合ってる。彼はUKで最高のMCだと思ってるから、いまでもこうして一緒に仕事ができるのは光栄に思うよ。彼は声のトーンが独特だから聴けばすぐにFlowdanだとわかるし、リリックもクールで、グライムのMCだけど間合いの取り方が上手いし、クレイジーなMCもできるから凄いと思うよ。今後も彼と一緒に仕事をしていきたいね。
—The BugのプロジェクトではMCを多くフィーチャーしてきたイメージがありますが、最新作『Angels & Devils』ではLiz Harris、Inga Copeland、GonjasufiといったMCではない人もフィーチャーしていますよね。あなたにとって、ラップと歌、MCとヴォーカリストの違いはどういうものですか?
ほう、良い質問だ(笑)。MCは、エネルギーがあって、強烈で……活発で……聴くと電撃が走るような感じが好きんだ。ヴォーカリストは、詩的な響きで、ドリーミーで心地良いというか……Gonjasufiも、Liz Harrisも、Inga Copelandも、それぞれが特別なトーンを持っているから、一種の楽器として聴いているし、今作でもヴォーカルは楽器のように使ったつもりだよ。
俺が前からメディアや人々の批評に対してムカついているのは、そういうメロディックな部分があるのにも関わらず無視をして、ハードな部分でしか認識していないことなんだ。『Pressure』と『London Zoo』ではRoger Robinsonが、『London Zoo』ではRicky Rankingが歌ってるんだけど、人々はそういう部分を無視して認識しているんだよね。だから今回のアルバムはより二面性を強調させているんだ。
俺は音楽には2つの聴き方があると思っていて、ライヴではハードなサウンドでぶっ飛ぶような、燃え上がるような感じにしたいんだけど、それとは逆に、家に居る時や旅行で飛行機に乗っている時、自転車に乗っている時に、ヘッドホンで聴く時はチルアウトできる音楽にしたいんだ。一見別ものだけど、俺は両方とも必要だと思っていて、わかりやすく言うと”甘いものも酸っぱいもの好き”みたいな感覚だね(笑)。今作では、そういった二面性とそのバランス感を重要視したんだ。

—いま、二面性という言葉が出ましたが、あなたが『Angels & Devils』で描いている”エンジェル”と”デビル”はそれぞれどういうイメージのものなんですか?
もともと”Angels & Devils”っていう言葉は、〈Ninja Tune〉に次のアルバムはどうするのか聞かれて、「『London Zoo』の”エンジェル&デビル”バージョンを作りたい」ってその場で適当に話した時に出てきた言葉でね。それが結果的にタイトルになったんだ。エンジェルのサイドとデビルのサイドそれぞれを極端に表現した上で、もともと相反するエンジェルとデビルが交わる部分を作り出すのが面白いと思ったんだ。で、さらに、2つを混ぜてしまって、どっちとも区別がつかなくなる状態にするのも面白いと思ったんだよね。だから、あまり白黒はっきりはしていないんだ。
よく人生でも白黒はっきりさせたいとか言うけど、結局人生はカオスでおかしなものだからはっきりさせなくて良いと思うんだ。今回のアルバムもそういう感じだね。皮肉にも『Angels & Devils』っていう白黒はっきりした感じのタイトルになっちゃったけど、アルバムの内容的には結構全体的にヘヴィーで、サイケデリックな万華鏡を覗いているみたいにトリッピーで、色々なサウンドが混ざり合った”カオス”なアルバムだと思うね。
—6曲目「Save Me」から7曲目「The One」への流れとかを見ると、白黒はっきりと二極に分けられた、エンジェル・サイドとデビル・サイドが表裏一体のトラックリストなのかなと思うのですが、実際はエンジェル・サイドにも悪魔的な怒りがあって、デビル・サイドにも天使が我々に与えるような希望、前向きな姿勢が伺えるんですよ。だから、実は2つは混ざっている複雑なひとつの感情として表現されているのかなと思いました。
そう。100%混ざっているひとつのものだ。今回のアルバムへの反応でとても面白かったのは、アメリカとイギリスの反応が結構違ったことでさ。イギリスの反応は、今作が混ざり合ったひとつのグレーな感じを表現していると理解してくれたんだけど、アメリカのジャーナリストは混ざっているということをあまりわかってくれてなくてね。単純にしか見てくれないんだ(笑)。アメリカ人の思考が単純なのかな……ってことはあまり考えたくないけどね(笑)。でもアメリカのリアクションに関しては違和感を感じたね。アニメのキャラクターみたいに特徴付けたがるんだ。
—『Angels & Devils』に込められたメッセージの中には政治や社会情勢に対する憤りという部分もありますよね。世界規模で見ても、例えば、大きな権力に対して反抗しているところもあれば、しっかりと治まっているところもあるというように二面性があるわけですが、この二面というのはもともとは私たち一人一人の中にあるものだと思うのです。平穏に過ごしていても突然違和感を感じて怒ったり、時間が経てばその怒りは治まったり。『Angels & Devils』はそういった、もっと日常的な、パーソナルな二面性を描いているようにも思いました。
そうだね。レコードを飾り過ぎるのはダメだと思う。みんなどこかで天使になりたいと思っているけど、やっぱり悪魔になってしまう部分も同じように潜んでいるんだ。誰でもそうだと思うよ。『Angels & Devils』のアートワークに載っている、俺が書いた詩の最後に部分にも、”There is angels and devils behindes all our eyes.(私たちの内側には天使も悪魔も潜んでいる)”という一節があるんだ。この世には、美しく生きていると言い切れるような完全な人間なんていなくて、100%天使な人はいないと思うよ(笑)。俺の中でも天使と悪魔の戦いは常に起こっているし、それが人生だ。本当に昔から、それこそ神がアダムとイヴを作った時からあると思うよ。最近の人は、世界はどんどん悪くなっていると思うかもしれないけど、実際のところ、状況はほとんど変わっていない。善悪の感情はいつも人間の中にあって、それが人から人へと映っていって、世界はバランスを保っているんだよ。
—今作は『London Zoo』から6年振りのアルバムなので、The Bugのリスナーには以前から作品を追っていたリスナーに加えて、若い年齢のリスナーが増えているのではないかと思います。特にBurialに始まり、Kode9や〈Hyperdub〉を熱心に追っている若者の中には、King Midas Soundを通してあなたを知り、The Bugというプロジェクトを知ったという人もいると思います。実際、いま20歳の僕はKing Midas Soundを経由してThe Bugを知り、『London Zoo』を初めて聴いたのは10代の時でした。あなたが手がけている音楽はグライム、ダブ、ダンスホール、ラガというあまりポピュラーではないジャンルですが、こういう音楽が持っている何かしらの熱いスピリットを若いリスナーやアーティストに継承していくということは、アルバムを作りながら意識されているんでしょうか? また若いリスナーからの反応を直に受け取ることはありますか?
深い質問だな(笑)。最初、Techno AnimalをJustin Broadrick(ジャスティン・ブロデリック)とやっていた時は、ぞっとするほど酷い嫌なノイズだと言われていたんだけど、できるだけ多くの人たちに聴いてもらいたいという気持ちはあった。20人の前じゃなくて、2000人の前でプレイしたいと思っていたよ(笑)。でも別に俺は音楽活動に関してはエリート主義ではないし、もともとはプロデューサーの方に興味があったからね。アンダーグラウンドにいるのも、いたいからいるのではなくて、自然とそうなっているだけなんだ。かといって、メインストリームに行きたいかというと、全くそんなことはないね。メインストリームっていうのはファシスト的なやり方もあるし、ラジオを聴いていても、間抜けな音楽しか流れてないからね。俺はリスナーは頭の良い人たちだと思ってリスペクトしているよ。重要なことだ。
君みたいな若いファンがいるのは非常に嬉しいよ。ずっとThe Bugのファンでいてくれている40代のおじさんにライヴをし続けても面白くないからね(笑)。つい先月、〈Jabberwocky〉っていうJames BlakeとEarthやJesuが一緒に名を連ねるクレイジーなフェスがあったんだけど、キャンセルになっちゃってね。代わりに別の会場を探して、急遽1日だけ俺とFlowdanでライヴをやったんだけど、それがソールドアウトになったんだ。凄く嬉しかったよ。フェスを楽しみにしていた人たちが他のアーティストのファンばかりではなく、自分のファンも沢山いたということがわかったからね。そのライヴには幅広いお客さんが来ていて、ジャマイカ人の女の子がステージの前で踊ってたりとか、ヘヴィーメタルが好きそうな人が後ろの方にいたりとか、ダブステップが好きなんだろうなっていう学生もいたりして、凄く良い夜だったよ。
自分の音楽は、若い人はもちろん、幅広い世代の人にも、普段は違う音楽の趣味を持っている人にも聴いてもらいたいね。そうでないと自分の作る音楽の幅も狭くなってしまうから。色々な人に聴いてもらうことは、そういう意味でも大事なことなんだ。
—『Angels & Devils』を制作した際に160曲のデモが作られたそうですが、エンジェルとデビルのどちらのサイドにも属さない楽曲が出来ることはありましたか?
そういう曲は沢山あったよ。でも、アルバムのヴィジョンとストーリー性がはっきりしていたから、当然だけど、それに合わない曲はアルバムに入れないことにしたんだ。
アルバム未収録曲「Zim Zim Zim ft. Burro Banton」
—そういうThe Bugとして作ったけど使わなかった曲をKing Midas Soundの方で使ったり、The Bugとしてリリースするための楽曲を作っている時にKing Midas Soundの方で使えそうな楽曲やアイディアが生まれたりすることはありますか?
King Midas SoundのRoger RobinsonはいつもThe Bugのトラックを盗もうとしてるよ(笑)。「Catch a Fire」っていう、The Bugでリリースした中ではヒットした曲があるんだけど、その曲をKing Midas SoundのステージでKiki Hitomiが歌ったことはあるね。
The Bugも、King Midas Soundも、それぞれユニットの芸術性、方向性、目的がはっきりしているから、どちらかの曲を作っている時にもう一方のユニットで使えるなって思うことは普通はないかな。Techno Animalをやっていた時は、方向性や目的がはっきりしていなかったから実験的に色々なことをやっていたんだけど、いまはあまり当時のような作り方はしてないな。
—『Angels & Devils』のアートワークに使用されている、Simon Fowler(サイモン・ファウラー)が描いた翼のドローイングはアルバムのテーマとどう関係しているものですか?
あの翼の絵は俺が選んだのではなくて、Simonがアルバムに合わせて作ってくれたものなんだ。Simonはドローンメタルが好きな若者で、Corruptedっていう日本のメタル・バンドのライヴを観に行った時に、King Midas SoundのKiki Hitomiが紹介してくれて出会ったんだ。ちょうど彼が、メタルのあのお決まりの感じに飽きてダンス・ミュージックにハマり始めていたということもあって、出会って以来、彼はよくThe Bugのライヴに来てくれたんだ。彼はSunn O)))やEarthのアートワークを手がけていて、その作品を見せてくれた時に、とても素晴らしい人だと思ったんだ。もちろん彼は絵の才能もあるんだけど、日本語がペラペラで、寿司職人でもあって、彼はいま日本に住んでいるんだよ。
彼には制作途中の音楽から受けた印象を絵にしてもらって、アイディアを交換して、それを材料にしてお互いにさらに作り込んでいく合うコラボレーションのような作業を繰り返したんだ。チームワークで完成させる作品にしたかったからね。彼はとても大変だったみたいで、ストレスで白髪が増えたとか言ってたけど、彼との作業を通してより良いものができたと思うよ。彼とはアートについてもかなり話しをして、Hieronymus Bosch(ヒエロニムス・ボッシュ)の地獄の絵とか、佐伯祐三の絵とか、あとはテロリスト集団が使っているアイコンを集めた本を見せたりして、俺がどういう雰囲気の作品が好きかを教えたんだ。色んなアイディアのソースになると思ってね。そういった行程を経て、彼が描いてくれた作品を見ては、”これはここが良い”とか”ここがイマイチ”とコメントしながら選別していったんだ。実際の絵はもっと大きくて、翼は絵の中の一部分なんだけど、翼の部分が素朴で美しくて本当に良かったから、ここだけを拡大して使おうという感じで決めたんだ。
これまでのThe Bugのアートワークはグラフィティっぽいものが多かったんだけど、今回の絵はファインアートっぽくてタイプが全く違うから、The Bugの新しいイメージを作れるかなと思ったんだ。Simonはこの後にリリースするEPと、さらにその後にリリースする『The Bug vs Earth』っていうEPのアートワークも手がけてくれていて、その3作で完璧なトリプティックを作るというコンセプトなんだよ。アルバムで使われているフォントやロゴマークも、全て彼が手書きでデザインしたもので、アルバムの楽曲にインスパイアされて作ってくれたんだ。彼とは今後もコラボレーションしていくつもりだよ。彼は天才だから、彼の作品は励みになるし、彼も俺の作品が励みになるみたいなんだ(笑)。素晴らしい関係だよ。
■Biography
ウォーリアー・クイーンをフィーチャーした「Poison Dart」が大ヒット・アンセムとなり、ザ・バグ(The Bug)ことケヴィン・マーティンにとっても大きなターニング・ポイントとなった『London Zoo』(2008)では、ロンドンのアンダーグラウンド社会に訪れる未来をディストピアとして描かれていた。その後ロンドンからベルリンに移住したザ・ バグことケヴィン・マーティンは、そのコンセプトをさらに拡大させ、世界崩壊後に訪れる絶景を描き出した6年振り待望の最新作『Angels & Devils』を完成させた。

『Angels & Devils』
Now On Sale
Ninja Tune / Beat Records
国内盤ボーナス・トラック2曲追加収録
アルバムの詳細はこちら!