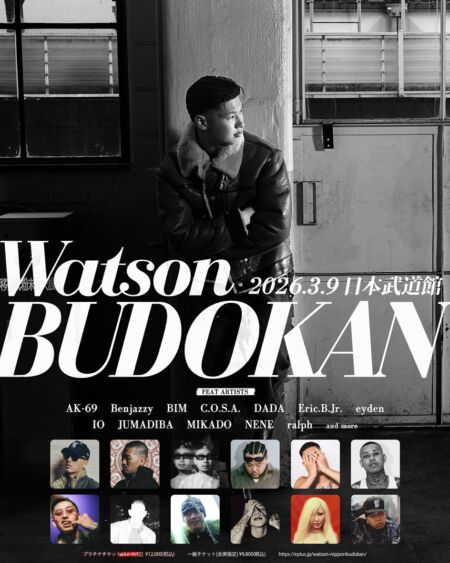滋味深い歌声とエバーグリーンなポップ・センスを有する京都出身のSSW/プロデューサー・luvis。その活動は明らかに次なるフェースへと向かっているようだ。
10月にリリースされた最新EP『from pier』では高橋直希(Dr.)、梅井美咲(Pf.)、冨樫マコト(Ba)といった新世代ジャズ・シーンを牽引する面々と共に初のバンド・レコーディングを敢行。自身の世界観をより強固に確立している一方で、豊潤な音楽の魅力にも溢れている一作だ。
その若さとは裏腹に、どこか熟練のミュージシャンのような佇まいも感じさせるluvis。果たして、彼はどこから来てどこへ向かうのか。今回のインタビューでは自身の生い立ちから最新EPの制作背景まで、じっくり語ってもらった。
Interview & Text by Takazumi Hosaka
Photo by 家太郎
京都で育まれたバックグラウンド
――個人的にluvisさんには達観した視点というか佇まいを感じることが多くて。それはサウンドやリリック、さらに作品に寄せられたコメントなどを含めた印象なんですけど。勝手ながら、それは京都で生まれ育ったことと無縁ではない気がしていて。
luvis:無縁ではないと思います。東京に出てきて、それは自分でも強く感じていますね。
――これまでの作品も時の流れを題材としていたり、その視野の広さが印象的でした。そういう視点ってどのようにして形成されたんだと思いますか?
luvis:街との対比だと思います。京都は時の流れが緩やかで、他の街と比べて細かい変化に気づきやすいんです。たとえばいつも通る道に花が咲いたり、そういった些細なことに目がいくんですよね。長い歴史のあるお寺が身近にあって、周囲も山に囲まれていて、そういう環境が自分のひとつの土台になっているのは間違いないです。
――それこそ京都の町並みのような過去への視点だけでなく、同時に未来を見据える視点が培われているのも興味深いなと思いました。決して懐古主義にはならないというか。
luvis:それも一種の対比だと思っていて。変わらないものがあるという前提で生きているからこそ、変化することに対して恐怖や躊躇がない。僕自身は変わっていくことが生きがいっていうくらい変化するのが好きなんです。そうやって新しい物事を吸収したりどれだけ心境が変わっても、自分の中には心の故郷みたいなものがあるから、不安になることはないというか。
――すごく腑に落ちた気がします。ちなみに、luvisさんは京都でどのような少年時代を過ごしましたか?
luvis:とりあえず虫が大好きでした(笑)。おじいちゃんが虫取り名人で、トンボの捕まえ方を教わったり、ワニガメとか外来種の動物の恐ろしさとかを聞かされたり。禁止されていたわけではないんですけど、僕自身がそんなにゲームとかを欲しない人間だったんです。小学校時代もゲームより虫取りとか秘密基地作ったり、割とアクティブな遊び方をすることの方が多かったですね。
――音楽は小さい頃から身近な存在だったそうですね。
luvis:家ではよく音楽が流れていました。ちょっとした空き時間にお父さんがギターを弾いたり、お母さんがピアノを弾いたり、そういうのが日常でしたね。表現としてというよりかは、生活の中の音楽っていう感じでした。
――luvisさんが音楽に興味を持ったのはどのくらいの頃ですか?
luvis:興味自体は小さい頃から持っていたんですけど、詳しく掘り下げたりはせず、YouTubeで80年代の音楽を聴いたりして漠然と楽しんでいました。あと、高校時代はミスチル(Mr.Children)しか聴いてなかったっていうくらいミスチルにハマってました。
――そうなんですね。ちょっと意外です。
luvis:完全にお父さんの影響なんですけど、全曲歌えるくらいには聴き込んでいました。より詳しくいろいろな音楽を掘り下げるようになったのは大学生になってからですね。
自分の中で大きな衝撃が2つあって。まずはD’Angeloを始めとしたブラック・ミュージック。Erykah Baduなどのネオソウルから聴き始めて、同じプロデューサーが手がけている作品を辿っていって90’sのヒップホップを聴くようになったり。そこでサンプリングされている曲を掘っていくうちにジャズやブルースも調べるようになりました。
luvis:そしてもうひとつはDinosaur Jr.やブッチャーズ(bloodthirsty butchers)といったオルタナに出会ったこと。裸の心でギターをかき鳴らすような表現。その2つの軸が、今の自分の音楽性にも大きな影響を与えていると思います。
――そういった音楽にはどのように出会ったのでしょうか? サークルの先輩や友人から?
luvis:いや、サークルにも入ってなくて、完全にひとりで研究していました(笑)。僕、そういう面では結構オタク気質で。初めて東京に来たのも、ヒップホップのレコードをディグることが目的だったんです。
――気合いの入ったレコード・ディガーですね(笑)。
luvis:今も好きですけど、その当時は特にレコード熱が高くて。サンプリングでビートメイクもやってみたくて、ヒップホップやサンプリング・ネタとなるソウルやジャズのレコードを買い集めたりしていました。結局、サンプリングせずに聴いてただけなんですけど(笑)。
――バンドを組んだりはしなかったんですか?
luvis:バンドは組んでないですね。バンドを組むのって、ある種“結婚”と似てるのかなって思うんです。結婚したことないのにこんなこと言うのもあれなんですけど(笑)。ひとりでやる小回りのよさとか利便性を捨ててでも「こいつと一緒にやりたい」って思う相手が見つからないと、組みたいって思えないんだろうなって。逆に言うと、そういうビビッと来る人と出会えたら、今後バンドを結成する可能性もあると思います。
――じゃあ、京都のシーンとの繋がりもない?
luvis:そうですね。全然ないです。
――昨年、同郷のKani Ningenさんがリリースした1stアルバム『yolkwhite』に参加されていましたよね。
luvis:Kani Ningenは実は高校の先輩で、彼も今は東京で活動しています。一緒に音楽をやってたわけではないんですけど、SNSは繋がっていて。僕が大学を辞めるくらいの時期に彼が芸術に関する論文をインスタのストーリーにUPしてて。それで興味を持って、改めて連絡しました。ちゃんと仲良くなったのはそれからですね。
様々な愛を歌っていく──luvisを構成する要素
――ご自身で音楽を作り始めたのはいつ頃からですか?
luvis:高校生くらいですね。最初は弾き語りで好きな曲をカバーしたり、自分で歌詞を書いてオリジナルを作ったり。そのうちに、友だちがライブハウスに誘ってくれて出演したりもしていました。
――軽音部などには入っていたんですか?
luvis:いえ、テニス部でした(笑)。軽音部の人たちに「どうやらテニス部に弾き語りやってるやつがいるらしい」っていうことが伝わって、軽音部主催のライブにも出させてもらいました。
――トラックメイクなどを始めたのは?
luvis:大学2回生のときですね。1回生のときは大学生として普通に過ごしていたんですけど、2回生でD’Angeloに出会って、「やっぱり音楽だわ」となり(笑)。そこから音楽に本格的に向き合うようになりました。僕、本当に単純なので。
――D’Angeloに衝撃を受けたときのことについて教えて下さい。具体的にどういったところに惹かれましたか?
luvis:経緯からお話させてもらうと、大学1年のときは遊び呆けていたんですけど、そのうちに「そろそろまた音楽やろうかな」って思い始めて。それでスタジオを運営している知り合いから、「レコーディングしてみない?」って誘われたので、弾き語りで3曲くらい録らせてもらったんです。そこで、自分には衝撃的にリズム感がないということに気づいて。
どうしたらいいもんかと思ったんですけど、単純なので「リズム感 いい 音楽」とかで調べたんです。そしたら「どうやらブラック・ミュージックのリズム感がすごいらしい」と。なるほどと思ってブラック・ミュージックの歴史を網羅しているプレイリストでいろいろと聴いていくうちに、D’Angeloの「Untitled (How Does It Feel)」に出会って、「何だこの音楽は!」って衝撃を受けました。
――それは独特のリズムのもたつきの部分だったり?
luvis:そのときはまだレイドバックとかもわからなくて。リズム、ハーモニー、音に込められた熱量など、シンプルに音楽として喰らいましたね。先輩にヒップホップ好きが多かったので、漠然とした憧れはあったんですけど、そこから解像度が一段上がったというか。
――luvisという名義、プロジェクトはどうやって始まったんですか?
luvis:それまでは本名でやってたんですけど、D’Angeloに出会ったことで音楽性も刷新したいなと思うようになり、luvisという名義を考えました。“luvis”って分解すると“luv is(LOVE IS)”になるじゃないですか。僕の音楽活動の根底にはずっと“愛”があると思っていて、それは恋愛、友愛、家族愛とか、様々な形の“愛”のことで。それを一生かけて歌っていきたいと思っているのと同時に、“LOVE IS(愛とは)”で終わってるように、きっと一生かかっても答えや結論みたいなものは出てこないんだろうなって思うんです。……最初は語感のよさで決めたので、後付けではあるんですけど(笑)。
――luvis名義での最初のリリースは2021年発表の「Journey」ですよね。
luvis:「Journey」を出すまでの1年間くらいが転換期だったと思います。当時はまだ本名で弾き語りをやっていた頃の要素もあって、歌メロはポップスなのに、トラックはブラック・ミュージック、ヒップホップみたいな感じで。ちょっと中途半端だったなって思います。その中で試行錯誤しながらも、当時の自分なりに納得のいく作品ができたなって思えたのが「Journey」で。
――もっとヒップホップやラップの方向に進もうとは思わなかったんですか?
luvis:「human day」などではラップもしているんですけど、そうですね……。やっぱり自分は弾き語りで育ったので、ハーモニーとメロディが好きなんですよね。ビートやリズムも大好きだけど、それだけじゃ少し物寂しいというか。欲張りなんですよね(笑)。
初のバンド・レコーディングで作り上げた『from pier』
――最新作『from pier』は最初にもおっしゃっていた「“心の故郷”とは何なのか」という問いから始まり、それに自ら答えていくというコンセプチュアルな作品ですよね。こういった構想もやはり東京に拠点を移したことが影響しているのでしょうか?
luvis:EPの曲自体は全て京都にいた頃に生まれたものなんですけど、テーマやコンセプトの部分ではかなり影響していると思います。東京の激しい流動性みたいなものは、京都にいたときには感じたことがなかったので。
あと、軍艦島に行ったことも大きな影響源ですね。友だちについていく形で観光に行ったんですけど、いざ現地に着いたら「ここで故郷を失ってしまった人たちがいるんだ」という事実に喰らって。それで……軍艦島から帰る船の中で、自然と童謡の「故郷」を口ずさんでたんですよね。そこが今回のEPの出発点になりました。
――テーマみたいなものが見えてきてから、どのようにして作っていきましたか?
luvis:サウンド感的にはフォークというか、生楽器の温かい感じを元から考えていて。それも東京に来た反動なのかもしれないんですけど。
――シンプルに、今の音楽的なムードとして。
luvis:はい。最初は今までと同様にDTMで作ろうと思ったのですが、自分が思い描いていたニュアンスに近づかなくて。それで今回のメンバーにお声がけして、レコーディングすることになりました。
――メンバーはもとから知り合いだったんですか?
luvis:それも結構偶然というか。東京に来てから全員の演奏を観る機会が別々にあって、それぞれのライブで一回は泣いてます。本当に心から素晴らしいなと思えるプレイヤーの方をお誘いしました。
――これまでひとりで制作してきたわけですが、それをバンドに落とし込むという作業はどうでしたか?
luvis:正直に言うと、最初は他の人の演奏や音色を入れることに対して不安もあったんです。自分の思うようにいかなかったらどうしようって。けど、いざレコーディングしてみたら、全くの杞憂でした。みんな僕の作品や感性を考慮して演奏してくれたので、すごく自然に溶け込んでくれた。もちろん自分からある程度指示させてもらったりもしたんですけど、大部分は自由にプレイしてもらって、そこで予想もしていなかったフレーズや音も生まれました。
あと、音作りの面では向さん(※)の存在も大きいです。特にピアノの音色をすごく緻密に、時間をかけて詰めてくれて。本当に彼らなしでは完成し得なかった作品だと思います。
※向啓介:showmore、ZIN、Aile The Shotaなどの作品を手がけるレコーディング/ミックス・エンジニア。
――デモから大きくアレンジが変わった曲などはありますか?
luvis:「蜃気楼」はめっちゃ変わりましたね。最初はシンセも入ってたんですけど、みんなでレコーディングした結果、トラディショナルな感じになりました。
――「蜃気楼」はオーガニックな音色と開けた世界観がどこか夏を想起させます。
luvis:《夕べ見た夢の続きを知らぬままで》っていうラインはギターを何となく爪弾いてたときに自然と出てて、これは湿り気のある京都の夏でしか書けない曲かなって思います。
――『from pier』というタイトルにも繋がってる「桟橋より」は、先ほどおっしゃっていた軍艦島でのインスピレーションを受けて生まれた曲なのでしょうか?
luvis:そうです。“桟橋”は世界の端っこというイメージで、そこから遠いところにある自分の故郷に想いを馳せているような情景を曲にしました。
――2曲目の「Q」は軽快なウッドベースが印象的な1曲です。資料によると“人間の問いを歌う”と書いてありました。
luvis:自分や身近な人が大切な何かを失ったりする経験が重なった時期だったので、自分の中に「なんで失ってしまうんだろう」っていう疑問みたいなものが漂っていたんです。そのイメージが曲に表出していると思います。答えを求めるというよりは、疑問を疑問のまま提示したという感覚。
――リリックを書くとき、自身の思いや感情を赤裸々に綴ったり、あるいはそれを架空の物語に投影する人もいると思います。luvisさんはいつもどのような意識で作詞していますか?
luvis:間違いなく自分の感情などは含まれているけど、“等身大”とか“赤裸々”っていう感じではないと思います。かといって架空という感じでもなく、もう少し広い世界で書いているようなイメージですね。自分の実体験はもちろん、友だちの話や小説とかからもインスパイアされたりしますし、自分の実体験に基づく妄想っていう感じ。
――先ほど、軍艦島に行った際のエピソードで出てきた童謡の「ふるさと」は、アシッド・フォークのようなアレンジや後半の展開も素晴らしいなと。
luvis:「ふるさと」は……ちょっとどうやって作ったか忘れましたね(笑)。ただ、DAWじゃなくてフィジカルのエフェクターを使用した記憶があります。打ち込みで作ったドラムを出力して、外付けのエフェクターに通してレコーディングする、みたいな。やっぱり厚みや質感が全然違うんですよね。〈Chase Bliss〉の「Generation Loss」っていうエフェクターがあって、それが超いいんですよ。今回のEPでは他の曲でもかなり活躍してくれました。ドラムやボーカル、ピアノ、自然音にも使ってます。
――その「ふるさと」から「Dance」に繋がる流れも気持ちよくて。EPのひとつの山場のようにも感じました。
luvis:やっぱり自分の心の故郷みたいなものに触れる瞬間を、映画のサントラみたいな感じで表現したくて。「ふるさと」を挟んで、クライマックスへと向かう展開は最初から構想していたことでもありました。
――「Dance」は牧歌的でたおやかなフォークながら、徐々に熱を帯びていく展開が秀逸です。
luvis:「Dance」は実は2年くらい前、それこそ軍艦島に行く前にできていた曲なんです。
――この曲は「桟橋より」や「Q」での問いに答えを提示するような楽曲ですよね。
luvis:回答となるような一番最後のアディショナル・セクションだけ、EP制作の佳境に至ってから最後に付け足したんです。
――《どこにいたとしても/僕はここにいるのさ/踊ろうほら夜は明ける》という部分ですよね。大げさな話、故郷が物理的になくなったとしても、自分の心の故郷は変わらない、と。
luvis:そう信じたいです。あると断言はできないけど、そういうことを信じて僕は歌いたいです。
――では、その2年くらい前、曲の原型ができてきたときのことについて教えてもらえますか?
luvis:当時、自分のありのままの表現を探していた時期で。トラックメイキングにハマってから、ずっとひとりで制作してきたんですけど、いざライブになると歌の力がトラックに勝てなかったりして。そもそもボーカル自体も楽に出せるような音域の曲ばかり作っていて、ライブで歌いきっても全然汗もかかない。これでいいのか? これが本当に自分のやりたい表現なのか? って悩むようになったんです
僕は考え方が極端なので、だったらもう一回弾き語りに戻ろうと思ったんですよね。実際にそれから半年くらいトラックメイクをしていない時期があって。「Dance」はそのときにできた曲です。
――そういった葛藤や悩みに対して、ご自身の中で回答は見い出せたのでしょうか? それとも現在進行系で模索しているのか。
luvis:とりあえずいろいろな人のライブを観に行ったんです。青葉市子さんやPredawnさん、君島大空さん、碧海祐人くんなど……何て言ったらいいかわからないけど、“揺らぎ”がある人というか。そこですごく衝撃を受けました。僕はこれまで、何かの真似事をしていたんじゃないかって思ったんですよね。もっと自分の素の表現を見つけようと思うようになって、それで《ありのままで揺れてもいいのかい》と歌う「Dance」が生まれました。
音楽はバカでかい生き物
――ありのままの表現を模索し、バンド・レコーディングも実現させた今作を経て、luviさんの今後の音楽活動はどのような方向に進むと思いますか?
luvis:もっと早いテンポの曲を作りたいですね。グランジまではいかないけど、激しいサウンド。それと今作のようなゆったりとした楽曲も作りたい。スタイルは違えど、どちらも“揺らぎ”があるような表現を目指していきたいです。
――先ほど、自身のライブについての話も出ましたが、パフォーマンス面で意識的に何か変化させていることはありますか?
luvis:それこそ、ライブの面ではかなり“揺らぎ”を出せるようになったと思います。トラックを同期で流すライブって、どうしても音量とか音圧が均一になりすぎるというか。それを自分の声とギターで工夫するんですけど、バンドだと最小のアカペラやマイクなしの状態から、ギターにファズをかけたりドラムをめっちゃ叩いてもらったり、音のダイナミクス・レンジがすごい広がる。緩急の付け方もかなり自由度が高い。あと、MIDIで打った音と違って、当たり前ですけど生楽器の演奏は一音一音が揺れていて。それが集合体となって1曲を構成するので、生き物っぽくなるんですよね。有機的というか。
――なるほど。
luvis:この自分が持ってる“うねり”や揺らぎみたいな部分って、すごく伝わりにくいものだと思うんですけど、それをどうにかして感じてほしいんですよね。僕はそれを模索し続けているし、今後もそういった表現をしていきたい。音楽でしか味わえない感動みたいなものを提供できるアーティストになりたいですね。
――音源の面でも、そういったうねり、揺らぎを重要視して作っていくのでしょうか。
luvis:それも大事なんですけど、音源ではもっと日常に寄り添いたいです。僕は音源とライブは別物という考え方で、音源はどういったシーンで聴いてほしいとかも考えて作ってます。久しぶりにおばあちゃんに会いに行くときだったり、めちゃくちゃ辛い失恋をしたときとか、かなり細部まで想像しています。
……本当は「日本一のロックンロールが作りたいです!」とか、ズバッと答えたいんですけどね(笑)。でも、やっぱり僕は振り切った音楽はできないんです。そんなものそもそも存在してるのか、とも思うんですけど。
――振り切った音楽?
luvis:たとえば喜怒哀楽の“喜”だけを抽出した音楽とか。愛や悲しさ、怒りとかを完全に含んでいないような。やっぱり矛盾があってこそ、人間の感情だと思うので。
――音楽活動を続けていくうえで、何か目標のようなものはありますか?
luvis:フジロックに一度は出てみたいですし、アルバムも作ってみたいです。あと、これは夢物語と思われるかもしれないですけど、自分のスタジオが欲しいですね。ある程度都心から離れた場所、もしくは振り切って北欧とかでもいいかもしれない(笑)。
そこで好きなだけ音を鳴らしたいし、好きな人たちを呼んだりして。そして自分が歳を取ったら、若いミュージシャンにそのスタジオや機材を開放して使ってもらいたい。今の段階からこんなこと考えてるのもおこがましいですけど、「そういう環境があったらよかったな」って自分が思うようなものを、後続に渡していきたいんです。僕が死んでいなくなった後も、豊かな音楽が鳴り続けていて欲しいので。
――それもluvisさんの視座の広さを感じさせる話だなと思いました。人間ひとりの時間軸だけで物事を捉えていないというか。
luvis:僕は音楽はバカでかい生き物だと思ってるんです。自分も他の人もそのDNAの一部でしかない。だから、自分も何かを次に繋いでいくような存在でありたいですね。
――音楽っていう途方もない大きい流れの中に、それぞれが存在しているというか。
luvis:光って消えての繰り返し。それの一部でしかないんじゃないかなって。
――すごくおもしろい考え方だなと思います。
luvis:去年、仏教に興味を持っていろいろと調べるようになったんです。その考えが影響していますね。あと、音楽って食器に似ているなと思って。食器って、どんなに素晴らしい作品でも食材や料理がメインというか、そのために存在するじゃないですか。その姿勢ってすごいカッコいいなって思うんです。
音楽に当てはめると、音楽が食材で器が人間。相互に干渉し合うし、器によって美味しさも変わる。でも、器がないと食べ物もカオスな状態になりますよね。
――食べ物、料理として成立しにくい。
luvis:メインは音楽だけど、僕がゲートになってそれを届けて、聴いてくれる人がいないと成立しない。垂れ流しになってるだけじゃダメだと思うんです。結局、音楽が生きていくためには全員必要なんですよね。そうやって全員が繋がって、ライトのように点滅していく……だいぶスピってきちゃいましたけど(笑)。
―――(笑)。でも、それがluviさんのスタンス、表現を理解するにあたって大事な要素なんだなって思いました。
【リリース情報】

luvis 『from pier』
Release Date:2023.10.11 (Wed.)
Label:Spincoaster Inc.
Tracklist:
1. 桟橋より
2. Q
3. 蜃気楼
4. ふるさと
5. Dance
■luvis:X(Twitter) / Instagram