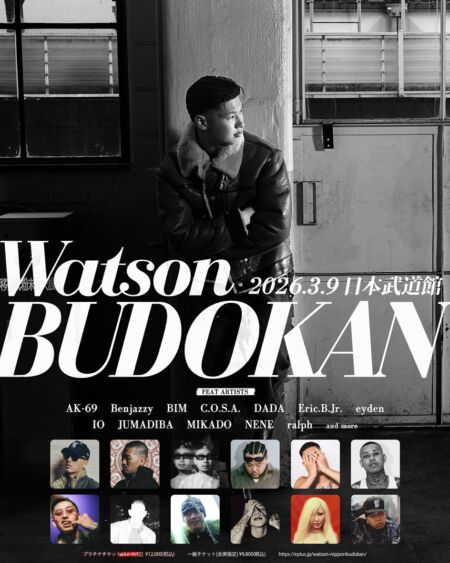水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミが、およそ9年ぶりとなるソロ・アルバム『沸騰 沸く ~FOOTWORK~』を本日5月15日(水)にリリースした。
この数年の間に、水カンでの活動以外にもiriやKID FRESINO、Chara、DATSなど、カッティングエッジなアーティストへの楽曲/リミックス提供を行い、アーティスト/プロデューサーとしての認知を拡大させたケンモチ。そんな彼が久方ぶりに上梓した待望の新作ソロ・アルバムは、なんと全曲ジュークという異色の作品に仕上がっている。
シカゴ発祥のBPM160を基軸とした高速ダンス・ミュージック=ジューク。そのタイトル同様、上音や展開では遊び心も効かせつつ、しかし基本はボーカルなしのストイックなダンス・ミュージックとなった本作。果たして、ケンモチがなぜ、このタイミングでジュークに惹かれたのか。今回はその謎を解き明かすべくインタビューを敢行。
また、9年前=水カン以前の活動についても改めて言及することで、彼の音楽家としてのスタートから現在地点、そしてこの先の展望までを予想させる内容となった。
Interview & Text by Takazumi Hosaka
Photo by 遥南 碧

DIYな活動〜Nujabes主宰レーベルからのリリースまで
――最新作についてお聞きする前に、これまでのソロ活動についても改めて振り返らせてください。2枚のミニ・アルバムをリリースした後に、Nujabesにフックアップされ、〈HYDEOUT PRODUCTIONS〉より2008年に『Falliccia』をリリース。大きな注目を集めました。まずはそこまでの経緯をお伺いしたいです。
Kenmochi:一番最初の話しをすると、中学生の時に近所に住んでいた友達がエレキ・ギターを買って、奥田民生の「息子」を弾いてたんです。そこで「うぉー! かっけぇ!」ってなって、僕もギター始めました。それが音楽を始めるきっかけですね。高校に入ってからは、楽器できるやつが集まって文化祭のためにバンドを組んで。当時はビジュアル系全盛期で、僕はBUCK-TICKがすごく好きだったんです。なので、BUCK-TICKとか、ボーカルが好きだったLUNA SEA、あとはL’Arc〜en〜Ciel、GLAYとかをコピーしていました。で、その時LUNA SEAが一回活動休止になるかならないかくらいの時で、SUGIZOさんがソロでドラムンベースを軸としたアルバム(1997年発表の『TRUTH?』)を、INORANさんがDJ KRUSHと一緒にヒップホップに接近したソロ・アルバム(同じく1997年発表の『想』、2011年にはボーカルのバージョン違いを収録し再発売)をそれぞれリリースしていて。そこからちょっとずつクラブ・ミュージックとかも聴くようになりました。
Kenmochi:それから、当時テクノ四天王と言われていたThe Prodigy、The Chemical Brothers、Underworld、Orbitalとかも聴くようになりました。今聴くと別にみんなテクノって感じでもないんですけど、当時はビック・ビートって言われていたりして、「おぉ、これはちょっとロックっぽいし聴きやすいぞ。カッコいい!」ってなって。そこからドラムンベースやテクノ、ハウスとかまで聴くようになって。そこで一番影響を受けたのが、大沢伸一さんのやっていたMONDO GROSSOの『MG4』(2000年)っていうアルバムで、生楽器を活かしたクラブ・ミュージックにすごい感銘を受けたんです。ハウスとか2ステップとかのビートの上に、サンバやボサノバ、あとはブラジリアン的な要素を加えていて。「これはカッコいいぞ!」と。その後、自分が〈HYDEOUT〉とかから出したインスト・アルバムのフォーマットはたぶんその辺で固まってきたんだと思います。
Kenmochi:ブラジリアン・ミュージックを取り入れたかったので、ガット・ギターを買って。ベースも自分で弾きつつ、MPC2000とかでリズム・トラックを組んで。当時は今ほどDAWも充実してなかったので、MTRにガシガシ録音して。トラック数足りないからピンポン録音とかを駆使して、インストの曲を作ってましたね。
――最初の商業的な作品リリースというのはどのタイミングなのでしょうか?
Kenmochi:それは結構曖昧なところで。特に求められることもなく自主でCDやレコードを作って、ディストリビューターとかも自分で見つけて、タワレコとかDMR(渋谷に位置していた老舗レコード・ショップ。2014年に閉店)とかにも置いてもらっていたんです。3枚目のアルバムも作っているタイミングで、僕の作品がたまたまNujabesの耳に触れる機会があって、「すごくおもしろいと思う。うちから出したい」っていう風に言ってくれて。「ぜひともお願いします!」っていう感じでリリースされたのが『Falliccia』ですね。〈HYDEOUT PRODUCTIONS〉の力もあって、それが世に広く認知されるきっかけになりました。
――なるほど。その後もいくつかソロ作品の発表が続くものの、水曜日のカンパネラも本格始動し、なかなか時間が取れなくなり……ということですよね。
Kenmochi:それもあるんですけど、2010年にリリースした『Shakespeare』ていうアルバム辺りを境に、ガット・ギターを軸にしたインスト作品っていうスタイルにちょっと限界を感じてきて。もうやることがあまりないなって思ったんです。
震災、ももクロ、Dir.Fとの出会いから水カン結成へ
――自分の中でちょっと飽きがきてしまったというか。
Kenmochi:そうなんですよね。次の作品からは違うことをやりたいなとうっすらと考えていた辺りで震災(東日本大震災)があって。それで精神的にも落ち込んで、あまり曲とかを作る気にもなれなかったんです。その時に、たまたまももクロの「ココ☆ナツ」っていう曲を聴いて、それですごく元気づけられて。それまではあまりJ-POPとかを聴いてこなかったので、日本語の歌詞で元気をもらう、みたいな体験をそこで初めて味わったんです。それで、こういう音楽もやってみたいなって思い始めたところに、(水曜日のカンパネラの)Dir.Fからお話を頂いて。彼は以前から「何か一緒にやりたいです」っていうことをずっと言ってくれてたんです。当初は僕の作った音楽をインスト・バンドで演奏するっていう企画もあったんですけど、「今はももクロとかが好きで」っていう話から、日本語の歌ものユニットを作ろうってなりました。それが水曜日のカンパネラです。
――Dir.Fさんとの出会いというのは?
Kenmochi:彼は普通に僕のCDを買ってくれてたみたいで。あとは僕が〈HYDEOUT〉からリリースする前に、“デザインフェスタ”に出展して、CDを自主販売してたんです。そこでたまたま出会って、交流が始まったっていう感じですね。
――その後、水曜日のカンパネラでの活動や、iriさんを始めKID FRESINOやDATS、Charaなどへの楽曲/リミックス提供などで活躍し、広く名が知れ渡っていくと。今回、およそ9年ぶりとなるソロ作品をリリースするまでの経緯は、本作のCDにも付属するセルフ・ライナーノーツに詳しく書かれていますよね。
Kenmochi:はい。tofubeatsさんもそういうの書いてますよね。インストだと、曲に関する文字情報とかってほとんどないじゃないですか。だから、買ってくれた人に何かサービスとかできたらなって思って。

――なるほど。このライナーノーツによると、昨年頃に時間ができたことに加え、イベントにDJ出演する機会があり、その際に自分の曲が欲しいと感じた。それが今回のソロ作品制作に繋がったと。
Kenmochi:水曜日のカンパネラとコムアイは、顔出しもしてるからそれなりに認知されてるんですけど。たまにイベントとかに自分がひとりで出させてもらった時に、あまり知られてないなって感じるのが寂しいというか(笑)。やっぱり、自分の看板を出して自分の店を開く、みたいな行為も必要だなっていうことで、活動を再開しようと思いました。なので、曲が溜まっていたからとかではなく、モチベーションが先でしたね。
――ケンモチさんのソロ作品という情報を聞くと、4つ打ちを軸としたクラブ・ミュージックに、ボーカルを上手くのせたポップな楽曲を予想する方も多いと思います。水曜日のカンパネラ以降に築いた自分のカラーのようなものから、敢えて距離を置くような作品を作った理由というのは?
Kenmochi:別に飽きたっていうわけじゃないんですけど、そういう曲は水曜日のカンパネラやxiangyu、その他のプロデュース・ワークでもやらせてもらえることですし。それをまた自分名義のアルバムでやっても、結局そういった作品のより規模が小さくなったバージョンになってしまうんじゃないかなって思ったんです。目新しさもないし、自分のソロ名義でやるんだったら、他の案件ではやらせてもらえないことをやらないと意味がないなと。今のケンモチヒデフミがやったら、一番「え?」って驚かれることをやりたかったっていうのもありますね。
――それでジュークに辿り着いたと。過去には水曜日のカンパネラでもジュークを軸とした「ウランちゃん」という曲もありました。
Kenmochi:そうですね、あれが唯一ジュークの曲ですね。今聴くとあまりジュークっぽくなかったりするんですけど(笑)。
「すごく奇妙で、おもしろい」 ジュークの魅力
――ジューク自体はアンダーグラウンドなシーンではかなり前からフォーマットとして定着していた印象があります。それこそ10年近く前から、ネットや国内でも局地的なシーンを形成してきました。ケンモチさんがジュークに最初に触れた、意識したのはいつ頃からなのでしょうか?
Kenmochi:僕はそんなにめちゃくちゃ音楽を掘ってるわけでもなくて。5〜6年くらい前から存在は知っていて、(水曜日のカンパネラの)『ジパング』(2015年)を作っていた時は、色々なレパートリーのベース・ミュージックをやろうっていう話になっていたので、そのひとつとして「ウランちゃん」を作って。
――ベース・ミュージックのサブジャンルのひとつとして認識していたと。今回アルバムを作るにあたって、ジュークに絞ることに決めた経緯というのは?
Kenmochi:アルバムを出すぞっていうところから考え始めて、何をやったらおもしろいかなって考えながら色々な音楽を聴いて。最初は普通の4つ打ちの曲もストックしていたり、ダブステップとかも作ったりしていたんです。そうやって試行錯誤していく中で、DJ Rashedの『Jukeworkz』(2009年)っていうアルバムに大きな影響を受けて。というのも、失礼かもしれないんですけど、めちゃくちゃ雑で荒い作りなんです。本人は意図していないかもしれないんですけど、楽曲制作を生業としているプロデューサー視点からすると、「なんじゃこりゃ!?」っていう世界観で。
――音も歪んでるというか割れてる。シカゴの、ジュークの原始的な熱が込められているというか。
Kenmochi:フットワーク以前の、ヒップハウスとかゲットー・ハウスとかって言われてたりするこの打ち込み方が独特過ぎて。ちょっといなたいというか。そこにガッツリ胸を掴まれてしまったんです。今のクラブ・ミュージックって、すごい洗礼されてきていて、トラップやフューチャーベースみたいな盛り上がっているシーンだと、みんな技術力で競い合っているような気がするんです。でも、元々はクラブ・ミュージックって、ロックやポップっていうもっと大きな潮流があった中で、それに対して、「おれたちにはロックやポップにはできないおもしろいアイディアがあるんだ」っていう、カウンターみたいなスタンスでスタートしたと思っていて。そういうアイディア先行みたいな姿勢が、最近のクラブ・ミュージックのシーンにはあまり見当たらないなと思っていた時に、DJ Rashedのジュークを改めて耳にして。
――アイディアとヴァイブスで勝負、みたいな。
Kenmochi:そうですね。こういう気持ち、忘れてたなって思って。それで、いっそのこと全部ジュークにしようと。
――サンプリングではなく、「ウランちゃん」のようにジュークのフォーマットを使いつつも、歌ものに仕上げるというアイディアも考えたりはしましたか?
Kenmochi:僕がジュークをおもしろいって感じるポイントのひとつとして、人間の声をボーカルとして扱わないっていう点があって。
――まるで楽器、ひとつの音色みたいに使うと。
Kenmochi:そこがすごく奇妙で、おもしろいなぁって思うんですよね。人間の声って、日常的に聞き慣れてるからこそ不自然なハマり方をすると異常に気になってしまうと思うんです。その違和感の中で、ベースがブンブン鳴って、超高速でダンスを踊ってる人がいて。何から何まで珍妙なんですよ。その特性を活かすためには、ボーカリストに歌ってもうらうよりも、サンプルとかをぶつ切りにして、プリミティブな手法を取った方が、ジュークのおもしろさが際立つかなと思って。
――ちなみに、曲のタイトルもとてもユニークですよね。何か付け方の法則みたいなのはあったりしますか。
Kenmochi:曲の何となくのイメージと、あとはみんなが知ってる固有名詞ですね。あんまりカッコいい名前付けてもしょうがないなと思って。あとは、作業場にたまたまAesopのスプレーが置いてあったりとか、その横にタイガーバームが置いてあったりして。そこから取ったり(笑)。
――なんとなくその辺りは予想できていました(笑)。目についたものシリーズみたいな。
Kenmochi:あと、「RoboCop」っていうのは、人の声がすごくぶつ切りにされているのが、なんかロボコップ感あるなって思って。『ロボコップ』(原題:RoboCop、1987年に公開された映画のタイトルであり、登場するサイボーグの名前)ってもう僕ら世代じゃないと出てこないワードだと思うんですけど、あのちょっとレトロな感じもジュークっぽいなっていう。


大事なのは「組み合わせの暴力」
――これまでの作品を聴かせてもらって、パーカッシブな音使いが特徴的だなと思いました。これはもちろんブラジル音楽などへの興味も大きく関係していると思うのですが、今回のジュークにも繋がるような気もします。
Kenmochi:もちろんパーカッションとかの音もすごい好きなんですけど、それとは別に、ブラジルの音楽って明るいんだけどちょっと切ない、っていう感覚がありますよね。サウダージ感とでも言うんでしょうか。個人的にあれが大好きで。基本的にはループ音楽で、みんなでバカ盛り上がりするんだけど、どこか切ない、みたいな。〈HYDEOUT〉とかから出してる時は、それがケンモチ節として定着していて。その9年前の作品を今の自分のモードで聴くと、ちょっとシリアス過ぎるんですよね。部屋聴きする分にはいいんですけど、あまりクラブとかで機能しないなっていうのはずっと思っていて。それをジュークのフォーマットに乗っけることで、いい意味でシリアスさが失われて、バカになって踊れるような気がして。その組み合わせの意外性というのが、「ジュークの人」じゃない自分の強みでもあると思っていて。
Kenmochi:逆にジュークは昔僕が身を置いていたクラブ・ジャズとか、歌もののハウスとかを作ってる人にはできないようなビートのアプローチなんですよね。これを合わせると、めちゃくちゃ意外性があるんじゃないかと思って。水曜日のカンパネラの時もよく言ってるんですけど、「組み合わせの暴力」っていうのを大事にしていて。本来一緒になるはずのないものをバチっと合わせて、違和感ありありなまんまお茶の間に流すっていうのが、実はいつも心がけていることなんです。普通、相性のいいもの同士を掛け合わせて、もっと美味しい料理作ろうとするじゃないですか。でも、僕らはそもそも混ざらないようなものをぐちゃっと強引に混ぜて、バーンと世に出すのが好きなんですよね。
――制作の記憶で特に残ってる曲などはありますか。
Kenmochi:1、2曲目(「Aesop」「BabyJaket」)ですかね。特に1曲目は、違和感の法則性を見つけたような気がして。これはイケるなと手応えを感じたのを覚えています。いつも意識してるのは、この曲が急にラジオでかかったらリスナーがどんな顔をするだろうかっていう部分で。僕は、この曲が流れてきたら笑っちゃうなって思ったんですよね。ゴリゴリとしたラップ調のボーカル・サンプルと、ストリングスとかのシリアスな上音が全然合ってなくて。それがおもしろいなと。
――まさしく組み合わせの暴力ですよね(笑)。
Kenmochi:そうなんですよね。きっとみんな聴いたら混乱するだろうなっていう。
――ちなみに、サンプリング・ソースはどのように?
Kenmochi:ネットで(権利的に)クリーンなサンプル・パックをいっぱい購入しました。探せばいっぱい出てくるし、僕が使ってるものも簡単にわかると思います(笑)。

――昔の曲を今改めて聴くと「ちょっとシリアス過ぎる」とのことでした。それは自分の内面的な変化なのか、それとも何か外的な要因が大きく影響しているのか、どっちだと思いますか。
Kenmochi:外的な要因が大きかったと思いますね。それまでは自由ですけど、インストなので基本的にひとりで完結していて。そんなに視野を広げるまでもなく、好きなことを好きなようにやってるっていう感じでした。その時は商業的な部分を考える必要もなかったんですけど、カンパネラとかを始めてからは、やっぱり僕以外の人の意見もあるし、こういう風にやったらおもしろくなるっていう感覚も芽生え始めて。そもそも、おもしろい音楽を作ろうっていう考え自体が水曜日のカンパネラ以降に生まれてきたものですね。そういう風に変わってから昔の自分の曲を聴くと、外に開けてないというか、少し視野が狭いような印象を受けるようになって。
――先程も少しお話に出たように、今回のソロ・アルバムを作るきっかけのひとつが、自分のDJセットでの持ち曲を作りたいということでした。その結果、でき上がったのがボーカルなしの全曲ジューク作品というわけですが、自分のDJセットとして、今作の曲を使うイメージはできていますか?
Kenmochi:はい。低音はちゃんとクラブでも魅力的に鳴るように意識して作りましたし。あと、自分のもち曲があまりない時は、オファーを受けたときもイベントの空気を読んで、今日は4つ打ちにしよう、今日はヒップホップに寄せようって考えたりするんです。でも、こうやってソロでジュークのアルバムを作ってしまえば、その上でオファーをもらうということは基本的に「じゃあジュークでいいんだね」「ジュークを求めてるんだ」っていう風に受け取れるじゃないですか。「これが僕です」っていう名刺代わりの音源が出てるので、頼まれた理由っていうのも明確になるというか。これは便利になるなって、今回改めて思いましたね。
――じゃあ、今後もしオファーが来たらジューク・セットでのDJを?
Kenmochi:そうですね。まぁ、このアルバムが純然たるジュークなのかって言われるとちょっと首を傾げたくなりますけど、このテイストでやろうとは思ってます。ただ、天の邪鬼なので、何か飽きてきたら違う感じでやるかもしれないですけど(笑)。

――ちょっと穿った質問をさせてもらうと、ジュークは決して世に幅広く浸透している音楽ではないけど、濃密なシーンが形成されているという印象です。そういう古参のジュークDJ、プロデューサーたちから今作がどういう風に見られるかっていうのは考えますか?
Kenmochi:確かに、そこは僕もすこし気になってたんです。でも、アルバム制作前にたまたま恵比寿BATICAでDJさせてもらう機会があって。そこで、いつものセットにジュークを組み込んだら、終わった後にジュークのパーティをやってるAKIOCAMさんから声をかけてもらって。「Rashedかけてましたよね!」っていう感じで仲良くなって。「今度ジュークのアルバム作ろうと思ってる」って言ったら、色々な方を紹介してくれて。その後、実際にジュークのパーティにも行ったんですけど、D.J. Aprilさんとか、D.J.G.O.さん、ファラカミ(Keita Kawakami)さんとか、「ジュークやってる人は少ないから、超ウェルカムです!」みたいな感じで、みんな暖かく迎えてくれて。
――なるほど。特に日本ではプレイヤーが少ないし、好きな人を見つけるとみんな仲良くなる、みたいな。
Kenmochi:しかも、僕と同年代ぐらいの人たちも多くて。もはやジューク/フットワークやってくれる人はみんなウェルカム! っていう感じで。すごく暖かく受け入れてくれました。なんなら最近、フットワークのダンス・レッスンにも通い始めましたし(笑)。
Kenmochi:RP Boo(フットワークのオリジネーターとも称されるシカゴのDJ/プロデューサー)とか、ダンサーじゃないですか。やっぱり自分の作った曲で踊れるのっていいよなーっていう思いがずっとあって。全然ダンス経験もないのに、いきなりシカゴ・フットワークのダンス・レッスンに行きました。今のところ玉砕続きで、全然踊れてないんですけど(笑)。
――本場のジュークDJの動画とかを観てると、取り巻きとかが勝手に前に出てきて踊ったりしますよね。
Kenmochi:ああいうのが最高ですよね。フットワークのバトル・トラックとかって、音だけ聴いてもわからないじゃないですか。やっぱり、あれをベースに踊ってる人がいて、こういう音楽なんだっていうのが初めて100%伝わる、みたいなところもあるので。できればダンスも少しは踊れるようになりたいなと思っています。
――確かに。個人的にも、話題になった〈Planet Mu〉からのコンピ(『Bangs & Works Vol.1 (A Chicago Footwork Compilation)』、2011年発表)をヘッドホンでひとりで聴いた時、最初は正直あまりよくわからなかった記憶があります。
Kenmochi:しかも、ベースが三連符ってありえないですよね。ジュークはキックとベースのバランスの取り方もちょっと異常で、いわゆる普通のスピーカーとかで聴いてても、キックの輪郭が全然ないから、「あれ? なんかベース鳴ってる?」みたいな感じなんですけど、クラブに行って聴くと、バインバインに出てて低音を体で感じるっていう。おもしろいですよね。

「音楽1年生って感じでフレッシュにやっていきます」
――では、今作を作り終わっての感想をお聞きしたいです。全曲ジュークのアルバムを作った今の方向性というかカラー、ムードはどのような感じなのでしょう?
Kenmochi:まず、ジュークやるのは今回だけかもしれないです(笑)。作り終わって改めて聴くと、全然ジュークでもフットワークでもないなって曲はいっぱいありますし。感想という意味では、9年ぶりに自分のアルバム出すっていう行為が新鮮でした。曲のタイトル、カバー・アートワークのデザインとか、全部自分で決めるじゃないですか。あとはリリースのスケジューリングとか、イベント開催準備とか、そういう諸々の行為が、昔は嫌ってほどやってたはずなのに、この9年間は全くやってなかったので。音を作ること以外の作業がフレッシュでしたね。水曜日のカンパネラ以外の外部仕事だと、ミックスダウンのところまで終わったらあとはアーティストさんの作品として自分の元から羽ばたいていくっていう感覚なので。
あと、早くも次の作品も作ろうとは思っています。今はまた変な組み合わせがないか色々考えたり、探している段階ですけど。音楽的には今、ゲットー感のあるサウンドに惹かれる傾向にあります。xiangyuと一緒に作ってるゴム(Gqom)っぽい曲とかジャージー・クラブとか。
――ケンモチさんの昔の作品を聴いていた時に、エキゾチックというか、異国情緒溢れる要素が多いのも印象的だなと思いました。もちろんブラジル音楽もそうですし、今の話を聞いていても、元々固有の風土を強く反映した音楽に惹かれるところがあるのかなと。
Kenmochi:クラブ・ミュージックばかりを聴いていた時期のちょっと後に、『ミュージック・マガジン』を片っ端から読むっていう時期があって。中村とうようさん(音楽評論家/『ミュージック・マガジン』の前身、『ニュー・ミュージック・マガジン』を創刊)とかがいらっしゃった時期とか、ものすごく濃密な民族音楽の特集が組まれていたり。そういうのを読んで、とりあえず片っ端から聴いていた時期もあって。そういう民族音楽とか宗教音楽とかって、テクノの延長線上にあるんですよね。アフリカの民族音楽とか、インドネシアのガムランとか、ああいうのって、ずっと同じビートが一晩中続いたりとかしていて。
――確かに。ある種トランス状態になるための音楽というか。
Kenmochi:最初の1、2分で何かが起きるわけじゃなくて、それを10分、20分と続けていった時の精神が高揚する感覚は、ほとんどクラブ・ミュージクと同じだなってことに気がついて。一時期、民族音楽とか宗教音楽でノリノリになってた時期があるんです。家で、ひとりで。それで、一番踊れるビートは何なのかって考えていくと、もうドローン・ノイズみたいなのあるじゃないですか。Vladislav Delayがリリースした『Demo(n) Tracks』(2004年)っていうアルバムがあるんですけど、とにかく「シュワー」「ジョーン」みたいな感じの、ノイズとディレイだけで構成されていて、「これが1番踊れる!」ってなったんです。
――ドローンで踊れる。
Kenmochi:皆さんがどうやって聴いてるかあまりわからないんですけど、僕は踊れるって思って。逆に足動かさないで聴いてると少し辛くなってくるような気もするんです(笑)。そういう“ドローン期”の後に、さっき話した通り震災が起きてももクロにハマるという現象が起きたんです。振り幅がえげつないですよね(笑)。
――でも、そういった音楽遍歴を経て、水カンに至るっていうのはすごく繋がっているように見えます。
Kenmochi:反動でポップスがすごい楽しく聴こえてきたんでしょうね。民族音楽は今でもすごく好きなんです。聴いたことないものがいっぱい出てくるから。
――なるほど。
Kenmochi:あと、自分の中のムードという意味では、去年の後半くらいから「人生一度きりだから何でもやっちゃおう」みたいなモットーを掲げるようになって。ジュークのアルバムを作ったり、ダンスを習い始めるのも、これまでの僕だったら忙しいことをいいわけに諦めてたと思うんですけど、ノリと勢いで動けるなら動こうって考えるようになって。
――自身の中で大きな変化が起きたと。
Kenmochi:たぶん、元々はそういう性格だったと思うんです。でも、3年くらい前に骨を折って、そこでちょっと一回落ちた時期があって。アメリカの“SXSW”で骨折して、色々なことが重なり2重3重に落ち込むことになり。そこからまた復活してきたというか。震災で落ちて、カンパネラで楽しくなって、骨折ってまた落ちて。それで去年くらいから盛り返してきているのが今、っていう感じですね。
――そういった考えというのは、先程お名前にも上がりましたし、インタビューも行ったxiangyuさんとすごく被るような気がします。(同日にはケンモチ同席の元xiangyuのインタビューを敢行。後日掲載予定)
Kenmochi:そうですね。xiangyuと一緒に音楽制作しているうちにそういうマインドをちょっと分けてもらったっていうのもあるかもしれないです。
――相互に良い作用を受けつつ。
Kenmochi:はい。xiangyuも去年から本格始動したばかりで。その音楽1年生を側で見ながらやる気をもらったっていう部分もありますね。僕も再スタートじゃないですけど、今はもう音楽1年生って感じでフレッシュにやっていきます。
――最後に、ひとりで作り上げた自分名義の曲を出すのと、曲を提供、もしくは他の人と一緒に作り上げるのと、どっちの方が自分に向いてると思いますか。
Kenmochi:ケース・バイ・ケースですね。両方ともできるのがいいのかな。CMの曲とかもそうですし、アーティストさんの曲も。僕は10年間サラリーマンやってきたんで、人に合わせて制作することも全然嫌じゃないんです。オリジナル作品ではちょっと変なことをやって、発注受けた仕事に対しては的を絞って良い球を打ち返す。そういうアーティストになりたいですね。どっちかに偏るのはあまり望んでないです。

【リリース情報】

Kenmochi Hidefumi 『沸騰 沸く ~FOOTWORK~』
Release Date:2019.05.15 (Wed.)
Label:KUJAKU CLUB/孔雀倶楽部
Tracklist:
01. Aesop
02. BabyJaket
03. RoboCop
04. Jaburo
05. Fish Sausage
06. Mountain Dew
07. Hippopotamus
08. Fight Club
09. Hacienda
10. Tiger Balm
【イベント情報】
Kenmochi Hidefumi 沸騰 沸く ReleaseParty
“点火”
Kenmochi Hidefumi 沸騰 沸く ReleaseParty Day1
日時:2019年6月19日(水) OPEN 19:00 / START 19:30
会場:東京・恵比寿BATICA
料金:ADV ¥2000 / DOOR ¥2500 (各1D代別途)
出演:
Kenmochi Hidefumi
DÉ DÉ MOUSE (DJ)
xiangyu
==
“再点火”
Kenmochi Hidefumi 沸騰 沸く ReleaseParty Day2
日時:2019年6月20日(木) OPEN 19:00 / START 19:30
会場:東京・恵比寿BATICA
料金:ADV ¥2000 / DOOR ¥2500 (各1D代別途)
出演:
Kenmochi Hidefumi
D.J.G.O.
KΣITO
みとこんどりあ (DJ mitokon)
……and more!
[VJ]
KUJAKU CLUB
ご予約方法(E-mail)
宛先:kenmochi.official★gmail.com (★→@)
件名:ご予約希望日
本文:内容下記3点
・代表者名(カタカナ・フルネーム)
・ご予約希望日
・予約枚数
※ご返信に数日かかることがございます。
※こちらからのメール返信をもちまして予約の完了となります。
※ご予約の締め切りは前日の23時となります。
※料金につきましては、当日お店にてお支払いいただきます。