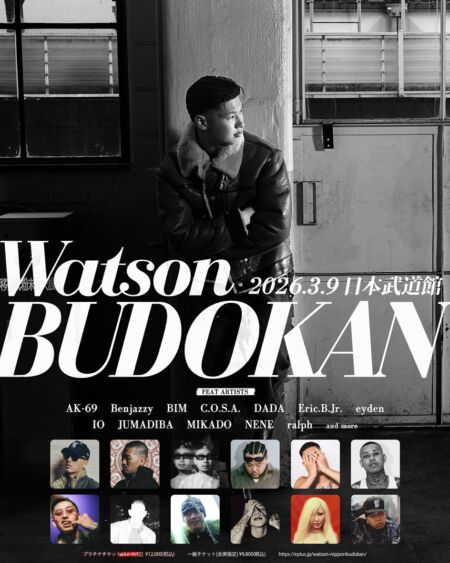2017年、台湾で行われたヒューマンビートボックスのアジア一決定戦を制し、日本人史上初のアジアチャンピオンの座を獲得。スイスで行われた世界大会ではソロ部門での日本人史上最高位を勝ち取るなど、数々の輝かしい経歴を持つビートボクサー・BATACO。しかし、そんな日本を代表するビートボクサーがある日、突如シーンの表舞台から姿を消した。
それからおよそ5年の月日が流れた今年10月、BATACOは活動再開を告げる新曲“Prolegomenon ft. SHOW-GO”を引っ提げ、シーンへの復帰を果たした。シーンから姿を消していたその期間を「修行期間」と位置付け、ビートボックスを音楽表現としてどのようにアウトプットするべきかを模索してきたBATACOは、ビートボックスを「歌唱の延長線上」として捉え直すという新たな表現論を確立。その実践の場として制作された新曲では、気鋭のビートボクサー・SHOW-GOを迎え、ビートボックスという表現の新たな可能性を示している。
今回のインタビューではそんなBATACOに、ビートボックスの新たな可能性や、今後の展望、そしてシーンの未来について話を訊いた。
Text by Jun Fukunaga
Photo by Ryo Sato
ビートボックスシーンと音楽シーンの断絶
――およそ5年ほどの「修行期間」をどのように過ごされていたのでしょうか。
BATACO:この5年間は、ビートボックスを音楽の表現としてどのようにアウトプットするのがいいのかを模索していました。その中で見つけたコンセプトが、「ビートボックスをラップや歌の延長線上として捉える」という考え方です。つまり、従来は(ビートボックスを)リズムマシンやドラムといった楽器の延長線上に位置付けていましたが、歌唱の延長線上としてビートボックスを配置するということ。
そこからこの5年間はビートボックスをどのように表現するのがいいのかを模索していました。……その一方で、作曲、ミックス、マスタリングなど楽曲制作には多くの工程がある中で、完全にひとりで作り切るのはちょっと違うなと思うようにもなって
――なぜそう思われたのですか?
BATACO:これに関しては、有名な寿司屋「すきやばし次郎」の店主のドキュメンタリー映画『二郎は鮨の夢を見る』を観たことがきっかけです。それまでは、職人さんが最初から最後まで手がけているのだと思っていたのですが、実際は仕入れの選別は専門の人に任せている。寿司作りも意外にチーム戦だったんだということを知って、自分も専門家を探してチームで音楽を作りたいと思うようになりました。
――では、そこから制作のためのチーム作りが始まったと?
BATACO:そうですね。アレンジャーに関しては、いろいろな人に相談していたのですが、あるとき、Spotifyのおすすめで出てきた曲がめっちゃよくて。その曲について調べてたら、偶然にもその人が渋谷でその日にライブすることがわかって。そのときは彼はメインではなく、バンドメンバーとしてギターを弾いてたんですけど。歌い手の子も知り合いだったので、その足でライブ会場に行って紹介してもらいました。
――ちなみに、その方のお名前は?
BATACO:〈w.a.u〉に所属しているプロデューサー/ギタリストの01sailくんです。それが今から大体3年前ですね。同時期に知り合いの伝手でミックスエンジニアを紹介してもらえたことで、曲作りの体制はある程度整ってきました。
そもそも体制を整える必要性があると思ったのは、ビートボックスは世間的に「パフォーマンスをライブでみせるもの」と強く認識されているというか、まだ録音芸術としては認められていないと感じていたからでもあって。
――ビートボックスシーンはいわゆる音楽シーンとは別のところに存在している、ということですか?
BATACO:はい。ビートボックスシーンと音楽シーンはかなり離れていて、その間には断絶があるんですよね。ビートボックスシーンに自分はいるけど、音楽シーンの中にはいないという感覚があるんです。だからこそ、その中に自分も入っていく必要性を感じています。
そこで音源をレーベルから出したいと思ったのですが、そのためにはまずレーベルに認めてもらう必要があります。でも、自分がやっていることをちゃんと伝えるためには音源だけでなくMVも必要だと思いました。その制作費をどうやって捻出するかが当時の悩みでしたね。
――結果的にその資金はどうやって捻出されたのですか?
BATACO:学生時代に所属していたクマ財団に、元財団生も対象とする制度が新しくできたんです。そこで自分でMVの資料を作り、プレゼンして企画を通して支援してもらえるようになりました。
そしてそのMVを〈SPACE SHOWER〉のスタッフさんにお見せしたところ、いい反応をもらえて。それで今回、“Prolegomenon”をシングルとしてリリースできることになりました。
SHOW-GOと共に目指した「誰もやっていない表現」
――新たな表現を模索していたという「修行期間」は、具体的にどのような取り組みをされていましたか?
BATACO:とにかくたくさん曲を作って実験していましたね。もちろんビートボックスの練習もしていましたけど、それだけではなく、さっきお話したようにもっと音楽シーンに入っていくための道筋を探していました。
――新曲“Prolegomenon ft. SHOW-GO”について、「序論」「前置き」を意味するタイトルや、この楽曲に込められた想いを聞かせていただけますか?
BATACO:この曲は一度表舞台から去った僕が新たにやり直そうという決意を表明した最初の一曲です。「これからこれでやっていくぜ」というスタンスをみせる曲になっていているので、タイトルも“Prolegomenon”と名付けました。
3年くらい前に作り始めた曲ですが、制作中にすごく手応えを感じたのと、自分がこれからやろうとしていることを一番表現できている曲だったので、再始動を告げる一曲目に選びました。
――先ほどアレンジャーの方を迎えたという話もありましたが、具体的にどういった工程で制作されたのですか?
BATACO:まず僕がトラックを含めて、ある程度大枠を作ります。それをアレンジャーの01sailに渡して、アレンジ後に戻してもらったものをこちらで修正してから最後は一緒に2人で詰めていく。そうしてできた曲をエンジニアさんに渡すという工程で制作しました。
――SHOW-GOさんをコラボレーターに迎えていますが、その理由を教えていただけますか?
BATACO:SHOW-GOとは大会でよく一緒になったりして、芸人さんでいう「同期」みたいな絆を感じているんです。今回、彼をフィーチャリングに迎えたのは、この曲にはリファレンスとなるものが全くなかったことが大きな理由です。この曲で僕が求めていたものはまだ誰もやっていない表現でした。そんな挑戦的な作品に呼べるのは、SHOW-GOくらいしか思いつかなかった。
それにも関わらず、SHOW-GOはとても上手に乗りこなしてくれたというか、僕の予想を超える120点の内容で返してくれました。それにインスパイアされて、自分のパートを録り直したりもしましたし、結果的に僕の表現自体のブラッシュアップにも繋がりました。
――具体的にSHOW-GOさんにはどういった要素を求めていたのでしょうか?
BATACO:今回はトラックがあって、その上にビートボックスを乗せるとき、表現としては「刻むようなビートボックス」を想定していました。その場合、他のビートボクサーはテクニックを前面に押し出して、たくさん刻みがちになるんですけど、僕が求めていたのは、そんな風にこれみよがしにやるのではなく、もっと「上品な刻み」だった。そのエレガントな刻みを巧みに表現できるのは、やはりSHOW-GOだけだなと。
――“Prolegomenon”で目指したという「まだ誰もやっていない表現」という部分について、もう少し具体的に教えてもらえますか?
BATACO:こだわったのはビートボックスによる質感表現です。ボーカロイドと生歌では音の質感が違うように、人間の口から出る音には楽器など他のものには出せない独特の温かみがあります。その温かみを持った質感的な表現フロウというか、テクスチャーの流れが迫ってくるようなイメージが、僕が考えている新しいビートボックスの表現コンセプトです。
その質感表現という意味では、音を触覚に変換する装置「Synesthesia X1(シナスタジアX1)」を使って、実際にその音のテクスチャーのフロウを感じ取れるようにし、それを楽曲やMVでの表現に落とし込んでいます。
「歌唱としてのビートボックス」
――従来の歌唱とビートボックスの関係性について、BATACOさんはどのように捉えているのでしょうか?
BATACO:ビートボックスをやっている感覚は喋っている感覚に近いというか、ただ音が違うだけで、本当に会話のような感じでビートを刻んでいくんです。Reeps Oneというイギリスのビートボクサーも同じようなことを話していて、『We Speak Music』という彼のドキュメンタリーがあるのですが、そのタイトルもそういった言語的な側面を強調しているように感じます。
そしてあるとき、ビートボックスは言語が違うだけでラップのようなものなんじゃないかって思ったんです。セッションではみんな会話をするような感じでビートボックスをやっている。
――だからこそ、「歌唱」として捉え直すことは自然なことだと。
BATACO:歌やラップも含めた歌唱に、ですね。個人的な考えですが、歌唱というのは表現形式の文脈だと思っていて。80年代にラップが誕生しますが、ざっくり言うとその前の歌にはメロディがあって、そこに歌詞が付いているというコンテクストでした。細かく言えばその間にはレゲエのトースティングなどいろいろとあると思うんですけど。
ただ、ラップが生まれたことで、「メロディがなくてもいい」という感じで、表現としてのコンテクストが書き換わったと思うんです。そう考えると、その文脈の中に新たに「ビートボックス」も加えられるんじゃないかと。
――リズムマシンやドラムの代替ではなく、歌唱として曲の中に組み込む際、どのようなことを意識していますか?
BATACO:リズムマシンやドラムと歌唱の大きな違いは、それがメインになるかどうかだと思います。曲を構成するとき、基本的にボーカルはメインになりますよね。一方、リズムマシンや楽器は曲の土台や周りを作ったりと、どちらかといえば引き立て役になるものだと思うんです。
ビートボクサーの曲に関してもそれは同じで、大体のビートボクサーは、ビートボックスの音を素材にしてトラックを作っているんですけど、僕が今やっているのはそうではなく、歌のように曲の真ん中にビートボックスを置くという構成。つまり、ビートボックスを前面に押し出すということです。そうすることでこれまでとは違うおもしろい景色が見えてくると思っています。
――ビートボックスをワンショットのサンプル的に使って曲を作るのではなく、ボーカルのように独立したものとしてメインに配置する。
BATACO:そうですね。キック、ハイハットなどビートボックスの音を単体で録り、それをDAWやサンプラーに入れて、切り貼りしながらビートを作ったとしても、それは打ち込み的な感じになってしまう。それに対して、僕の曲は一個の身体がずっとあるというか、メロディラインのように音のフロウがずっと繋がっているイメージですね。そういう意味では従来のビートボックスの曲よりも、もっとフィジカルなビートボックスの使い方をしていると言えます。
――そういった表現方法にはどのようにして辿り着いたのでしょうか。
BATACO:2018年頃にCM用の楽曲を制作していたとき、たまたま今回のような構成の曲ができたんです。トラックのためにビートボックスがあるのではなく、元々トラックがあって、その真ん中にビートボックスを乗せるっていう。
それを後から振り返ってみて、「あのビートボックスは歌唱と言えるのでは?」って気づいたというか。あと、Reeps Oneの「We Speak Music」というスローガンの先に行きたいと思っていたことも、きっかけのひとつでした。
――このようなビートボックスにおける新たな表現形式について、周りのビートボクサーやリスナーからはどのような反応がありましたか?
BATACO:やっぱり従来にない表現ということもあって、新しいものとして捉えてもらっている感じがします。MVへのコメントを見ていると、自分が期待していたよりもポジティブな反応が多いですね。発表する前は、もしかしたら冷たくあしらわれるかもって思っていました。それは新しい表現ということもありますが、そもそもビートボクサーが楽曲を発表すること自体が割とハードルが高いというか。正直、普通にパフォーマンス動画を公開する方が反応がいいんですよね。
――ビートボックスシーンのファンからはパフォーマンスやバトル動画のようなものが求められている。
BATACO:コロナ禍を機にビートボックスバトルのパフォーマンス動画がオンラインに増えたりと、シーンが盛り上がっていることは事実なんですけど、それはヒップホップにおけるMCバトルのようなもので。楽曲とバトルパフォーマンスは別モノとして捉えられている印象があります。
だけど、僕としてはビートボックスが好きな方には楽曲の評価もしてほしい。そして、ビートボックスのバトルファン以外の層、もっと言えば、音楽が好きな人にも伝わってほしいです。それで認めてもらえたら、今よりもビートボクサーの曲をもっと聴いてもらえるようになると思うので。
――ビートボックスシーンの外側にアプローチする必要性を感じていると。
BATACO:そうですね。ビートボックスバトルが盛り上がってること自体はとてもいいことだと思っています。でも、ビートボクサーが活躍できる場がもっと広がってもいいんじゃないかとも思っていて。今はバトルが盛んですが、ビートボックスシーン自体ももっと多様化していかないと、いつか廃れてしまうというか、成長が止まってしまうんじゃないかと思うんです。そのためにも、今おっしゃられたように外側へのアプローチも必要だと考えています。
「グラミー賞にビートボックス部門を」
――「グラミー賞にビートボックス部門を創設する」というビジョンも掲げていますが、この意図についても教えてもらえますか?
BATACO:これは自分の希望みたいなものなんですけど、以前Chance The Rapperの活躍によって、グラミー賞の選考基準が変わりましたよね。
――それまで選考外だった「フリーダウンロード」でのリリース作品が、Chance The Rapperのミックステープをきっかけに対象になり、大きな話題となりました。
BATACO:彼の活躍と圧倒的な支持を考えると、選考基準の変更を認めざるを得なかったわけですよね。だから、ビートボックスシーンが今後もっと発展していって、それくらい影響力を持つ大きな存在になれば、自然とグラミー賞にビートボックス部門が創設されるんじゃないかなって。ただ、それは自分ひとりでは絶対に実現できないことなので、いろいろなビートボクサーが「歌唱としてのビートボックス」だったり、もしくはさらに新しい表現に挑戦する必要があると思っています。
先日発表した“Prolegomenon”のリミックスは、このノウハウを他のビートボクサーにも共有するという意図もあります。この表現方法がみんなに伝わって、ビートボックスシーンの発展に繋がれば嬉しいですね。
――ビートボックスにおける新しい表現を確立されていく中で、今後はどのような展開を考えていますか? 特に実現したい企画や挑戦してみたいことがあれば教えてください。
BATACO:直近ではMVで使った、共感覚体験装置の「Synesthesia X1」を使って、一般の方にもビートボックスの音を肌で体験してもらえる場を作りたいなと考えています。
また、音楽を作り続けるのは当然として、単に自分の作品をリリースするだけでなく、もっと体験型のエンターテイメントにできるよう、表現を拡張させていきたいです。あとは海外のレーベルと契約して、「歌唱としてのビートボックス」という表現を世界に広めていけたらなと。
――最後に、長らくBATACOさんのカムバックを心待ちにしていたファンの方々へ、メッセージをお願いします。
BATACO:今回、活動再開と共に新曲をリリースさせてもらいましたが、すごく温かい声を頂いて本当にありがたく思っています。これからもまだまだいろいろな準備をしているので、そちらもぜひご期待ください。
SHOW-GO コメント
▼コラボ曲“Prolegomenon”について
BATACOさんから最初に楽曲に参加してほしいと連絡が来て、僕は一人での制作ばかりしかやってこなかった身なので、新しい形のお誘いにワクワクしました。
そしてBATACOさんが話してくれた“Beatbox”というものの魅力や特性の解釈に、僕にも共通する部分があって、意気投合したのを覚えています。
僕のverseを作る上でのこだわりとかは特になくて、ひたすらに自由に、無心で音の上で遊ばせてもらったという感覚です。
Beatboxというものを再定義する、BATACOさんらしい挑戦的でクールな楽曲になっていると思います!
▼BATACOのカムバックについて
BATACOさんは昔から画面越しに見ていた憧れの先輩ですし、世界大会でも戦った思い出もあります。東京だったり、京都だったり、ちょこちょこご飯に行ったりして色々お話していたので、今回遂に表舞台で動き出したか! という感じで嬉しいです。
僕も刺激をもらいながら、色々新しいこと挑戦してえなぁ〜なんて思ったりです。

【リリース情報】

BATACO 『Prolegomenon feat. SHOW-GO』
Release Date:2024.10.28 (Mon.)
Label:Immanence Production
Tracklist:
1. Prolegomenon feat. SHOW-GO
==

BATACO 『Prolegomenon (REMIX) [feat. COLAPS and RIVER’]』
Release Date:2024.11.06 (Wed.)
Label:Immanence Production
Tracklist:
1. Prolegomenon (REMIX) [feat. COLAPS and RIVER’]
■BATACO:X(Twitter) / Instagram