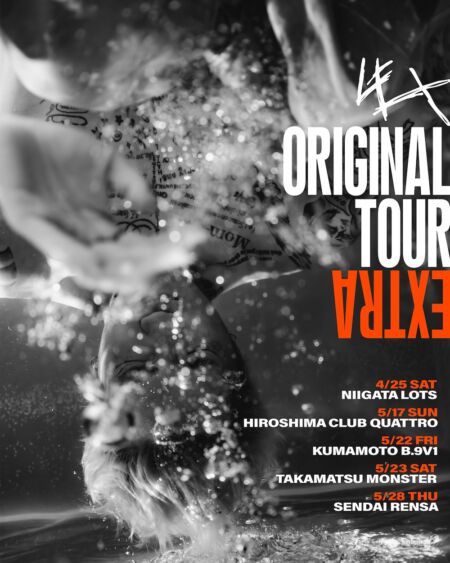都内を拠点に活動する5人組、gatoが1stアルバム『BAECUL』を10月14日(水)にリリースすることを発表。合わせて、「G0」、「ame」に続く3か月連続シングル「dada」を9月2日(水)にリリースした。
同曲はライブではすでにおなじみ。トラップやエレクトロ、パンクのエネルギー、切れ味鋭いリリックなどが混然一体となり爆発し、フロアに狂喜乱舞の渦が巻き起こる、彼らのアッパーで挑発的な側面がダイレクトに表れた一撃必殺ボムだ。しかし、改めて音源として聴いてみると、そのミクスチャー感覚は明らかにネクスト・フェーズ。そこにはタイトルのもとになった、第一世界大戦中に始まった芸術運動“ダダイズム”とリンクしてくる部分があると、バンドのフロントマン・ageは話す。
人の理性や作為、作品に意味を持たせることを根底から否定したダダイズムの概念から、彼は何を見出したのか。今回は「dada」の世界観をフォトで表現した写真家・石間秀耶による『Overdose』からのセレクションと共にインタビューを展開していく。
Interview & Text by TAISHI IWAMI
Photo by Hideya Ishima


――ageさんのルーツは大きく2つ。ひとつはポストハードコアやエモといった生々しく感情を描き出すバンドを好きになったこと。もうひとつはジャズ・バーのベーシストであったことだと私は認識しているのですが、いかがですか?
もとを辿ればそうですね。中学生の頃に、地元の木更津でバンドをやっていた憧れの先輩が、Rage Against The MachineやPink Floydを勧めてくれて、そこから自分なりにいろいろと探っていくうちにハードコアを好きになったんです。あとはCD屋さんで、エレクトロだけどロックの基本みたいなコーナーにも置いてあったDaft Punkにもハマりました。だから今の“バンドでエレクトロをやる”というスタイルになったことは、自然だったのかもしれません。
――ジャズの世界に入ったのはそのあとですか?
高校生になって軽音楽部でベースを弾くようになったんです。それからしばらくして、母親がジャズ・バーに連れて行ってくれたことがきっかけですね。セッションに参加できるっていう前情報があったんで、ベースも用意して行って弾いてみたら、マスターが気に入ってくれて、そこからよく出入りするようになりました。
――ジャズとハードコアは、ageさんのなかで別軸だったのか地続きだったのか、どちらですか?
ざっくり言えば、ジャズは繊細でハードコアは大味。サウンド感や技術的なことに目を向ければ、両者には大きな違いがありますけど、それは後からついてくることで、文章を書きたいと思ったら文法を学ぶ必要性が出てくるでしょうし、なんでもそうじゃないですか。それよりも、僕にとってはマインド的な起点の部分が重要だったんです。ジャズにはゲットーから生まれた「やってやるぞ」みたいな反骨的側面もあります。ハードコアもリアルな怒りを音にしたものが多い。精神から溢れ出てくる何かを表現するという意味では、ギャングスタ・ラップなどのヒップホップ・カルチャーも含めて、僕のなかでは共通するものがあるんです。
――ジャズバーでの演奏経験からは何を得ましたか?
ジャズのセッションは、演奏そのものが言語的なコミュニケーション・ツールというか、プレイヤー同士の対話であり、それを楽しんでもらうオーディエンスとの対話でもあり、そのなかで自分はどう弾きたいのかという、自分自身への問いかけでもあるんです。人は人と関わることで生きています。そこで我を通すことも、相手の立場を考えることも、どちらも大切じゃないですか。その間に歪が生まれたときに、相手のことをどれだけ考えるか、自分の機嫌をどう取ってあげるか。そういった人間的なことを学べて本当によかったです。
――そこからエレクトロに接近していった経緯を教えてもらえますか?
大学に入ってからpost ageっていうバンドを組むんですけど……。
――バンド名(笑)。
ポストハードコアとかポストロック的なことをやっているという意味で(笑)。で、そのバンド。メンバーが、Aphex Twinのような深みを攻めたエレクトロニック・ミュージックが好きで、色々と聴かせてくれたんです。僕はさっきも話したようにDaft Punkが好きで、そこに彼が教えてくれた曲も加わって自分が好むハウスやテクノの世界が見えてきました。そこで、ポストロックのなかでもアンビエント的な要素を多分に含んでいるものと、4つ打ちのディープ・ハウスやテクノが自分のなかで重なってきて、それらを上手く融合した音楽がやりたいと思うようになったんです。
――オンタイムのアーティストだとBonoboが最も近いように思うのですが、どうですか?
Bonoboも好きですし、あとはTychoからも影響は受けています。それが2016年とかその辺り。当時のpost ageは流動的なメンバー編成で、なんだかんだで10人以上の入れ替わりを経て、ドラムのhiroki、ギターのtakahiro、マニュピレーターのkai、そして僕がベースではなくボーカルという今のメンバーに落ち着いて、gatoとして本格的に動き出したのが2018年前後です。
――そこから2019年4月にはVJのsadakataさんがメンバーに加わりましたが、それ以前から映像やファッション、ステージ上の動き、hirokiさんの手がけるアートワークなど、ビジュアル面にも並々ならぬこだわりを感じる活動が印象的でした。
ライブをやっていると、スポットにハマるというか、アドレナリンが出まくっている状態というか、演奏しているのに視界がぼやけきて音が聴こえなくなる瞬間があるんです。あの没入感を視覚化したいという思いが根底にあります。それで、sadakataにはライブのサポート・メンバーをお願いしていたんですけど、本人もずっと正式メンバーになりたいと言ってくれてましたし、回を重ねるごとに彼女の重要性が増してきていることは明らかだったので、入ってもらいました。

――そして自主企画や近しい仲間のアーティストのパーティは、数百人のキャパを埋められるようになりました。私はそこで繰り広げられる光景に、新しいシーンの芽生えを感じているのですが、ageさんの感触としてはいかがですか?
多くの人たちが集まってくれることはほんとうにありがたいんですけど、個人的な満足度としてはまだまだです。
――それは人数、規模感的なことですか?
そうではなくて、コミュニティとしての成立度ですね。僕らはバンドではあるんですけど、もっと広くカルチャー・アイコンのひとつになりたくて。つまり、ライブが主役でそこにファッションやアートなどが付随してくるようなイベントがやりたいわけじゃないんです。音楽におけるフィーチャリングくらいの感覚で、様々な表現がフラットに存在する空間を自分たち発信で作りたい。まあ、これまで打ってきた企画が、リリース・パーティと銘打ったものばかりだったんで、そもそものやり方自体をもっと考えないといけませんね。


――そんなカルチャー・アイコンになるべく新たなモードを端的に示したのが、7月にリリースしたシングル「G0」だったように思います。音楽的にこれまでになかったサウンドを展開していますし、リリース前の映像告知や、MVの世界観からも、おっしゃったような意志が伝わってきます。
“G0=Gravity Zero”、無重力ということなんですけど、そこには自分たちが自分たちのアイデンティティに縛られているような感覚から抜け出したいという意味があります。僕らはジャズやハードコア、パンク的な精神がルーツにあって、それらをエレクトロと融合させるスタイルでずっとやってきたんですけど、そういったバックボーンを背負いすぎて視野が狭くなった重力がかかっている状態から、どうにかして解放されたい時期だったんですよね。
――それでハードコアな攻撃的要素を、今までにない視点から表現した曲が生まれたんですね。
自分で“アイデンティティ”と言うくらいですから、そこは変わってないんですけど、もっと自由でいいかなって。だから、余計なことは考えずとにかく気の赴くままに曲を作ることに集中しました。その結果すごく自然体で、ジャージー・クラブ、ジューク/フットワークっぽい、今までにやったことのないスタイルに気が付けば着手していたという感じです。
――そんなサウンドと、足取りが軽いながらも味わい深い風情のあるメロディとのマッチングが印象的でした。
メロディについては、もっと根本的な自分のアイデンティティ、日本人でありアジア人であることに目を向けて和を感じさせるものにしようと思った結果ですね。元々そういう意識はあったんですけど、海外の音楽から受けた影響が圧倒的に強いこともあって、念頭にはいつもアメリカや北欧の世界観に近づけたいという思いがありました、そして、いつしかそこばかりに注力するようになっていたんです。でもそれだと真似事でしかないし、「自分を表現したいのに、他人に近づけようとしてどうする」ってことに気が付きました。結果、J-POPまではいかないにせよ、そういうメロディになって。「そこいくの?」って、褒められているのかよく思われてないのかはわかりませんけど、反応してくれる人が多かったんで、新しい自分たちを示すことはできたのかなって、思います。
――MVもすごくおもしろかったです。
まず、曲の長さが約2分しかないのは、自由に作ったとは言いつつ、ストリーミング時代のコマーシャル的な意味合いもありました。それに合わせて、監督のNasty Men$ahと話し合って、インスタとかで流れてくるブランドの広告映像的なものをイメージして作ったんです。あえて商業的に、服をリースしてもらったりヘアメイクさんにもついてもらったりして、東京駅周辺や青山通りでロケしました。景観も綺麗でファッショナブルなんですけど、そこを歩いている多くの人たちは、音楽やアートに大して興味はない。そういう現実を描き出したらおもしろいかなって。
――そんな自由度の高い曲から、今回のシングル「dada」へと繋がるわけですが、すでにライブで披露していて毎度ものすごい画がフロアに広がる、あの曲ですよね?
ですね。いちばん盛り上がるやつです(笑)。
――タイトルの由来となったのは、第一次世界大戦中に発したダダイズムだと伺いました。理性、作為や意味、それまでに培われてきた芸術の形式を否定する芸術運動ということで、「G0」の“自由”とも繋がってきます。
さっき話した“アメリカや北欧の音楽に近づける”ということも、“自分たちのアイデンティティに自分たちが縛られていた”ということそうなんですけど、頭でっかちになっちゃって曲が書けなくなった時期があって。だから、エレクトロがどうとかジャンル的なことも、曲を作る意味や理論も考えることを止めて、直感で湧き上がってくる攻撃性だけでトラックを作ったんです。そこに同じような感覚で歌詞を加えたことでさらに強くなった段階で、タイトルとして浮かんだのが、確実に相手を仕留められる曲になったという意味で“ダダ”という銃の発砲音と、ダダイズムの精神だったので、2つを掛け合わせたタイトルにしました。


――ダダイズムには以前から興味があったのですか?
はい。おっしゃったように、ダダイズムとは“理性があるから人である”ことを重んじてきたはずなのに、理性もくそもない戦争をドンパチやってることに感じた虚無感のうえに、理性そのものや目的、意味や作為、これまでよしとされてきた芸術のマナーなどを否定する、アンチ芸術的な芸術です。でも僕は、いろんなことに対する関心や目的とともに何かを作っていくことが芸術だと思っていたので、その表現手法や作品自体に興味はありつつも、概念はいまいち咀嚼しきれてなかったんです。
――私も「少しモヤっとするけどなんかカッコいいぞ」と思っていた記憶があります。
例えば(近くにある紙コップを手に取って)「このコップを僕がここに置きました。芸術です」と言われても、「え?」って以上の感情から進捗しないというか。でも気になるんですよね。
――そんな思いが前進する瞬間があったんですね。
周囲への関心や目的意識がフラストレーションになっていた状態から解放されたことや、今の社会背景に対して僕が持つアンチテーゼとリンクして腑に落ちました。
――今の社会背景とは?
例えば、コロナ禍の真っただ中に小池都知事が再選したじゃないですか。そこには現状維持を望む人も、消去法的な感覚の人も、選挙に行かなかった人もいると思うんですけど、そのあと、都知事が感染者数に振り回されてなのか何なのか、それに見合った補償を伴わない再度の自粛を求めた時に、みんな文句を言ってたじゃないですか。
――それなら選挙の段階で行動しておくべきだったということですか?
いえ。選挙で当選した以上、つべこべ言うなということでは決してないし、言いたいことは言うべきなんですけど、あくまで全体的な印象として、都知事も都民も、どちらも後手になっているような印象が僕には否めなくて。
――確かに。
そして、それ以前から、僕らが戦うべきは新型コロナウイルスなのに、そのスタートラインにも立てていない価値観のぶつかり合いも起こっている。それらは、人の理性が信じられなくなって、ダダイズムが台頭してきた時代背景と、少し似ているように思うんです。


――そこで「dada」という曲をリリースする意味とは何でしょう? 「G0」同様、ご自身の主張を無意識的、感覚的に切り貼りしていく自由なミクスチャー感覚の光る曲で、ダダイズムの先にあるシュルレアリスムとも重なってくるように思います。
ダダイズムもシュルレアリスムもそうなんですけど、やってる側は無作為な状態で、その本質は鑑賞する側の感情も含めて成立すると思うんです。ダダイズムの代表作とされている、マルセル·デュシャンが便器を倒してただサインをしただけのレディメイド作品『泉』も、便器という既製品の意味を壊しただけで特に意図はないものに対して、それを見た人の“解釈”という動きが生まれて広がっていった。
――はい。
僕はアート・アイコンになりたいという目的に向かって動いていた。でもコロナ禍に我々がどう行動するべきか先導する人たちが、僕の側から見れば理性も道理もなく振る舞って、クラブやライブハウスという表現の場のいくつかが、奪われてしまったような状態になった。そこに覚えた虚無感や理性という存在への疑いが源にあって湧いてきた感情を、整合性や意図を持たせずに、思うがままに吐き出したのが「dada」なんです。この曲を受けて、どんな人の解釈がどう動いていくのか。もしこの曲に矛盾や不快感を覚えた人がいたとして、それもまたこの曲の正解。そういった感じで曲が広がっていってくれたら、僕の勝ちというか、そこで一歩進んだ議論が生まれてくれたらいいなと思います。
――それでこのありそうでなさそうなトラックだと考えると、これを人は何と言うのか、興味深いです。
作っている時は、小さい頃にただブロックをくっつけて組み上げて、わけのわからないものができたけどおもしろいみたいな感覚でした。こんな曲を作ろうとか、そういう意識はまったくなかったです。あえて僕が自分で振り返って解釈すると、4つ打ちのプロデューサーが振り切って作ったトラップ、ですかね(笑)。
――コロナ禍の先はまだまだはっきりと見えてこない感がありますが、この先はどう動いていくつもりですか?
僕らが懇意にしていた箱や、そのほかの場所もたくさんなくなったことに対する怒りや悔しさはありますけど、バンドとしては、gatoという肉体がすごく強化されてきている感触があるんです。当初はライブができないなら配信だとか思っていましたけど、ただやっているだけだと、だんだん人から観られなくなってくるし、投げ銭も入ってこなくなるし、じゃあもっと注目してもらってメイクマネーできるように、さらに工夫するのかとなると、ライブはしたいですけどそこにエネルギーを使うのはちょっと違う。もう振り切ってYouTuberになるとか、それも違うしそこにはプロの人がいるしそもそも勝てるはずがない。やっぱりいいものを作ることだよなって。スタートラインに戻ったような感覚ですね。

――いろんなことが精査されて、本当にやりたいことが改めて見えてくるということなら、私もすごくわかります。
少し立ち止まれたことで、MVひとつにしても、今まで以上に自分たちでもちゃんと勉強して、監督さんとしっかりコミュニケーションを取って力を借りるようになりましたし、そういう流れのなかで、バンド・メンバーの考えてることもいろいろと聞けて前よりも仲良くなりました。きっと、頭でっかちな自分が良くも悪くも何も考えない状態、無になれたことが有になって、自分のなかでの正しい判断ができるようになったんじゃないかと。だから、物事に対して集中はするけどフラットでありたいですね。そういった心情を、アルバムの良さを伝えることにどう落とし込むかが、これから最も大切なことだと思っています。
――どんなアルバムになるのか、言える範囲で聞かせてもらえますか?
これまでの曲のリメイクもありますし、今まで以上に生ドラムやギターにフォーカスしたバンドらしい曲もありますし、「dada」や「G0」のような限りなく無意識に近い状態で作った曲もあります。思いっきり“俺!”、ひいては“gato!”って感じの作品になっていると思うので、よろしくお願いします。


【リリース情報】

gato 『dada』
Release: 2020.09.02 (Wed.)
Label:gato
Tracklist:
1. dada
==

gato 『BAECUL』
Release: 2020.10.14 (Wed.)
Tracklist:
1. G0
2. ame
3. dada
4. babygirl
5. miss u
6. orb-interlude-
7. 9
8. luvsick
9. C U L8er
10. middle
11. males -interlude-
12. throughout
13. natsu
14. the girl