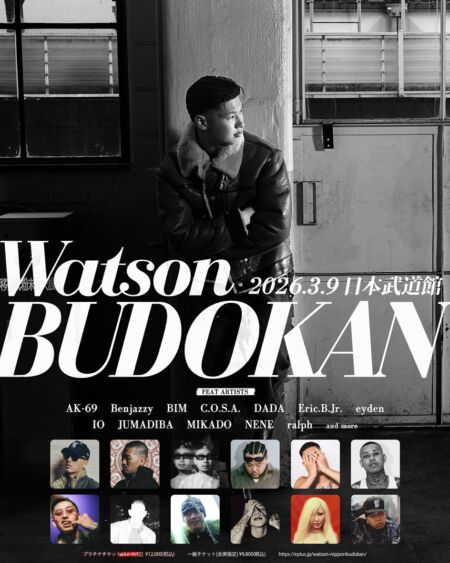今思えば、一昨年の年末にリリースされたThe fin.の1stアルバム『Days With Uncertainty』は、その後2015年に起きた国内インディ・シーンの興隆〜成熟といった流れに先鞭を付ける役割として機能していたのかもしれない。
BandcampやSoundCloudなどのネット上での活動をメインにスタートした、この神戸出身の4人組、The fin.はしかし、その1stアルバム・リリース後は慌ただしく世界中を飛び回るようになり、皮肉なことにも盛り上がりをみせる国内のシーンとは一線を引いた、独自の活動スタイルを推し進めていくことになる。
そんな彼らが遂にリリースしたおよそ1年3ヶ月ぶりとなる新作EP『Through The Deep』は、目まぐるしく変わり続けるトレンドやシーンといった周囲の雑音から圧倒的に距離を置いた、ひたすらに自己を追求したかのような進化/深化ぶりをみせた作品だ。
この新作の内容はもちろんのことながら、彼らの活動スタイルも含め、国内では他に類を見ないその独特なスタンスを紐解くべく、今回のインタビューを敢行した。
Interview by Takazumi Hosaka
Photo by Kohei Nojima

L→R:Kaoru Nakazawa、Ryosuke Odagaki、Yuto Uchino、Takayasu Taguchi
—まず、新作となるEPの制作のことからお聞きしたいのですが、収録楽曲を書き始めたのはいつ頃からなのでしょうか?
Yuto Uchino (以下:Y):楽曲は……タイトル曲の「Through The Deep」っていう曲と、「Heat」っていう曲が半年前くらいに完成して。それ以外の曲はもっと前、1年以上前くらいにはもうできてました。2014年の12月に1stアルバム(『Days With Uncertainty』)をリリースしたんですけど、その直後くらいにはできてたので。
—その1stアルバムのリリース後はプロモーションやライブなどで忙しかったかと思いますが、その合間を縫ってレコーディングやミックスなどを行っていたのでしょうか?
Y:デモは結構昔に作ったんですけど、本チャンのレコーディングは比較的最近に……あ、でもそうでもないか。
Ryosuke Odagaki (以下:R):結構前に録ったやつもあるよね。
Y:そうか、そうやね。ライブとかの合間を縫ってちょくちょくレコーディングとかしてました。
でも、今作に関しては、なんか”とりあえずできた曲を録ってみる”みたいな意味合いでスタートしてて。元々最初からEPをリリースするために曲を作ったりレコーディングしていたわけじゃないんですよ。
—とりあえず楽曲を録り溜めしておいた、みたいな。
Y:1stアルバムって結構コンセプチュアルだったというか、ガッツリ作品に向き合って作っていたんですけど、一旦それが終わったので、今度はもっと自由に作ってみようかって。
—さっきおっしゃっていた、半年くらい前にできたという「Heat」という曲は、とても短い曲で、言うなればインタールード的な役割を果たしている楽曲だと思うのですが、そういった全体の構成みたいなものはいつ頃から考えていたのでしょうか?
Y:実は今2ndアルバム用の曲も既に結構揃ってきていて、その「Heat」と「Through The Deep」はかなり2ndアルバム的な雰囲気の曲なんですよ。2ndは「Heat」みたいなインタールード的な曲がたくさん入ってて、曲と曲の間にそういう短い転換みたいなものを挟んだような、そういう作品を作りたいなって思ってて。で、その中で今回のEPがリリースになったので、この作品にもそういう流れをひとつ作りたかったというか。
—では、2ndはこれまで以上に一枚としての流れみたいなものに重きを置いた作品にしたいと。
Y:そうですね。
—なるほど。では、今作のレコーディングとミキシングは前作に引き続き全てYutoさんが手がけ、マスタリングも前作と同じくJoe Lambertが担当していますが、こういった人選が変わらなかったのも、とりあえず録ってみようというスタンスだったからなのでしょうか?
Y:えっと……レコーディングとかミキシングをするっていうのは、自分の中ではある意味作曲の延長くらい重要なことなんですよね。だからまだそれを他人に手渡すというか投げるっていうのは、自分の中ではできなくて。でも、マスタリングはまたちょっとそれとは違くて、まだ任せられる部分もあるんです。それで1stの時に頼んですごい感触が良かったJoeにまたお願いしたんですけど、それはすごい自然な流れだったよね?
R:うん。あまり議論とかもせず、自然な成り行きで決まりましたね。

—レコーディングとミキシングも作曲の一部というのは、実際に録って、ミックスしてやっと楽曲が完成するというか、そういう感じですよね?
Y:そうですね。なんかぼくらの音楽って、ミキシングでかなり変わると思ってて。自分は音のレイヤーを重ねていく前に、ミキシングしながら曲をじっくり聴いて考えるんですよ。その時に「デモ作ったときにおれはこの曲をどうしたかったのかな」とか、「この曲は何を意図して作ったんやろ」とか、自問自答というか作品と自分を照らし合わせて、進めていくんです。そこから「リヴァーヴの深さはこれくらいやな」とか、「音全体の向かってる方向はこっちかな」みたいな感じで詰めていくんですよね。だから、その段階が自分の手の中から抜け落ちてしまうと、ある種ぶん投げてるというか、出しっぱなしになってるというか。ミックスって一回自分で出したものを、もう一回見つめ直していくっていう作業なんですよ、ぼくの中では。それがなかったら……スタジオでずっと喋ってるだけになってしまう(笑)。
—今の話にはすごい納得させられました。でも、だからこそ、The fin.の楽曲ってライブで演奏することがすごい難しいというか、形になるまでが一筋縄ではいかないような気がします。
Y:基本的にぼくが作ってきた新曲をスタジオに持って行って演奏してみても、最初は全然できないですね(笑)。
あんまりみんなで音出して曲作るっていう方法はやっていないし、自分たちのなかでは常に新しいことに挑戦し続けているっていうのもあって。だから、それをバンドに持って行っても、最初は実現できないことが多いんです。これは昔からずっとそう。
スタジオで頑張ってバンドの演奏を練りあげて、曲の完成形に向かわせるというか。そういう方法でライブは成り立ってるんですよね。
ライブで「音源と比べてもあまり違和感がなかった」みたいなことを言ってもらえることが多いんですけど、そういうプロセスを踏んでるからなのかなって思いますね。
—「バンドの演奏を曲に向かわせる」とのことでしたが、そういう楽曲の完成形のようなものは、最初からYutoさんの頭のなかにあるのでしょうか?
Y:デモの段階が結構完成形に近くて。それをバンドに還元して、肉体化していくみたいな。そういう感じですね。
—なるほど。では、The fin.は1stアルバムで早くも大きな注目を浴びたと思うのですが、それ以降初の音源リリースということで、プレッシャーのようなものは感じなかったのでしょうか?
Y:実は1stのときが結構そういう状態で。最初のEPとかとは全然違うプレッシャーとかもあったんです。だから今回はあまりそういうのは感じずに、本当に自由に作れましたね。
でも、「Through The Deep」と「Heat」は、とりあえず自由に作ったっていう感じではなく、自分のやりたい方向に進み始めたというか、そういう感じの曲なんですよね。
—いわゆる「2ndアルバムのジンクス」というようなことも言われたりすると思いますが、今後制作に向かうであろう2ndアルバムではまた1stのようなプレッシャーを感じると思いますか?
Y:でも、2ndに向けて昨年かなり大量に曲を書いたんですよ。2015年って結構楽曲制作において「ここやな」っていう、ひとつ何かを掴んだというか。そういう年だったんですよ。なので、実は自信がある……というか、「ヤバいんじゃないか」みたいなのはないんですよね。何も考えてないわけじゃないですけど、そういう自然体な、まっさらなスタンスでやれてるので、今のところ。
何かこう、昨年イギリスに行ったんですけど、たぶんそこでの影響が大きくて。なんやろ、日本の中である程度評価されたThe fin.みたいなものを忘れることもできたし、ほぼゼロに近い状態からチャレンジしていく視点っていうのも思い出させてくれて。そういう経験をできて良かったなって思いますね。
—今おっしゃっていたイギリス公演の他に、The fin.は既にSXSWやアメリカ・ツアー、アジア・ツアーなども行っており、海外での活動の割合も徐々に大きくなっていると思うのですが、今後国内と国外での活動の比重についてどう考えていますか?
Y:それは昨年すごい考えていたことで。昨年はツアーは圧倒的に海外が多かったんですよ。普通おれらみたいな若いペーペーのバンドって、もっと日本中を細かく回ったりするじゃないですか。そういうことはできなかったので、東京、大阪、名古屋、行けて福岡、札幌とか、各地の主要都市を抑える形を取っていたんです。ただ、そこで海外と日本でのギャップとかをどう埋めるかっていうのが課題として出てきて。
日本だとしっかりプロモーションもしてもらっているので、ある程度観に来てくれるじゃないですか。でも、さっきも言ったけどイギリスではまだまだこれからって感じだし、かといって台湾とか行くと日本よりも人が集まったりもして……。そういう各地で起こる色々なギャップをどうしようかなって。バンド的にもそういうギャップがあると、結構大変なんですよ。やりづらいというか。なので、その点についてはすごい考えてます。
確かに他のバンドに比べたらやっぱり日本での活動の比重は下がってしまうと思います。でも、ちゃんと主要都市でのライブはやっていきたいなって思ってるので、そこは見逃してほしくないなって思いますね。

—海外での多くの活動を経験していく中で、国内との音楽シーンや音楽業界の違いなどもハッキリと見えてきたのではないでしょうか?
Y:うーん……、単純に「いいな」って思うのは、音楽業界とかシーン云々の前に、やっぱりリスナーが根本的に違うんですよね。よく言われてることだとは思うんですけど、やっぱり”音楽が身近なもの”なんですよね、向こうって。本当に当たり前の文化なんですよ。これはもう積み重ねてきたものが違いすぎる。
……そこが違ってくるので、必然的に音楽を売ろうとする人たちの考えも違ってくるし、シーンみたいなものの在り方も当然変わってくる。たぶん日本の音楽業界とかシーンを変えるっていうのは……PCの根本的なバグを直さずに、表面の問題だけ解決しようとしてるっていう感じなのかなって思って。
—もう地道に積み重ねていくしかない、と。
Y:そうですね。シンプルなことの積み重ねが現代の環境を作っていると思うので。
もちろん国ごとでも環境は全然違います。アメリカとヨーロッパも違うし、アジアも全然違う。けど、やっぱりその中でも日本は一番特殊なのかなって思いますね。
アジアの国々はやっぱりすごいグローバル化してるんですよ。でも日本は、良い意味でも悪い意味でも閉じてるというかなんというか。
—よく言われている”ガラパゴス化”っていうやつですよね。
Y:それが逆に面白いなって思う気持ちもわかるんですよ。大学生の頃とかは「日本は狭苦しいな」とか思ってたんですけど、海外を色々回って日本に帰ってくると、海外の人が日本を面白がって観光にくる理由がわかるようになったというか。でも、確かにぼくらのような音楽をやっていく上では、難しくもある。
—そうやって積み重ねてきた文化が違いすぎるがゆえに、マジョリティに刺さる音楽の質というか、テイストのようなものも、現状では欧米を中心とした文化圏とはかなり異なっていると思います。そういった点で、The fin.のような音楽を鳴らしているバンドやアーティストはやはり苦戦を強いられると思うのですが、そういった状況については、どのように受け止めていますか?
Y:ぼくらみたいな音楽をやってて、しかも英語で歌ってると、やっぱり圧倒的に届く範囲が狭くなってしまいますよね。でも、それは国内のみで考えたときで、世界的な視野で考えたら、そっちのシェアの方が圧倒的に大きいわけで。だから……国内の状況は確かに悩ましいですけど、運良くぼくらは世界に出ていけているので。日本だけで活動しなければいけないなら、たぶん今やってる音楽を変えていかなきゃいけないと思います。でも、海外でちゃんと認められさえすれば、日本は……これでも良いかなって(笑)。
—以前別媒体のインタビューで「リアルタイムの洋楽はチル・ウェイブ以降ハマった」とおっしゃっていたと思うんですが、そのチルウェイヴと括られたアーティストたちも早々に自身の音楽性を変化させていき、それ以降の欧米を中心としたインディ・シーンは目まぐるしくトレンドのようなものが変化し続けている状況だと思うのですが、今The fin.のみなさんが興味をもっている音楽はどの辺りなのでしょうか。
Y:最近ライブを観て一番良かったのは、The Internetですね。あの辺のOdd Future周りって、おれらが大学生の頃から騒がれてたし、そんなに新しくはないじゃないですか。でも、なんか未だに仲間で集ってやってるっていう感じが良くて。
あとはPhony PplっていうNYのバンドなんですけど、2013年にアルバム出してて。ソウルとかR&Bがごちゃ混ぜになったブラック・ミュージックなんですけど、結構そういうのをぼくは最近聴いてますね。バンド形式で、普通に演奏してるんですけど、オーガニックというかなんというか。
—色々なところで言われていると思うのですが、今は世界的にソウルとかファンク、ディスコのようなブラック・ミュージック的要素がトレンドとして蔓延している雰囲気もありますよね。
日本でもそういった要素を取り入れたバンドが人気を獲得してきている現状もありますが、The fin.としてはそういう要素を取り入れてみようとは思わないのでしょうか?
Y:何かをガッツリ取り入れようっていう姿勢はぼくらにはあまりなくて。自然にそういう影響が出てきてたら良いんですけどね。あんまり「こういう方向にいこう」とか、そういう具体的な方向性みたいなものは決めない質で。そういうのをそのまま取り入れても真似っ子になっちゃうような気がして。
—The fin.の活動を見ていると、やはりそういった周囲のサイクルとかトレンドとは全く別の時間軸で進んでいるような印象を抱きます。もちろん進んでる/遅れてるとか、どっちが先でどっちが後でみたいな話ではなく。そういう周囲との時差みたいなものを感じることはありますか?
Y:う〜ん、でも、真似しないようにはしてますね。あんまパクらないように(笑)。
全部自分の中で一回消化したいんです。そこから自分の表現としてアウトプットしていきたくて。
すごいインスタントな音楽を作りたいなら、その時々で流行っている要素をパクっちゃえばいいじゃないですか。それこそ今は音楽なんて1〜2日あったら数曲完成させられる。誰かがすごい曲を作ってネットにUPしたら、たぶん3日くらいで別の誰かが真似した曲をUPするっていう。インターネットを中心とした音楽って、そういった速度感で進化している側面もあると思うんですよ。それはそれですごい面白いし、カッコいいんですよ。でも、同時にすごいインスタントで、すぐに消費されてしまう。シェアされるのも、イイねが付くのも、そして飽きられるのも早い。何もかもが早いんです。すっごいカッコいいものは、すっごい早さでダサくなっていってしまう。
……そういうのも良いと思うんですけど、自分は元々あまりそういうのを追いかけるタイプじゃないなって思ってて。そういうのよりは、もうちょっとアート寄りな考え方で。単純に音を出すにしても、「自分のこういう感情の中からこういう音を出す」みたいなことに重きを置いていて。だから、そういう風に見えてしまうんですかね。コツコツやっているというか、勝手にやっているというか(笑)。
—SoundCloudとかでは頭の30秒とか15秒で掴まないと、次をクリックされてしまうので、自然とそういった作りに向かっていってしまう傾向があると思いますが、確かにThe fin.の音楽はそれとはある意味正反対ですよね。
Y:そうですね。元々の考えというか性格が違うんですかね。意識しなくても自然にこうなっちゃいますね。
—ネット上のそういった速度感とはまた質が違うと思いますが、ここ東京の音楽シーンもとても早い速度で動いていると思うのですが、そういった動きに対しては、どのようなスタンスで接していますか?
Y:最初はおれらも飲み込まれてしまうんかな〜って思うときもあったんですけど、よくよく観察していると「いや、これはなんか違うな」って思うようになって。そこからは自分たちは自分たちのスピードでやったら良いかなって思えるようになりました。
あと、自分の好きなアーティストとかもマイペースに活動している人が多くて。そういう人ってじっくり作品を作りこんでいるので、やっぱりインスタントじゃない魅力があるんですよね。だから自分たちもそういうところにいきたいっていう思いもあります。
新しいモノを追っかける面白さもわからないわけじゃないんですけどね。ただ、新しいから追っかけるっていうよりかは、自分が良いモノを追っかけていたいんです。
—ここまでの話を聞くと、このEPに収録されている「Anchorless Ship」という曲名はとてもThe fin.の活動スタイルを表しているような気がしてきました。アンカーもなく、広大な海を漂っている船のイメージというか。
Y:なんかこう……あんまり人生の中に確固たる「正解」とかはないじゃないですか。「こうしたらいい」とか「あっち行った方がいい」とか。それでもその中で、自分で考えて決めて生きていかなければならない。でもそれはとても難しいことだから、みんな誰かを参考にしたがる。
—その方が楽ですもんね。
Y:そう。でも、バンドっていう集まりは結構そういうレールからはみ出していける集団だと思うんですよ。自分らなりの何かを見つけて、それを探求していくっていうことができるのが、バンドの良いところだなって思うので、そういう感覚をぼくは大事にしたいですね。
—なるほど。ではまた新作の話しに戻りたいと思います。以前からもそうだったとは思うのですが、今作ではよりサウンドもドリーミーになったということもあり、リリックで描かれている世界からは一切現実のニオイがしない、空想上の世界の景色のようなイメージを抱いたのですが、こういったイメージというのは、Yutoさんの頭のなかに浮かんだイメージを言語化した結果なのでしょうか?
Y:あー、なるほど。イメージっていうよりかは、ぼくは結構そのまま書いてるんですよね。思ってることをそのまま書いてて、ぼくからしたらかなりリアルなんですよ。でも……リアルじゃないんかな?(笑)
R:ぶっ飛んでるんじゃん?
一同:(笑)
—具体的な景色を描いてるんだけど、そこにリアルなニオイがしないというか、なんというか。
Y:ぼくは……ホンマに正直に書いてて、昔のことを思い出して書いてたりとか、自然に書いてるんですよね。でも確かに情景描写っぽくなっている自覚はあります。
—直接的なメッセージを投げかけるというよりかは、ある種のメタファーのような。
Y:それは間違いないです。例えば、歌うときに「嬉しい」っていう気持ちがあるとするじゃないですか、それで「嬉しい」って言っちゃったら、「嬉しい」で止まっちゃうじゃないですか。でも、たぶんある瞬間の自分の感情を全部曲の中に入れて、それを他の人にぶつけたら、その人が抱く感情はまたぼくとは違ったものになるはずなんですよ。
あの、物語とかもそういう構図があると思ってて。物語を読んでるときとか、映画を観ているときとかって、色々な生き方をしていひとたちがそれぞれその世界に引き込まれるじゃないですか。疑似体験というか。で、それが終わると「解散!」ってなって強制的にその世界から追い出されて、自分の世界に帰っていく。その時にたぶんみんな持ち帰ってるモノはバラバラなんですよ。その持ち帰ったモノっていうのは、たぶんその人たちの人生を通過したモノなんだと思うんです。
で、そういう体験こそ物凄いリアルだなってぼくは思ってて。現実世界ってそうじゃないですか。確実にわかっていることっていうのは何もなくて、ここにバンド・メンバーみんな一緒にいるけど、みんな考えてることは違うし、けど共有してるモノも確かにあるし、みたいな。
だから、そこをどんだけクリアに出せるか、どんだけクリアに人に届けられるかっていうのが自分のなかでの課題なんです。それが情景描写っぽくなってしまう理由ですかね……。

—そういうリリックのイメージってメンバーとは共有していますか?
R:ぼくが思うのは、1stのときもそうやったんですけど、Yutoが歌詞を送ってきてくれて、それを見ると、「たぶんYutoはこうやって世界を見てるんやな」っていうのはいつも思います。
Y:たぶん絵とかもそうなんじゃないかと思うんですよね。表現をするっていうことは、自分から見えた世界を切り取っているというか。
で、そういう行為にこそ価値はあると思っているんです。ただ同じ風景を描くにしても、みんなが見ている風景は違うだろうし。でも実はサウンドもそうなんですよ。ミックスも含めて全部そこに行き着くというか。
—なるほど。では、時間もなくなってきしまったので、The fin.の今年の展望を教えてもらえますか。
Y:たぶん……海外での活動が昨年以上に多くなりそうな気がしてます。アジアでの活動をもっと広げるっていうのと、あとイギリスはこれからもっと本格化していくと思いますし、アメリカにも行きたいなって思っていて。日本にいない時間が増えてしまうかもしれませんが、それでもライブだけはコンスタントにできればって思ってます。


The fin.『Through The Deep』
Release Date:2016.3.16
Price:¥1,500+tax
Tracks:
1.White Breath
2.Divers
3.Through The Deep
4.Heat
5.Anchorless Ship
6.Night Time (Petite Noir Remix)
“Through The Deep Tour”
2016年4月01日(金) 心斎橋 Music Club JANUS
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ワンマンライブ
2016年4月02日(土) 名古屋 CLUB UPSET
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ワンマンライブ
2016年4月09日(土) 渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ワンマンライブ
2016年6月10日(金) 台北 THE WALL
OPEN 19:00 / START 20:00
ADV NT.1100 / DOOR NT.1300
ワンマンライブ
2016年6月16日(木) 仙台 CLUB SHAFT
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ゲストアクト有り
2016年6月21日(火) 広島 4.14
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ゲストアクト有り
2016年6月22日(水) 福岡 The Voodoo Lounge
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500(Drink代別)
ゲストアクト有り