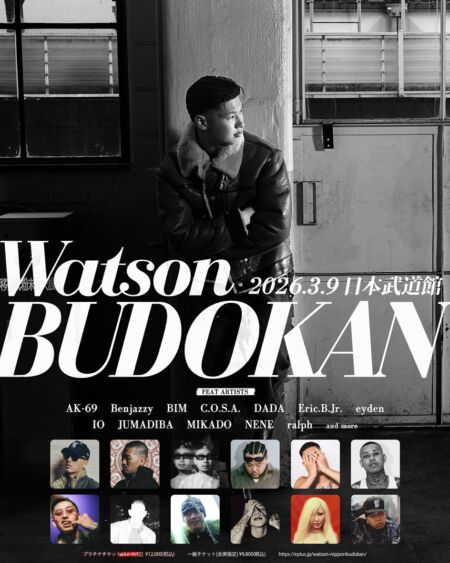京都を拠点に活動する4人組ロック・バンド、the engyが8月28日(水)に配信シングル『Still there?』をリリースした。
歯切れの良いギター・サウンドと4つ打ちのビートが夏らしさを感じさせるダンス・チューンとなっている本作のリリースを機に、the engyの中心人物であるボーカル山路にインタビューを敢行。彼の半生を振り返ると共に、多様なバックグラウンドと職人的な哲学を感じさせるthe engyのサウンドの背景に迫った。
Interview & Text by Kohei Nojima
Photo by Takazumi Hosaka

――山路さんは、普段お仕事として塾の講師をされているんですよね?
山路:そうです。大学入った時からその塾でバイトをしてまして。予備校時代に生徒として通ってた塾なんですけど、大学行くか専門学校行くか迷ってた時に「大学行ってウチに働きに来い」て言われて、大学行ったんですよね。なので、塾で働くために大学に行ったみたいなところはあります。
――ちなみに教科は何を?
山路:英語と社会と国語です。 小中学生が対象なんで基礎的なところを。
――じゃあ平日は塾の講師をしながら週末は音楽をって感じですね。両立は大変ですか?
山路:はい、でもどっちも好きなことなので、全然大丈夫です。ただ、生徒とか親御さんが「山路先生〜!」ってライブ観に来てくれたり、それはちょっと恥ずかしいですね(笑)。でももすごく励みになります。
――それでは、まずは山路さんのミュージシャンとしての原体験教えてくれますか。
山路:そもそも音楽に興味を持ったきっかけは、幼稚園の時にある日突然「ピアノはどうして音が鳴るの?」って言い出したみたいで。「だったら習ってみたら?」って、ピアノを習わせてもらったんです。
――ハンマーが弦を叩いて音が鳴るという、構造的な部分が気になった。
山路:そうです。正直、「こういう風に鳴ってるんや」ってことがわかってからはすぐに興味を失ったんですけど、せっかくなので習い事自体は続けてたんですね。そしたら音を出すこと自体が楽しくなっていって。で、次は「ギターの音がどう鳴ってるか知りたい」って思い、ギターを始めて。そっから本格的に音楽をやるようになったって感じですね。
――当時は、どういう音楽を聴いていましたか?
山路:最初は普通にJ-POPを聴いていて。コブクロみたいなのをやりたかったんです。 でも、自分の声のキーが一般的な男性とは異なってて。普通、男性が女性の曲を歌う時ってキーを下げると思うんですけど、僕は逆にキーを7個ぐらいを上げないと上手く歌えなくて。そのことに気づくまで、自分は歌がめちゃくちゃ下手なんやと思ってたんですね。だからギタリストになりたいと思って。そこからAvenged SevenfoldとかAerosmithとか、ラウド〜ハード系のロックを経てレッチリ(Red Hot Chili Peppers)とリンキン(Linkin Park)に出会い、「これはヤバい!」って。なので、僕の中の核としてはレッチリとリンキンになるかなと思います。僕、あんまり音楽には詳しくなくて。最近はよく「黒いですよね」「ブラックっぽいですよね」って言われるんですが、最初“ブラック”が何を意味するかわからなかったくらいなんです。「John Mayer好きなん?」とか言われても、「それは人の名前ですか? それともバンド名ですか?」みたいな(笑)。でも、よくよく考えてみると親父はジャズやブルースが好きで。憂歌団とか日本のジャズ、ブルース・シンガーものがよく家で流れていたので、知らずにそういったところからの影響が出てたのかな? っていう気はします。
――そうなんですね。the engyのサウンドのルーツとしては、色々なジャンルを横断しているのだと思っていました。
山路:音楽をやろうって決めた時、「アメリカで流行ってるものが何年後か遅れて日本にくる」っていう風に思っていたんです。なので、当時は向こうで流行ってる音楽を聴いてたんです。それこそグラミーを獲るようなアーティストですね。最初の頃は自分の中で勝手にそういう世界的なアーティストと勝負していて。曲作る度に「これじゃまだBeyoncéに負けてる」「Jay-Zには勝ってない」みたいな(笑)。その後、YouTubeとApple Musicに出会ってからは、当時Ed SheeranとかTwenty One Pilotsみたいな、新たに世界で流行り出した音楽を聴いたり、もっともっと音楽を掘り下げるようになりました。Chet FakerとかSG Lewisみたいなエレクトロニックなアーティストにも惹かれて、「こういうサウンド、取り入れられへんかなぁ」って思うようになったり。
――ちなみに、普段はどういったところを意識しながら音楽を聴いているのでしょうか?
山路:曲を聴く時は、「何でこうなってるんだろう?」っていうのを気にしながら聴くようにしていますね。「この人はキックを立たせたいから、こんなにペラいギターを使ってるんだろうな」とか、自分なりに分析しながら聴くようにしています。
――そこからthe engy結成までの経緯というのは?
山路:さっきもお話したように、僕はギタリスト志望だったんです。でも、入った大学のサークルに人が全然いなくて、バンドを組めなかった。しかも、僕の作る曲が歌いにくいのか、誰も歌えなくて。「このままだと一生バンド組めへんな」って思ったんです。なので、しょうがないからひとりで弾き語りをしていました。そしたら「声、良いね」って言われるようになって。だったら自分がボーカルでバンド組んでみようかなと。
――メンバーはどのようにして?
山路:僕、軽音サークルの会長をやってたんです。と言っても僕の代は自分一人しかいなかったんで、自動的に会長になっただけなんですけど(笑)。その時に、勧誘を頑張ってたら後輩がめっちゃ入ってきてくれて。その中のひとりがギタリストとして入ってくれた濱田です。ベースもできるって言うからベースやらせて、当時のドラムとスリー・ピースでスタートしました。学祭に向けて、その3人で練習してたら、スタジオのPAさんが僕の声をすごい褒めてくれて。「外でやったらいいのに」って言ってもらえて。初めてちゃんとした音楽のプロの方に評価されて、「自分の声、良いんや」って思えたんです。ライブ・ハウスでも活動するようになったのは、それからでしたね。
――当時の音楽性はどのような感じだったのでしょう?
山路:今よりギターも歪んでて、もっと激しかったですね。そもそも「リンキンのボーカルがレッチリで歌ったらおもしろいんじゃないか」っていうイメージでバンドをやっていたので。
――では、どのタイミングで今のような方向性にシフトしたのでしょうか?
山路:後輩にエンジニアを目指している奴がいて、そいつと一緒に「She makes me wonder」っていう曲を作ってからですね。あの曲は当時EDM界隈で流行ってた展開とか雰囲気を取り入れてみようってことで作った曲なんです。シンセとか打ち込みの知識がなかったので、全部の音を生音でやったらこうなったっていう感じですね。そこからiPadでトラック・メイキングをするようになって、それがめっちゃ楽しくて。そこからですね。
――音作りの時はどのようなことを意識していますか?
山路:僕は音の意味を考えちゃうタイプで、「この音をなんで出すんだろう」っていうのがすごく気になるタイプなんです。例えば「ポン」という音と「ドーン」という2つの音があったら、 その2つの音の組み合わせが気持ちいいからそうしてるはずだと思う。であれば、そこにさらに別の音を乗せる意味が僕にはわからないんですね。そもそも、以前から音数自体は結構少なかった方なんです。レッチリとかリンキンも、やりたいテーマや曲で表現したいことが明確にあって、全ての音がそのために組み合わさっているって感じるんです。僕はレッチリのJohn Fruscianteが特に好きなんですけど、Johnがあのビートであのベースに対して弦を一本を鳴らすだけでめちゃくちゃカッコいいじゃないですか。Linkin Parkも音数が多いけど、全部の音がひとつの目標のために積み上げられているなって思うんです。そういう部分が好きなんですよね。でも、曲を作ってて、テンションが上がってくるとやっぱり音を足しちゃうんですよね。だから、足した後に「この音はいる? いらない?」ってジャッジを毎回のようにしています。
――the engyの楽曲は、その骨太なグルーヴも特徴として挙げられると思います。グルーヴの作り方に関してはどう考えていますか?
山路:ライブハウスでやり出した頃は僕も濱田も初心者みたいな感じだったんで、最初はグルーヴとかも全然出せなくて。「音源は良いんだからライブも頑張れよ」ってよく言われてました。でも、ある時から「ライブ良いよね。グルーヴあるよね」っていう風に逆のことを言ってもらえるようになって。「え、そうなんや」みたいな(笑)。ただ、ひとつ思うのは、自分はリズム感があまりないんです。普通の8ビートとかじゃなくて、ブレイクビーツみたいに細かくリズムを刻まないと、上手くリズムに乗れないんです。そのリズムがドラマーとかでは絶対に出てこないフレーズらしくて、そういうのが特徴として出ているのかなって思います。あとは、やっぱり自分たちの曲で踊って欲しいので、曲を作ったら実際に踊れるかどうかっていうのをめっちゃチェックするんです。そこに一番時間を割いているかもしれません。
――「この曲は踊れないな」って思った時は、どうやって改良を?
山路:僕は全ての音をビートとして捉えているんです。ドラムはもちろん、ギターやベースの音もビートとして捉えていて。このドラムのリズムに対して、どういうギターを被せればノリが生まれるかとか、そういうことを常に考えていて。他の楽器でビートが構築できてるなって思った時は、ハイハットをビートではなく上モノとして扱ったり。逆にギターやハイハットだけでビートが完成してたら、キックは「ドーン」とゆったりとしたテンポのノリを出すために鳴らしたり。どれをビートにしてどれを上モノにするかっていうのを常に考えながら、ノリを作っています。だから、この曲では踊れないなって思ったら、ハイハットの役割をギターに替えてみたり、ギターでやるとノリが出すぎちゃうから、スネアの音を大きくしてみよう、とか。そういう調整をしていきます。
――the engyの音を聴いていると、楽器一つひとつが歌っているような印象を受けます。その1音1音を確認する作業が要因なのかなと。
山路:レッチリもそうですけど、全部の音がリフなんですよ。コードを弾くだけでも、コピーしたくなるようなリフとして完成している。そういうところも大好きで。ベースにフレーズを考えてもらった時も、「そのリフはノリは出るけどフレーズとして、リフとして本当にカッコいいのか?」みたいなことを言っちゃうことは多いですね。やっぱり、リフとして音の粒が立ってるかっていうのは結構意識しています。そういうこともグルーヴに繋がってるのかもしれないですね。
――the engyが活動し始めた2015年〜2016年頃って、東京では「STAY TUNE」をリリースしたばかりのSuchmosがメキメキと頭角を現してきて、他にもNulbarichやLCUKY TAPESなど、横ノリのグルーヴが得意なアーティスト、バンドが注目を集め始めた頃と重なります。the engyは彼らの次の世代、みたいな見られ方もされていると思うのですが、当時は東京のシーンの盛り上がりをどのように感じていましたか?
山路:僕ら、音楽は大好きなんですけど、詳しくないんですよ。なので、東京のシーンについてもあまりよくわかってなかったですね。ただ、「Stay where you are」を作った時、ドラマーの境井が「次はこういうグルーヴィーなサウンドがくる」みたいなことを言ってたので、なんとなく意識はしていました。そもそも、バンドを組んだきっかけが「すごいカッコいい曲を作りたい」ていう単純なものだったので、あまりポリシーもなかったんです。なので、そういう流行りそうな要素を教えてもらったら、とりあえず取り入れてみたらおもしろいんじゃないかなっていう気持ちでやっていました。
――そもそもトレンドやシーンって、同じ時代を生きるアーティストが同時多発的に同じようなことを感じ、それをアウトプットしたただの結果であることも多いですもんね。
山路:そうだと思います。さっき言ったようなアーティストたちが窓口を広げてくれて、僕らのようなサウンドも世の中に広がりやすくなったと思うので、よかったなと思います。ありがたいですよね。

――今回リリースする新曲「Still there?」についてお伺いします。爽やかなイントロから間には4つ打ちも入ってきたり、とても夏っぽい楽曲に仕上がっていますよね。
山路:そうですね。そもそも曲作りが大好きなので、お題をもらうと飛びついちゃうんですよね。8月にリリースしたいんで「夏っぽい曲はどう?」って言われて、即採用しました(笑)。あと、コードでも遊んでみたくて。この曲はコードが2つあって、ギターとベースは全然違うコードを弾いてるんです。「夏っぽさ」「コードで遊ぶ」っていうお題から作った曲ですね。
――でも、歌詞は全然夏っぽい感じではないですよね。
山路:そうですね。「Still there?」は“TALK”をテーマとしています。実は最近、同様に“会話”に関する歌詞を何曲か作っていて。この前発表した「Touch me」もそうなんです。この曲は自分が喋り過ぎちゃうのを自覚しているから、少し抑えようと思っている。けど、やっぱり喋ってしまって、「おれの話、聞いてる?」みたいな内容の曲で(笑) 。
――普段、歌詞はどんなところからインスピレーションを得るんですか。
山路:完全に音からですね。そもそも英語で歌い出したのも、その音のハマり方がすごいカッコいいなと思ったからなので。楽器始めた時に、色々な海外の楽曲の歌詞の子音とかを分解して研究してみたりはしていました。独学で色々と勉強していたら、ある程度英語のフレーズが降りてくるようになって。なので、内容とか意味は結構後付けのことが多いですね。
――「Still there?」キャッチーでありながら、リズムや構成はかなり複雑な楽曲になっています。
山路:この曲は、実はバンド・サウンドとは別にトラックが走っていて。そのトラックに対してフィルターをかけて、前に持ってきたり裏に隠したりすることで、ビートとして出したり消したりしているんです。あと、今使わせてもらってるスタジオは音がすごくよくて。そのスタジオのエンジニアの方に色々教えてもらいながら、ようやく帯域の話も理解できるようになって。実際に帯域で遊ぶっていうのを曲で挑戦してみたいなと思って、今回のアイディアに辿り着きました。上の音域削ったり、逆に下の帯域を削ったり、各楽器の音が被らないようにもしつつ。あと、曲の最後で鳴っている小さいキックは、クラブの外でかすかに聴こえるキックの音がカッコいいなと思って、それを再現したつもりです。
――今は次作リリースに向けてたくさん曲を作って、レコーディングをしている状況ですか?
山路:そうですね。デモが全部上がってレコーディングに落としているっていう段階ですね。スタジオで色々なことを勉強したので、これまでとは比べ物にならないほど自分のレベルが上がってると思ってます。今まではドラムの音のことについてはわからないからエンジニアさんに任せたり、「この音、カッコいいですかね?」って聞いたりしてたんですけど、「この音はこうなってるからカッコいいんだ」って自分で判断できるようになって。自分としては本当にやりたかった音、理想的な音を作れるようになったかなって思っています。その一方で、自分の曲を広い範囲届けようと思ったらキャッチーじゃないといけないし、大衆性と芸術性は絶対に交わるっていうのが曲作りの根底にあるものなので、そういう部分のバランスがちゃんと取れているのかっていうのはこれまで以上に気にしながら作ってます。
――トラックメイクも好きで、やろうと思えばひとりでも活動できるであろう山路さんが、バンドとしての活動を続ける理由、魅力は何だと思いますか?
山路:まず、僕はひとりだとやらないと思うんですよね。もちろん曲作りは好きだから、ひとりでもずっと作り続けると思うんですけど、プロのミュージシャンとしての音楽活動はできないと思うんですよ。バンド・メンバーがいるからこそ曲を仕上げないといけないなって思うし、メンバーに影響されながら曲を作ってる。メンバーが感動してくれる曲を作りたいっていうのも自分の中のモチベーションのひとつになっていると思います。なので、音楽活動を続ける上で、僕の場合はメンバーは絶対必要。良いときも悪いときも含めて、メンバーは家族みたいなもんですね。

【リリース情報】

the engy 『Still there?』
Release Date:2019.08.28 (Wed.)
Label:Lustrum Music Entertainment
Tracklist:
1. Still there?