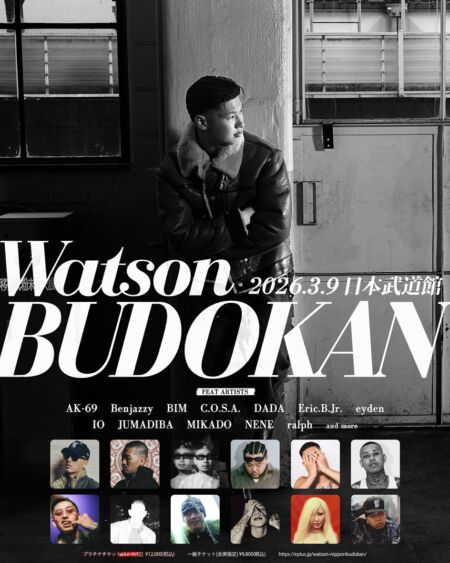先月新木場スタジオコーストで開催された”Hostess Club Weekend”にて初来日を果たしたロンドンの新鋭サイケ・ロック・バンド、Pumarosa(ピューマローザ)。
ミニマルかつタイトなグルーヴを刻むリズム隊の上で、ギターやシンセ、サックスといった上音、そして紅一点ボーカル・Isabelの妖艶な歌声が自由に漂うその音楽性は、TemplesやTame Impalaといった新世代サイケ・バンドたちとも共鳴しながらも、時に呪術的でもあり、シャーマン的でもあり、独特な存在感を放っている。
傍目から見ていると失速気味に思えるUKインディ・ロック・シーンから、彼らはどのようにして頭角を現したのか? そして5月にリリースを控える待望の1stアルバムはどのようにして作られたのか? ――今回、初の来日公演を行ったPumarosaの中心人物であるドラマーのNicholas Owenと、シンセやサックスなどを自在に操るTomoya Suzukiのふたりに、短い時間ながらも様々な質問をぶつけてみた。
Text:Takazumi Hosaka
Photo:Yuma Yamada

L→R:Nicholas Owen(Dr.)、Neville James(Gt.)、Isabel(Vo./Gt.)、Tomoya Suzuki(Syn/Sax)
―日本に着いたのは昨日ですか?
Nicholas:そうだね。昨日着いてから、少し東京を見て回ったりちょっと食事したりしたよ。日本の食事はすごい美味しいよね。
Tomoya:僕は他のメンバーとは違って、以前にも来たことがあって。母親が和歌山の出身なので、新宮っていう海辺の街には行ったことがあるんだ。
Nicholas:Tomoya以外のメンバーは、僕も含めてみんな今回が初めての日本だと思うよ。
―日本に来る前は、日本という国に対してどういうイメージを抱いていましたか?
Nicholas:今回は渋谷に滞在してるんだけど、日本に関してはあの街のイメージに近いものをずっと抱いてきたよ。NYにも似た大都会だから、映画なんかで時々日本の様子を目にする機会とかもあってさ。だから、実際に自分たちが渋谷という街に着いた時、「あれ、こんな場面、何かで見たぞ」っていうシュールな感覚があったよ。あと、不思議なんだけど僕は日本に対して「丘」のようなイメージも抱いているんだよね。連綿と続く丘のイメージが。それが一体なぜなのかはわからないんだけどね(笑)。
―それは不思議な意見ですね(笑)。では、次はバンドについてお訊きしたいと思います。Pumarosaはまだ結成して2年ほどですが、すでに確固たる音楽性、世界観が確立されているように思えます。こういったことに繋がるバンドの方向性、コンセプトのようなものが固まってきたのはいつ頃からなのでしょうか?
Tomoya:徐々に変わってったいう感じだよね。
Nicholas:そもそも僕らは「バンドやろうぜ」っていう感じで集まったわけではないから、最初はジャンルも定まっていなかった。だから、それぞれのやりたいことをインプロ的に自由で演奏していく中で、徐々に形が見えてきたという感じかな。この5人のメンバーがそれぞれありのままで持ち寄ったモノが、この2年間で固まってきたっていう感じかな。

―セッションを繰り返していく中で方向性が見えてきたと。
Nicholas:いわゆる実験っていうやつだろうね。現在に至るまでずいぶん色々なタイプの曲を書いてきたけど、ある時期「こういう方向性がいいね」ってなって、しばらくそういう路線でやってると、ある時また好みが変わって「次はこういうのやってみよう」ってなったり。
だから結局のところ変化っていうのが自分たちにとってのアイデンティティなんだよね。そうやって常に変わり続けることは、結果としてはすごくいいことなんだろうなって思ってるよ。
Tomoya:変化するっていうのはとても自然なことだからね。自分が聴いている音楽の好みだって、自分の生き方とか周りの環境が変わるのに応じて色々と変わっていくのと同じように、自分のセンスが変わったら変わったで、それを素直に出す。そういうことを、5人のメンバーがそれぞれみんなで試していけるっていうのが僕らの良いところなんじゃないかな。
―では、メンバーそれぞれの音楽的なルーツはかなり異なっているのでしょうか?
Nicholas:みんなPumarosaの前にもそれぞれ色々なバンドをやってたよね。だから、音楽的なルーツでは共通する部分もいっぱいあるんだけど、幅の広さがみんなすごいんだ。
Tomoya:僕なんかは教会のクワイヤで歌ってたこともあるんだ。5年ぐらい毎日のようにね。あと、基本はジャズとクラシックがルーツにあるんだけど、メタル・バンドで歌ってたこともあるし、今はレゲエ、ダブ系の音楽もやってる。本当に何でもやるんだよね。家ではひとりで変なエレクトロ・ミュージックを作るのが好きだし。
―メンバー間で共通している部分を挙げるとしたら?
Nicholas:例えば、いつかのグラストンベリー・フェスティバルでMassive Attackを観た時とかは、メンバー全員揃って衝撃を受けてね。全員一致ですぐに「こういう曲書こう」っていう風になり、実際に彼らに影響を受けたような曲も作った。BO NINGENの時もそうだね。みんなで観に行ったんだけど、これまた全員触発されて、次のリハの時には「ああいう感じの曲を作ろう」ってなったり。そういう時に「あ、みんなこういうの好きなんだ」っていうのがわかるんだよね。
―なるほど。では、バンドとしての楽曲を作るプロセスがどのようなものか教えてください。
Nicholas:アプローチはその都度様々なんだけど、たとえばIsabelがピアノ一台で書いちゃうときもあるんだけど、そこからみんなでアレンジして広げていく時に、色々な手法を試してみるので、最初のデモとは全く異なった仕上がりになっていくこともあるんだよね。
基本的にはずっとレコーダーを回しっぱなしにして、インプロで延々とプレイしながら固めていくんだけど、それをレコーディングするっていうのが難しくてね。セッションの中でいい演奏ができたとしても、それはその場のノリやエネルギーとか、色々な要素が複雑に絡み合った結果なんだよね。だから、それを聴き直して、同じように再現しようとしても、中々上手くいかないんだ。だから、いつもすごい苦労はするんだけど、そうやって偶然録れたものを、後から聴き直して、さらにアレンジを詰めていくっていう工程はよくやってるね。
Tomoya:その場のノリ、その場の雰囲気っていうのが僕らの場合はすごく大事で。だからこそ、最初に録れた時のフィーリングを曲のコアとして、そこから膨らませていくっていう方法を大事にしているんだ。土台は固めたら、あとはある程度自由に作っていく。それぞれ影響を受けたものや考え方も違うけど、そういった5人の異なる個性を楽曲に織り込んでいけるのが僕らの強さでもあるからね。

―5月には待望の1stアルバム『The Witch』をリリースしますよね。インプロで曲を固めていく、肉付けしていくというだけあって、Pumarosaの楽曲はとても自由度が高いですよね。それをスタジオ作品としてパッケージングする際にはどういったことを意識しているのでしょうか。例えばスタジオ作品はライブとは全く別物だという意識なのか、それともライブ感あるものをそのままパッケージしようとしているのか、など。
Nicholas:まさにそこなんだよね。僕らの持ってる即時性、その場でのエネルギーとかパワフルさってものをレコードに記録したい、レコードで表現したいっていう思いは確かにある。一つ一つの音を重ねていくんじゃなく、いっぺんに演奏して土台を作るっていうのは、そういったことを目的としているからっていうのも事実で。でも、レコードにするにあたってはやっぱりオーバーダブとかも必要になってくるし、新しい音色を加えたり、サウンドの厚みを出したりしたくなるから、そういう作業も行っている。それでも、やっぱり根底にはライブっぽい音をパッケージングしたいっていう思いはメンバー全員にあったと思う。ライブでお客さんが聴いているような音、それをレコードにして出したかった。でも、やっぱりライブで聴くのとヘッドフォンで聴くのは全然違うよね。もっと言えばアルバムだってスピーカーで聴くのとヘッドフォンで聴くのでは聴こえ方が全然違うし。
そういった僕らだけではどうしたらいいのか見当もつかない部分で力になってくれたのが、プロデューサーのDan Carey(ダン・キャリー)だったんだ。優秀なプロデューサーっていうのは、そういうミュージシャンのアイディアをなんとか形に収めてくれる人のことを言うんだと思う。今回、僕らの1stアルバム『The Witch』の制作に際して、そういう優れたプロデューサーの作業を間近で見ることができて、すごく勉強になったと思うし、それ以前の僕らのレコーディング経験なんて本当に僅かなものだったから、今回のアルバム・レコーディングはそういう意味でもとても貴重な体験だったよ。
―あなたたちの日本デビューEP『Pumarosa Ep』にも収録されていた「HONEY」は、Adam Curtisの政治的ドキュメンタリー、『Bitter Lake』からインスパイアされたそうですが、そういった政治的というか社会的なメッセージを自分たちの楽曲を通して伝えようという思いはありますか?
Nicholas:もちろん。せっかくこういったアウトプットする場、手段を持っている身であるのだから、自分たちの目に移ることや日々気になることを発信していくのは、とても当たり前で、とても大事なことだと思う。
シェルターの中に自分たちだけで篭って、現実の世の中と接点を持たずに、現実の世の中を映し出さないことばかりやっていても、僕はあまり意味がないと思う。今、起きていること――狭義ではなく、世界的な視野から見てっていう意味だけど、そういった現実に対しての意見や考えを反映させるっていうことは、意識してやってることだね。「Honey」なんかは映像(MV)もそうだよね。
―なるほど。では、さきほど音楽的バックグラウンドをお訊きした際に、Pumarosa以前にもメンバーそれぞれ他のバンドでの経験があるとおっしゃっていましたが、ロンドンのインディペンデントなバンド・シーンの現状について教えてもらえますか?
Nicholas:バンドがどうこうっていうより、今ロンドンでは会場がどんどんなくなっちゃってるんだよね。始めたばかりのバンド、小さな規模でしかやれないようなバンドがやるような場所がね。まあいいところもいくつかは残ってるけど。
Tomoya:ここ数年で半分ぐらいに減っちゃってるよね。

Nicholas:そう。でも、実際に活動してる人やバンドは相変わらず大勢いるから、僕らから見ても一体どこで彼らがプレイしてるのか、不思議に思ってしまうくらいで。例えばThe Silver BulletとかPassing Cloudsっていういいベニューがあったんだけど、どっちも最近になって再開発の煽りを受けて潰れてしまった。派手な高級アパートみたいなのに建て替えられちゃってさ(笑)。
Tomoya:逆に考えると、そうやって厳しい環境になると、みんなアンダーグラウンドなところに潜り込むから、音楽的にはどんどんおもしろいものが生まれていくかもね。表面上には当たり障りのないミュージシャン、バンドばかりがいるように見えるけど、その水面下ではエキサイティングなシーンが育っているかもしれないよね。
―では、そのような厳しい状況にあるというロンドンのシーンにおいて、シンパシーを抱くようなバンドはいますか?
Nicholas:……難しい質問だな(笑)。僕は普段は結構古い音楽ばかり聴いてるからさ。敢えて挙げるとするならば、shameはいいバンドだよ。僕らの友達なんだけど。あとはBo Ningen。彼らのステージはなんど見ても圧倒される。
Tomoya:あとはBlood Sportとかね。Bo Ningenもそうだけど、僕らとは音楽性が似ているわけではないんだけど、アティチュードとかそういった面で共感するような人たちが多いかな。
【リリース情報】

Pumarosa 『The Witch』
Release Date:2017.05.19 (Fri.)
Label:Fiction / Caroline / Hostess
Cat.No.:HSU-10126
Price:¥2400 + Tax
Tracklist:
1. Dragonfly
2. Honey
3. The Witch
4. Priestess
5. Lions’ Den
6. My Gruesome Loving Friend
7. Red
8. Barefoot
9. Hollywood
10. Snake
※日本盤はボーナストラック、歌詞対訳、ライナーノーツ付(予定)