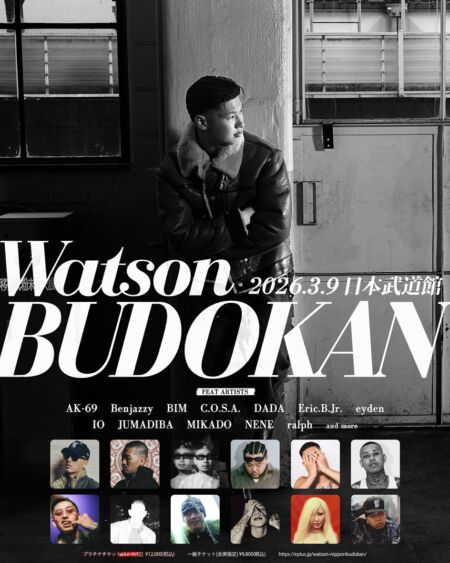昨年末にリリースしたアルバム『Pressure』に続き、早くもPAELLASが新たなミニ・アルバム『D.R.E.A.M.』を9月6日にリリースした。
大阪で結成され、2012年には現体制とは大きく異なるメンバー編成(バンド名もThe Paellasと名乗っていた)での1stアルバム『Long Night Is Gone』をリリースし、その後東京へ拠点を移したPAELLAS。彼らは様々なシーンを横断するような活動ぶりをみせながらも、自身のサウンド・スタイル、そしてバンド編成も幾度に渡って変化させながらもサバイブしてきたバンドだと言えるだろう。
そんな彼らの新作『D.R.E.A.M.』は、前作の妖艶で内省的なムードから一転、華やかな音使いにより肉体的なグルーヴも獲得。そして一番の驚きはキャリア初の日本語詩への挑戦だろう。果たしてバンド内ではどのような意識の変化が起こっていたのかを明らかにするためにインタビューを敢行。新作についてだけでなく、今の東京を中心としたシーンなどについても、長く俯瞰し続けた彼らの視点で語ってくれた。
Interview & Text by Takazumi Hosaka
Photo by Kohei Nojima

[L→R:bisshi (Ba.)、Ryosuke Takahashi (Dr.)、Satoshi Anan (Gt.)、MATTON (Vo.)、msd. (Sp.)]
――前作からAnanさんがソングライティングのメインを担うことになったとのことですが、それは今作も変わらず?
Anan:そうですね。
――前作リリース時のインタビューでは、趣味以外の制作で、ほぼひとりで作り上げていくのは初めてだったと語っていました。その初めてひとりで作曲の大部分を担ったアルバムをリリースして、どのような反響やリアクションを受けましたか?
Anan:大体僕らが耳にする評判はポジティブな反応が多くて、嬉しかったですね。でも、欲を言えばもうちょっと広がっていってほしかったなっていう思いはありました。
――制作の中心的役割を担うことになった上でのプレッシャーや重圧などは感じていましたか?
Anan:もちろん自分が中心になって作っていくに辺り、PAELLASっていうバンドを今後どういう方向性に持っていくべきかっていうことも考えてはいましたけど、それが大きな重圧だったかっていうと、今振り返ってみるとそんなこともなかったと思います。
――これまでのPAEELASの活動からすると、今作は結構短いスパンでのリリースになると思うのですが、今作の楽曲はどのくらいの時期から出来上がってきたのでしょうか?
Anan:前作のツアーが2月くらいに終わって、そこからすぐに制作に取り掛かりましたね。『Pressure』をリリースして、余ってた曲とかもほとんどなくて。今作はまっさらな状態、ゼロから作っていきましたね。プリプロもレコーディングもかなりギリギリでしたし。
――楽曲制作のプロセスなどは、前作とあまり変わらず?
Anan:そうですね。でも、前作は僕が一曲まるまる持っていったのがアルバムの半分くらい? だったんです。その他の曲は既存の曲とか、僕が1バースだけ持ってきたものに、みんなで肉付けをしていくっていう感じで作っていて。でも、今回のミニ・アルバムは基本的に全部僕が作って、そこからバンドで細かいところを練っていくっていう方法を取っていて。そこは変わった点だと思いますね。
――メンバーの皆さんにお訊きしたいんですが、Ananさんが持ってくる曲に対して、前作の頃と比べて何か変化を感じましたか?
Ryosuke:かなり変わってきたなって思いますね。これまでのPAELLASと比べるとすごくポップになったなって思うし、メロディの作り方がかなり変わってきたんじゃないかなって。あと、何ていうかすごく頭を使って作った曲だなって感じましたね。前はもっと感覚的だったというか。
Anan:自分でも『Pressure』の頃よりリズムと旋律みたいな部分に対しての意識は変わったなって思いますね。

――感覚じゃないというと、音楽理論に沿って?
Anan:別にそんなに音楽理論をガッツリ勉強していたわけでもないので、あくまで自己流って感じなんですけど、『Pressure』の時は自分が気持ちいメロディっていうか、自分でも歌えるようなメロディの範疇で作ってた気がするんです。でも、今回はちゃんと歌える人が歌うっていうことを前提として、メロディを作っていきました。
――メロディに対して、意識が変わったのは何故なのでしょうか?
Anan:やっぱり、今回の作品でPAELLASをもっともっと広めたいって思って。そのためにはやっぱりメロディが一番重要で。色々な人の耳に残るようなメロディや、印象的なフレーズをいかに作るかっていう部分を今回は大事にしていました。
MATTON:前作はAnanにとってのパーソナルなものを出してきたっていう感じなんですよね。メロディに限らず楽曲全体の雰囲気とかも含めて。でも、(『Pressure』収録の)「Anna」とかは今作の楽曲にも繋がる曲だったのかなって、今振り返ってみると思ったりもするんですけど。
MATTON:もちろん今作にもAnanのパーソナルなカラーはあるんですけど、今回はそこに加えてより音楽的、理論的な肉付けがされているというか。もっともっとたくさんの人に聴いてもらいたいっていう想いが伝わってくるような楽曲になっていると思いますね。
そもそも、僕らは元々ポップな音楽が好きなんですよね。だから、今回レーベルが変わって、いきなりポップな作品をリリースすると、ちょっと穿った目で見られる部分もあるのかもしれないんですけど、僕らにとっては前作も、あの当時の自分たちなりのポップなものを目指して作った作品なわけで。それでリリースしてみて、「まだ足りないな」って思ったから、今回はさらにポップな方向に舵を切ってみた。すごく自然な流れだと思いますね。
Anan:別にJ-POP的なポップさとは全くの別物だし、今後もそういうものを目指す気もないですし、僕らはもっと世界基準でのポップスを目指したいんですよね。Michael JacksonとかHall & Oates、最近で言ったらThe Weekndだったり。そういうもっと音楽的に豊かなポップスを目標としていきたい。
――前作制作時にはFrank Oceanの影響が大きかったとおっしゃっていましたが、今作では今名前が挙がったThe Weekndや近年のJustin Bieberなど、もっと大文字のポップスに惹かれるようになったそうですね。
Anan:そうですね。The Weekndは今聴いても全然カッコいいなって思いますし。もっと最近で言うと、僕は個人的に生音を使ったハウスとかに惹かれていますね。例えばDan Kyeっていうアーティストとかにハマってて。〈Rhythm Section〉っていうレーベルがあって、そこがリリースしている作品が全部いいんですよね。例えばビートがドラム・マシーンでも、ベースが生音だったり。そういうハウスばっかり聴いてますね。そういうサウンドをPAELLASでやるかって言われたらちょっとわからないですけど。
――今作で言えば「MOTN」が最もそういったクラブ・ミュージック寄りの楽曲ですよね。
Anan:そうですね。確かにあの曲はそういった質感を表現した曲ですね。あの曲はbisshiが基本的にエディットしてたんですけど。
bisshi:Ananが各曲毎に参考にする曲をまとめたプレイリストがあって。「MOTN」で言えば確かにそこにDan KyeとかKAYTRANADAが入っていて。自分も元々そういうサウンドが好きだったので、それを素直に反映させたって言う感じですね。KAYTRANADAを土台にしつつ、上モノはDan Kyeに寄せていったというか。
Anan:あと、ソウル・シンガーのGavin Turekの作品の音作りも参考にしていましたね。すごいカッコいいプロダクションなんですよ。
――前作リリース時にはリミックス・コンテンストを開いたりもしていたので、最初はもっとクラブ・ミュージックに寄りの作品になるのかと思っていたのですが、実際には全体的にかなりポップに開かれた作風となっていて驚きました。
Ryosuke:あのリミックス・コンテストに関しては、ただのプロモーションの一環というか、特に深い意味というか目的はなかったんです。
bisshi:ただ「おれらがやったらおもしろそう」っていう、それだけっていう感じだよね。
MATTON:バンドのモードが変化していったのは、そのリミックス・コンテストよりもツアーでライブをこなしていったっていうことが一番の要因だったのかなって僕は思いますね。
Ryosuke:確かに。ツアーの車の中とかで、「もっとこういう曲が欲しいよね」とか、そういう話は常にしてたよね。
――前作はあまりライブを意識することなく作られたともおっしゃっていたと思いますが、今作は最初から意識していたのでしょうか?
Ryosuke:でも、それは今回も一緒だよね。
MATTON:まぁミックスとか音選びっていう部分では意識はしていないけど……。
Anan:ライブを意識していないっていうのは今作も前作も同じですけど、今回はMATTONが歌って僕がギター、bisshiがベースを弾いて、Ryosukeさんがドラムを叩いてmsd.くんがサンプラーでっていう編成を意識しながら、そこに沿って作ったつもりです。逆に『Pressure』の時は自分たちの編成とかを全然意識せずに作っていたので。そういう意味では、結果的にライブを意識したっていうことになるのかなって思いますね。
MATTON:自分たちの肉体を使って演奏して、お客さんに揺れてもらうっていうのはみんな意識してたところだと思います。
――あと、単純に音が派手になりましたよね。なので、ライブでもすごく映えそうだなって。
Anan:シンセとかの音色だったり、生ドラムの抑揚だったりが関係していると思います。前はシンセもこじんまりとした音を好んでいたんですけど。
――前作制作時はアナログ・シンセにハマってたそうですね。
Anan:はい。でも、今回はアナログ、デジタル半々くらいですね。シンセ奏者の方をお呼びして、「こういう感じで」っていうイメージを伝えて弾いてもらうことで、プロフェッショナルな音にしてもらったり。その結果、自分たちだけでは中々できなかったであろう派手な音にすることができました。あとは今回、エンジニアに葛西さん(葛西敏彦)が加わってくれたことが大きいですね。ドラムテックの人にも入ってもらったし。
MATTON:そこは一番大きい変化だと思いますね。これまでの制作環境と比べて。
Ryosuke:元々レコーディングする前からAnanが「ドラムを生で録りたい」って言ってたんで。そのAnanが目指しているヴィジョンっていうものに近づけるために、ドラムテックの人に入ってもらったり、葛西さんともじっくり話をしながら詰めていって。完成形みたいなものをある程度全員で共有できていたのが大きいと思いますね。前作の時は僕がエンジニアリングして、bisshiがミックスして、みたいな感じだったんで。
bisshi:かなりDIYな感じでしたね(笑)。
Ryosuke:死にそうになりながらやってたよね。
bisshi:その頃と比べたら、そもそも実際に作業している時間も全然違うので、当たり前ですけどクオリティは高くなりましたよね。あとは、バンド以外の人が多く関わってくれたので、ビシっと決められた期間内で集中して作業に臨んだんじゃないかなって思いました。自分たちでやっていた時は、結構ダラダラ作業しちゃうことも多かったので。

Ryosuke:終わりが見えないし、一生かかるのかなって思ったよね。前回は。
Anan:音色の選び方にしても、時間が決められていたので、みんなで集中して判断して。前回は色々と試してみたりとかしてたんですけど、今回はテキパキと決断することができて。
Ryosuke:「こういう音を出すためにはどうしたらいいんだろう」ってなった時に、前までだったら実際に弾いてみたり一回一回試行錯誤していたんですけど、今回は葛西さんにざっくりとイメージを伝えるだけで、一発でその音にしてくれて。だから、その完成形に近づくための道のりは格段に早くなりましたね。
――PAELLASとしては、エンジニアさんと共に作業するというのは、今回が初めてだったのでしょうか?
MATTON:これまでにももちろんミックスやマスタリングの作業ではエンジニアさんにお願いしていました。でも、これはちょっとおこがましい話かもしれないんですけど、実際に自分たちが信頼した耳とセンスを持っていて、自分たちと感覚が近い人と一緒に作品を完成させていくっていう意味では今回が初めてでしたね。
――その葛西さんの視点、意見が加わることにより、自分たちのサウンドに対する新たな発見、気付きなどはありましたか?
MATTON:自分たちの新たな一面を引き出してくれるっていうよりも、PAELLASらしさみたいなものをより引きずり出してくれたっていう方が近いかもしれないですね。自分たちが「こうしたい」って思っている音やアイディアを実現させてくれる。でも、確かにその引きずり出してくれたものを聴いて、また新たなアイディアや考えが自分たちの中で生まれてくるっていうのはあったと思いますけど。
Anan:「こういう音がいいんじゃない?」とか、そういう導き方をしてくれるっていうよりかは、本当に僕らと近い感覚、視点で一緒に制作していって。
Ryosuke:どっちかっていうと、レコーディング期間中はメンバーがひとり増えたっていう感じだったよね。
MATTON:曲っていうのは人の好みによるので、もしかしたら前の方向性の方が好きだったっていう人もいるかもしれないですけど、単純な録音物のクオリティとしては、これまでの作品と比べても今回がダントツで一番だと思います。
――1曲目の「Together」、そして2曲目の「Shooting Star」では初の日本語詩に挑戦していますが、これはどういったところから生まれたアイディアなのでしょうか?
MATTON:前作をリリースして、ライブをこなしていく中で、やっぱりどうしたって言葉が届かないというか、そういう印象を感じてしまうことがあって。それはもちろん僕の力量云々の話もあると思うんですけど、やっぱり英語っていう言語としての問題もたぶん大きくて。日本語わかるからって、初見で日本語詩の曲を聴いて全て歌詞を聴き取れるわけではないと思うんですけど、断片的にでも頭に入ってくるフレーズってあるじゃないですか。英語詩で歌っていると、事前に聴いてきてくれたお客さん、もしくは英語がわかる人でも、そういう部分で中々に難しいなって思うようになってきて。さっきも話しに出たことだと思うんですけど、今回の作品はもっともっと広い層に届けたいっていう想いもあったので、自然と日本語詩に挑戦してみようってなったんですよね。ただ、タイミング的なことも考えていて、本当は今作じゃなくてもいいかなって思ってたんです。でも、制作していく上で、やっぱり今しかないなって思ったんですよね。なぜか。
――Ananさんが作ってきたトラックを聴いて、今回日本語詩でトライしてみようって思ったのでしょうか?
MATTON:そうですね。単純に「歌詞を書くぞ」ってなった時に、もう日本語の方が先に出てくるようになっちゃったんですよね。なんならできれば全てを日本語で書きたい、くらいの感じにもなったんですけど、まぁ、音がメロディに乗るかっていうところで難しい部分もあって。「Fade」っていう曲も最初は日本語で書いてみたんですけど、やってみたら合わなくて。それで英語詩で作り直しました。たぶん今後もそういう試行錯誤はあると思いますね。……ただ、今回リードになる曲は日本語詩で作りたいっていうのは、曲を聴く前から考えていたと思いますね。
――実際に日本語で書いてみてどうでした?
MATTON:PAELLASとして日本語詩の曲を世に出すっていうのは初めてなんですけど、個人的には以前から書いたりしていたこともあって。それこそ日本語だと街を歩いてるときでもポンって自然に頭に思い浮かんだりするんですよね。なので、単純に作りやすい。けど、同時にメロディに乗せて、カッコよく仕上げるのは難しい。だからこそ、バッチリメロディにハマった時は英語の時よりもやりがいを感じるというか、喜びがありますね。これは完全に個人的な感情なんですけど。元々全然日本語詩の音楽も聴いてましたし、抵抗があったわけではないので。

――今作にはサウンド面、リリックの面でも前作リリース後のツアーでの経験などが活きているとの話でしたが、既に東京でも長いキャリアを持つPAELLASから見て、国内のインディペンデントなバンド・シーンに対して、何か変化を感じたりすることはありますか?
MATTON:もはや……シーンとかそんなものは何もないというか(笑)。いや、実際はあるんですけどね。まだ全然知られてないけどカッコいいバンドとかもいて、たまに観に行ったりもしてるんですけど。ただ、シーンみたいなものは……やっぱり、もう別にないんじゃないんですかね。2015年くらいから消えてなくなってるんじゃないかなって、僕は思いますね。
――海外のインディ・ロック〜オルタナティブなR&Bからの影響を自身のサウンドに上手く落とし込み、それぞれ独自のサウンドを鳴らしているっていう意味では、やはりD.A.N.やyahyelの名前を出してシーンのように括ってしまいたくもなりますが、往々にしてシーンというものはそういった外野の人間が形式的に作りあげたものであって、当事者たちや現場では実体がないものだったりしますよね。
MATTON:そうですね。たぶん、当事者たちはみんなシーンみたいなものは全く意識していないと思いますね。D.A.N.もyahyelも、あとはWONKとかもそうなんですかね。直接話したこともあるし、彼らのインタビューとか見ても、主張していることや価値観が全く異なっているんですよね。なので、変な意味じゃないですけど、そこにシンパシーとかを感じるとか、そういうことはないですね。僕はWONKのボーカルのKentoくんと一度対談させてもらったこともあるんですけど、そこでも本当に考えていることや、バンドとしてどう活動していきたいかっていう部分で、僕らとは違うスタイルなんだなって思いましたね。
Anan:単純に日本だから目立つっていうだけで、もしここがアメリカだったとしたら、そういったバンドが一緒くたに語られることはたぶんないだろうし。もちろんみんな自分たちが好きな音を鳴らしているっていう部分は共通しているかもしれないですけど。
MATTON:もちろんお互いインプットしているものには共通するものがあると思うんです。だから、アウトプットしているものが全然違ったり、思想や価値観がバラバラでも、そういった部分を何となく汲み取って一緒に聴いてくれてる人もいるのかな、とは思いますけどね。
Ryosuke:みんなで盛り上げようとか、そういう雰囲気も特にないしね。
MATTON:うん。あと、最近一緒になるバンドの人たちは、結構ハッキリしているというか。僕らが東京に出てきた時は、いい意味でもうちょっとゆるい雰囲気だったんですよね。音楽のジャンルとかは違うけど、インプットが近ければ友達半分、ライバル半分、みたいな感じで。横の繋がりとかも結構あって。
Anan:でも、そういう同世代のバンドたちが次にどういうことするのかなっていうのは純粋に気になりますけどね。
MATTON:そうだね。でも、彼らはどう思ってるかわからないよね。他のバンドのことは全く気にしないっていう人もいるし。何か、バンドってある意味ブランドというか企業みたいな部分もあるじゃないですか。そういう意味で言うところの、「企業理念」みたいなところを、みんな結構明確に、ハッキリと持っているバンドが多いなって思いますね。
――なるほど。では、PAELLASはいかがでしょうか? そういった理念やスタンスなどを明確に共有できていますか?
Anan:バンドとしての音楽面でのアイデンティティはかなり固まってきたと思います。この構成で、R&Bだったりハウスに寄ったサウンドを奏でるっていう、それがある種のブランディングにもなってくると思いますし。
MATTON:さっきおっしゃっていた通り、僕らは結構活動歴が長くて。それこそ最初の方はそういう考えもないまま始めちゃったっていう歴史があるので、今さらブランディングとかコンセプトみたいなものを固めるっていうのができない。っていうか、正直そんなことはやってらんないんですよね(笑)。なので、周囲の人とも一緒に作業していく中で、ある程度任せるところは任せちゃうっていうか。僕らはわりと柔軟な方なんじゃないかなって思いますけどね。
あと、これは僕だけだと思うんですけど、色々なバンドを観ていく中で、まだ誰もやっていないようなことをやりたいなっていうのは考えていて。もちろんそういう新しい要素はスパイス程度でいいと思っているんですけど、さりげなくどっかに入れたいなって思いますね。それはサウンド面に限らず、バンドとしての見せ方とかも含めて。
――これまで様々なレーベル、プロダクションを移籍してきたPAELLASですが、その経験を踏まえた上で、自分たちにとってベストだと思う活動スタイルをとるためには、レーベル、マネージメントはどのように機能していくべき、どのように機能して欲しいと思いますか?
Ryosuke:でも、お世辞じゃなくて、結構今が理想に近いんじゃないかなって思いますけどね。何ていうんですかね、簡単に言ってしまえば僕らがやりたいことを本当にやらせてくれるんですよ。
MATTON:うん。やりたいけど、自分たちの力じゃなかなかできない部分をやってくれるし。レコーディングやプロモーション施策もそうですし。
Ryosuke:リリースのタイミング決めるのとかもそうだしね。あとは……ツアーに行く時に運転もしてくれたり(笑)。今までは誰かが運転して、もうひとり誰かが起きててみたいな感じでしたけど。でも、今となってよく考えたら、自分たちで長時間運転してツアーして、100%の演奏できるのかって言われたら厳しいですよね。

MATTON:だからこそ、もう言い訳できないっていうのもありますけどね。
Ryosuke:そういった細々としたことをやってくれる分、僕らはそれぞれプレイヤーとしての向上に集中できるというか。
――では、今の環境がこれまでで一番音楽制作、音楽活動に集中できていると。
MATTON:それは間違いないですね。あと、音楽と、それを演奏するミュージシャンっていうものに対する理解が深いというか。他のレーベルに所属しているバンドとかの話を聞いたりする限りではそう感じますね。もちろん今までのレーベルがどうこうっていう話ではなく、やっと自分たちの考え、スタンスもそこに追いついてきたっていうのもあると思うんですけど。これまではマネージメントっていう契約がなくて、レーベルとして作品毎の契約だったんです。なので、その中でやってくれていたこともたくさんあるんですけど。
Anan:アーティストと目線が近いっていうのは、一緒に仕事していく中ですごく重要なことなんじゃないかなって思います。マネージメントにしろ、エンジニアリングにしろ、僕らも向こうのことを理解できないし、向こうも僕らのことを理解できないような状態だと、やりたいことと実際にできあがってくる作品にギャップが生まれてきてしまうんじゃないかなって。
Ryosuke:僕はPAELLASに入る前から結構長くバンドをやってきているんですけど、初めてって言っていいくらい音楽業界で”いい大人”に出会えました。ちゃんと僕らのことも考えてくれるし、会社のことももちろん考えてるし、いいバランス感覚で。本当にチームだなって思えるんですよね。
MATTON:音楽の趣味も合うしね。マネージャーが車でかける音楽とかを聴いたりするんですけど、そこで色々情報を得たり。
Ryosuke:あんまり喋らなくても大丈夫だしね。気遣わなくていいんですよ。なので、すごく楽です(笑)。
――今作の制作で曲やアイディアなどは出し切ったとおっしゃっていましたが、今現在のPAELLASはやはりライブへのモードに向かっている感じなのでしょうか?
Ryosuke:そうですね。新曲も早くやりたいですし、ツアーが楽しみです。
Anan:今はバンドとしてはライブのことしか考えてないですね。

【リリース情報】

PAELLAS『D.R.E.A.M.』
Release Date:2017.09.06 (Wed.)
Label:Space Shower Music
Cat.No.:PECF-3184
Price:¥1,600 + Tax
Tracklist:
1.Together
2.Shooting Star
3.Lying
4.MOTN
5.Fade
6.Eyes On Me
■PAELLAS オフィシャル・サイト:http://paellasband.com/