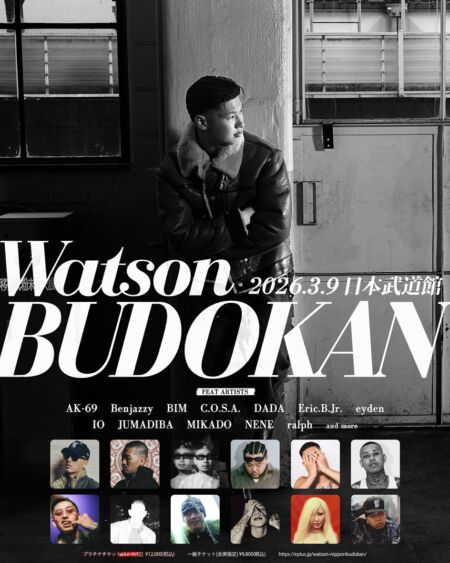ビート・メイカー、illmoreなどを擁するライフ・スタイル・レーベル〈Chilly Source〉と、〈Manhattan Records〉による共同主催イベント“Vibin’Out”が6月21日(金)に東京・渋谷WWWにて開催される。
本イベントにはDJ HASEBE、AKLO、illmore、pinoko、ケンチンミン、15MUS、DJ KROなど、〈Manhattan Records〉、〈Chilly Source〉と縁深いアーティストに加え、1stアルバムのリリースを控えるFNCY、そして、illmoreの客演としてKojoe、CHICO CARLITO、SHOHEY from THREE1989などの出演がアナウンスされている。
さらに、当日は〈Chilly Source〉リーダー・DJ KROによる会場限定MIX CDが販売されるなど、大型イベントへの気合の入りようが伝わってくる。
そこで今回は昨年末に待望の1stアルバム『ivy』をリリースした俊英・illmoreのインタビューをお届けする。リリース後も高い評価とプロップスを得ている同作の制作背景、そしてillmore本人のキャリアについて、この機会に改めて振り返りたい。
Interview & Text by Ryota Inoue
Photo by Takazumi Hosaka

リスペクトする面々と作り上げた集大成
――最新作『ivy』は、これまでの『11』だったり『mood』といった、サンプリング主体で作っている、ある意味初期衝動的な作品とは異なる印象を受けました。より広い層へと届けることを意識しているんじゃないかなと。制作の手法という部分では、これまでの作品と何か異なる面はありますか?
illmore:実はこれまでも、サンプリングだけじゃなくて自分で作っている作品もあったんです。(Native Instrumentsの)MaschineをメインにKompleteとかに入ってる音源も使って、弾いたり打ち込んだり。ただ、それをまとまった形にするまでには至らなかったんです。やっぱりサンプリングに比べると、制作するスピードが違くてどうしても遅くなっちゃうんですよね。『mood』とかはサンプリングの曲が溜まってきたから出そうかなっていうの感じの作品で。自分の中では今回みたいなオリジナルの作品も作りたいなっていう想いはずっとあったんです。あと、インストだけじゃなくて、これまでの活動で繋がったラッパーさんやシンガーさんにも参加してもらいたくて。満を持して自分からオファーを出して、完成させたのが『ivy』っていう感じですね。
――客演に名を連ねてるアーティストの方たちは、illmoreさんが信頼している面々だと。THREE1989のSHOHEYさんの参加は、個人的にも意外でした。
illmore:SHOHEYくんは2017年の12月くらいに福岡のイベントで一緒になって。大分のケンチンミンがTHREE1989と繋がっていて、それで紹介してもらいました。ライブもめちゃくちゃ良かったし、SHOHEYくんはヒップホップもすごく好きみたいで、絶対いつか一緒にやりたいなと思っていて。そのライブの1ヶ月後くらいに、『テラスハウス』観てたらSHOHEYくんが出ていて(笑)。それきっかけでまた連絡を取り、今回のコラボが実現しました。「Parade」のビート自体はちょっと前に作っていたもので、出す機会が中々なかったやつだったんです。SHOHEYくんだったらこのビートを完成に導いてくれるんじゃないかなって思って、お願いしました。本当に今回は丸投げみたいな形でしたね。「SHOHEYくんの感じるようにやって欲しいです」っていう。
――制作時に、ラッパーだったらフロウとか、シンガーだったらメロディだったり、そういったトラックに対してのアプローチの仕方を指示というかディレクションをすることは?
illmore:普段は結構お伝えするんですけど、今回のアルバムに関しては、ガチガチにストーリーやコンセプトを組んだわけではないので、結構お任せする形が多かったですね。もちろん何度かキャッチボールしたり、「愛について歌って」とか、そういうざっくりとしたテーマをお伝えすることはありましたけど。
――歌とかラップが返ってきた時に、トラックを手直ししたりっていうのは?
illmore:それは結構ありますね。「BOYS! feat. サトウユウヤ」とか「Rain feat. 18scott」は、最初はワン・ループの状態で渡して、返ってきてから展開を変えてみたり。向こうから意見を言ってくれることも多くて。お互いのアイディアや意見を入れつつ、ミックスまで仕上げました。
――CHICO CARLITOさんが参加した「Compass」は、オートチューンを駆使するなど、彼にとっても新たな挑戦となった作品だと思います。これはどちらのアイディアで?
illmore:どうだっただろう。たぶん、オートチューンをかけたのは僕だと思います。曲の質感というか雰囲気的に必要だなと感じて。あの曲は結構CHICOも悩んでて。ふたりで試行錯誤しながら完成させた記憶があります。CHICOも「あの曲、もう提出しちゃった? もしまだならまた録り直したいんだけど」って言ってくれたり。

――録音は客演アーティストそれぞれっていう感じですよね。それにも関わらず、全体として違和感を感じさせない音作りになっているのが流石だなと思いました。
illmore:はい。レコーディングは皆さんそれぞれにお願いしています。今回はミックスとマスタリングまで自分でやっているので、そこで調整できたのかなって。結構しんどかったですけど(笑)。
――個人的には、MuKuRoさんが参加している「Still Living」が今回のアルバムの中ではちょっと異質な曲かなと思いました。ベルの音色が強く出ていて、リリックも少し好戦的な内容で。
illmore:そうですね。最初は違うビートで投げていたんですけど、それをMuKuRoがめっちゃ気に入ってしまって。本人だけじゃなくて〈Pitch Odd Mansion〉の面々からも、「ごめん、このビートはMuKuRoの曲として出したい」って言ってきたので、彼に提供しました。最初はクールだけど少しキャッチーな感じのビートだったんです。新たにビート渡して完成させた「Still Living」は、MuKuRoのイカつい面も出ていてすごく気に入っています。ミックスがすごく大変でしたけど(笑)。
CHICO CARLITO、MuKuRo、唾奇ら沖縄勢との親交
――illmoreさんは今回のアルバムに限らず、CHICO CARLITOさんやMuKuRoさんなど、沖縄のラッパー勢との繋がりも深いですよね。
illmore:最初は“Beat Grand Prix”(2015年よりスタートした、日本最大級のトラック・メイク大会)の第1回目の時にSweet Williamと出会って。同い年だし、予選の時からカッコいいって思ってて、話しかけて仲良くなったんです。その時から〈Pitch Odd Mansion〉の話は少し聞いてて、TENとかも会場で会ったりしましたし。その2回目の時に、もっと密に〈Pitch Odd Mansion〉周りの人たちと知り合って。その中でも特に唾奇はカッコいいなって思ったので、大分のイベントに、唾奇とSweet Williamを呼びたいなって思ったんです。そしたらちょうどアルバムを出すっていう話を聞いて。ケンチンミンとかと一緒に遊んだりしましたね。その後、今度は唾奇が沖縄のイベントに自分を呼んでくれて、それで沖縄のラッパーたちと繋がったっていう感じです。
――なるほど。
illmore:その時のおもしろい話があって。沖縄に行った時、宿はAirbnbで取ったんですけど、その民家っていうのが唾奇が昔住んでた実家だったんです(笑)。「Kikuzato」のMV撮影とか、Recとかもやっていたところで。そこに604(唾奇やMuKuRo、MAVELなどが名を連ねる沖縄のクルー)の面々もみんな集まってきて。そういう出来事も、何だかんだ深く繋がるきっかけになった気がします。
――運命というか、奇遇過ぎますね(笑)。そういった色々な出会いも経て、〈Pitch Odd Mansion〉のコンピ(2017年リリースの『Pitch Odd Mansion & MS Entertainment Presents“2 HORNS CITY #1 -MARS DINER-”』)に参加されると。
illmore:はい。あれは(國枝)真太郎から直接連絡をもらって。〈Pitch Odd Mansion〉のメンバーは大体みんなタメなんですよね。1991年生まれ。
――同世代で特に気になる、もしくはリスペクトするビート・メイカーは?
illmore:難しいですね……。同世代にビート・メイカーがいっぱいいるような気がして。それよりも、同世代じゃないんですけど、兵庫県のdhrmaは自分にはないセンスが感じられてすごく気になってますね。
「カッコいい音を鳴らし続ければ、それが自然と自分の音になる」
――illmoreさんの音っていうのはすごく確立されてきているように思っていて。日本のヒップホップの流れとして、〈Dogear Records〉だったり〈DLiP Records〉だったり、ISSUGIさんやNagmaticさんみたいな、確立されてきた個性的な音があって。その流れの中に新しくillmoreさんの音みたいなものが入ってきたなと個人的には思っていて。ご自身では自分の音をどのように分析できますか?
illmore:自分としてはまだまだ全然だと思っていて。迷ったりすることもあります。今までって、結構アングラとポップなシーンが2極化していましたよね。地方では特に顕著なんですけど、イベントとかもハッキリと棲み分けができていた。でも、僕は元々ヒップホップだけじゃなくて、色々な音楽を聴いてきて。それこそ、小さい頃はクラシックを聴いて、チェロを弾いてましたし。父親はトランペットで母親がピアノとフルート、妹はバイオリンをやっていたり、親戚のオジさんも東京でブルースとかをやってて。そういう家庭環境で育ったんです。だから、「なんでヒップホップはヒップホップだけなんだ」とか、「そもそもヒップホップってなんだ?」「みんなそれぞれのヒップホップがあるじゃん」って思うようになって。

illmore:そういうしがらみが嫌になり、DJとかもやめてビート・メイクに没頭するようになりました。元々お酒飲んでワーって騒ぐようなタイプでもなかったですし、色々なジャンルの音楽の中でも、特にリラックスした、レイドバックしたようなムードの楽曲が好きだったっていうのもあって、こういうスタイルになったんだと思います。
――illmoreさんの作品のレイドバック感というのが、これまでの国内シーンにあったような、例えば〈HYDEOUT PRODUCTIONS〉の感じとは異なるようなアプローチだなと感じていて。より太いというか、重い。illmoreさんの音楽に出会った時に、「懐かしい」という感覚と同時に、素直に「新しい」と思ったのを記憶しています。
illmore:ありがとうございます。それは嬉しいです。
――そもそも、クラシック音楽を嗜むような家庭環境で生まれ育ったillmoreさんは、どのようにしてヒップホップに出会ったのでしょうか?
illmore:小さい時はみんなと同じようにJ-POPを聴いていて、小学校高学年に上がる頃には洋楽のロックとかを聴いてました。でも、小学5年の時に地元のTSUTAYAで、なぜかEMINEMの『The Eminem Show』を借りるんです。それで「なんじゃこりゃ」っていう衝撃を受けて。最初は「お経みたい」って思ったんです。歌詞カードみたらめっちゃシモネタだし。でも、小さい時だったので、そのワル感というか、背徳感みたいなものに惹かれていきました。それからも洋楽のロックを中心には聴いてたんですけど、中学校くらいでLinkin ParkとかLimp Bizkitみたいなミクスチャーを聴き始めて。そういう流れから気づいたら50 CentとかUsherとか、ブラック・ミュージック寄りになっていき。ベタなところなんですけど、そういう流れでヒップホップに行き着きましたね。
――なるほど。確かにリミックス・アルバム『FRUIT CLUB Vol.1』でも、メジャーどころも抑えつつ、ラグジュアリーなビートで飾りを付けてという感じで、やはりアンダーグラウンドなんだけど、しっかりとオーバグラウンドも見据えているんだなと思いました。
illmore:「おれはアングラだ」とか思うこともないですし、逆に売れるために媚を売ることもないし。好きなことをやってるだけっていう感じですね。ただ、自分としては色々なサウンドを作ってみたいっていう思いがあって、結構バラバラになっちゃってるなって思ってるんです。なので、Olive Oilさんみたいに自分の確固たる核みたいなものを持っている人を見ると「カッコいいな」って憧れちゃうし、自分の音って何なんだろうって考えさせられるんですよね。
illmore:一時期はそういう部分で悩んでこともあったんですけど、どういうサウンドになろうが、ひたすらカッコいい音を鳴らし続ければ、それが自然と自分の音になるのかなって考えるようになって。ちょっと開き直った部分はあります。
――そういう意味でも異質の存在ですね。サンプルのループとドラムのループと、どちらから組むことが多いですか?
illmore:ドラムですね。結構作り溜めておくことも多くて。暇な時にドラムのループだけ組んでおいたりして、そこに合うサンプルをハメていくんです。でも、結果的には組んでいく過程でドラムを差し替えたり作り変えたりすることも多いです。何か、一見ちょっとアンバランスな感じに聴こえる組み合わせとかが好きで。あとは、サンプリングで作ってたけど、そこにシンセとかベースを足していくうちに、「これ、サンプルいらないな」ってなって取っちゃうとか。そういうのもありますし。色々なアプローチで曲を作ってます。
――Machineはジャケに写っている「MK3」ですか?
illmore:こんなこと言うと怒られちゃうかも知れないんですけど、まだ「MK2」をメインに使っていて(笑)。MK3は超便利なんですけど、操作感が結構変わったのと、ケースに入れるとパツパツで。MK2に慣れすぎているのと、自分のライブ・セットとかを移行すると、設定を全部いちから組まなくちゃいけなくて。あと、一番大きいのは、MK2はKojoeさんに頂いたものなんですよ。それに加えて、フェイス・ケースをPopy Oilさんに描いて頂いて。思い入れが強過ぎるんです。
夢が叶った日
ずっと昔から
この日を夢見てた
涙が出る程に嬉しい
いい音 発信していきます
POPY OILさん
ありがとうございました#popyoil #oilworks #oliveoil #fukuoka #9states #japan #maschine #ni #nativeinstruments pic.twitter.com/CoRx3A8tqX— illmore (@illmore18) 2018年9月29日
――確かに、MPCも2000だけ使いたいっていう人とかもいますもんね。慣れてる機材を使うのが一番効率がいいというか。
illmore:Olive Oilさんとかともお話したんですけど、逆にソフトウェアをアップデートしてなかったりして。これ、「4つくらい前のやつじゃないですか?」って言ったら「新しくしたら使い方わからなくなるからこれでやってる」っておっしゃっていて。
――なるほど。DAWもそうですよね。
illmore:ショートカット・キーが変わったり。そういう変化にも慣れてしまえば楽なんでしょうけど、それが大変で(笑)。
――ちなみに、MPCではなくMachineをチョイスする理由というのは?
illmore:元々はMPCを使っていたんですよ。その前はシンセで。たぶん、中学くらいの頃に、『JAPANESE TRACK MAKERS』っていうDVDを観て、「シンセで作れるんだ」って思ってKORGの安いシンセを買って、シーケンスを組んでみたんです。でも、ちょっと音色がダサくて(笑)。それで「なんか違うな」ってなって、MPC2500を買ってみて。手探りでループだけは組めるようになったんですけど、それと同時にDJへの興味も湧いてしまって。DJ機材へも手を出してしまうようになり……。脱線しましたけど、質問はMachineを選ぶ理由ですよね(笑)。
Olive Oil、Kojoeら、先達との出会い
illmore:大学に入ったら誰かトラックメイクのこと教えてくれる人に出会えるだろうって思ってたんですけど、実際は誰もいなくて。そこで〈Chilly Source〉のKROさんと出会えたんですけど。あとは結構DJをやってる人はいて、そのコミュニティに入ったりもしたんですけど、さっきもちょっとお話したように、変なしがらみとかが嫌になってやめて。それからもう一度トラックメイクに戻りました。その時、たまたま出てたのがMachineで。それを持って毎日スタバに行って1日1曲作ったんですよ。本当に手探りで、とりあえずシンプルなワン・ループでいいから作ろうって。その期間死ぬ気で頑張って、一気に習得したんです。それこそ目を瞑っても触れるくらい。ついでにビート・テープも完成しましたし(笑)。
――それが2011年に発表された『The Beat Tape Vol.1』なんですね。
illmore:そうです。最初、誰も聴かないだろうって思ってたんですけど、フリーDLだったんで、結構な人数の方が聴いてくれたみたいで。それはすごく自信に繋がりましたね。
The Beat Tape Vol.1 (2011) / illmore
昔2週間限定で公開したビートテープ
当時入れなかった17曲をボーナスで入れた40曲入りの僕の処女作です
雑な音ばかりですが良ければ聴いてください//https://t.co/yqPlElneMd pic.twitter.com/K9w7HwzDFY— illmore (@illmore18) 2017年4月27日
illmore:そこから本格的にビート・メイクにのめり込んで。KROさんに教えてもらって、先程話した“Beat Grand Prix”にも応募して。でも、その時は決勝ラウンドの14名には残れたんですけど、初戦で負けちゃって。大分でビート・メイクしている人なんて自分くらいしかいなかったし、その時はちょっと調子に乗ってたんでかなり悔しくて。悔しすぎて、負けたってわかった瞬間クラブから出ていこうとしたんですよ。そしたら、Olive Oilさんが話しかけてくれて。「1曲聴いたけど、マジヤバイなって思った」「同じ九州だし、頑張っていこうよ」みたいな感じで。それですっごく救われましたね。その後、応援に来てくれてた後輩の車で大泣きして。悔しさと嬉しさと、頑張ろうっていう思いとが混ざって、よくわからない感情なんだけど涙が止まらなくなって。そっから半年くらいで仕事も辞めました。もちろんその間にはKojoeさんとの出会いも大きく影響しているんですけど
――よりハングリー精神が出たと。では、今回のアルバムにも参加しているKojoeさんとの出会いについても教えてもらえますか?
illmore:それこそ大会の後、3ヶ月後くらいに福岡で開催された〈Oil Works〉のイベントに、僕をゲストで呼んで頂いたんです。当時まだまだ無名ですし、「ギャラなんて頂けません」って言ったんですけど、「いや、ギャラは払わないわけにはいかない」って言ってくださって。実際、当日はガッツリとビート・ライブをやらせてもらって、終わった後には「MVPだったよ〜」って、Olive Oilさんが並々の泡盛を渡してくれて。僕、お酒弱いんですけど、その日の泡盛は美味しく感じたっていうのは強く覚えてますね。
話は戻るんですけど、そのイベントの前に、Olive OilさんがKojoeさんと一緒にリリースした『blacknote』っていうジョイント・アルバムのアカペラを僕に送ってきてくれて。直接は言われてないんですけど、これはリミックスしろっていうことだなと。それに応えたくて、「回る」のリミックスを作りました。
illmore:それをYouTubeにUPして、Olive Oilさんにも連絡して。いざイベント当日、リハするために会場に入ったら、Kojoeさんもいて。「え? フライヤーに名前載ってなかったのに!」って、どうやらシークレット・ゲストだったらしく(笑)。「あの、ま、まわ、まわ、“回る”のリミ、リミックスを……」って、めちゃくちゃ噛みながら挨拶させてもらったら、「お前かよ〜」って。どうやらリミックスも聴いていてくれたみたいで。ライブ終わった後に「ビート聴かせてよ」って言ってくれたので、ビート・テープをお渡しして。その3ヶ月後にもたまたまKojoeさんが大分に来る機会があって、また新たに2枚くらいビート・テープをお渡しして。そしたら「一緒に何かやろうよ」って言ってくれました。その時、Kojoeさんもちょうど福岡に住んでいて。
――そうなんですね。
illmore:僕も後から知ったんですよ。それで、「福岡来なよ」って言われたので、超緊張しながら福岡のコーヒー屋さんで待ち合わせして。6時間くらい色々なお話ししました。それこそここでは言えないこととかも(笑)。「お前さ、インスタとかで動画UPしてるじゃん。絶対映像も制作してDVDで出した方がいいよ」とか、「カセットテープ出そうぜ」とか、色々なアイディアを挙げてくれたりして。あとは結構色々な案件も振ってくれて、僕は「試されている」って思ったので、その一個一個に超緊張しながら死ぬ気で応えて。たぶん、そこで徐々に信頼してもらえて、そして『here』(2017年発表のKojoeのアルバム。illmoreは6曲をプロデュース)や『da Flip』(Kojoeの過去音源をリミックスした作品)に繋がったんだと思ってます。
――間違いない。
illmore:最初は緊張してたし、ビビってて。当時はショート・メッセージでやり取りしていて、他の人は基本的にLINEでやり取りなので、必然的にKojoeさんだけ通知音が違くて。その音が鳴る度に背筋が伸びるというか(笑)。ちゃんとしなくちゃ! って思ってましたね。もちろん、今ではLINEでも繋がって、すごく良くしてもらっていて。一回り以上離れてる僕みたいなやつにも、フランクに接してくれて、いつも気にかけてくれてるし。知れば知るほど優しさと愛に溢れた人だなって思います。リスペクトと感謝しかないですね。
「やりたいことが多すぎて、『次はこれ!』って絞れない」
――Kojoeさんってビート・メイクやプロデュースに加えて、ラップも自身でやるじゃないですか。illmoreさんはラップをやろうと思ったことはないのでしょうか?
illmore:実はラップしようと思ったことはあって。一応2曲録ってるんですけど、絶対調べないでほしいし、できれば聴かないでもらいたい(笑)。僕、リリックが書けないんですよね。朝から晩までビート作ってるし、週末もそんなにクラブとかにも行かない。お酒も飲まない。何かリリックにするトピックみたいなものが思いつかないんですよね。今言った2曲のうち1曲はビート・メイクについて書いていて、もう片方は地元への愚痴というか、言葉だけで動かないやつへのディス。それ以外書くことが本当になくて(笑)。ゴースト・ライターがいれば全然やりますけど、それじゃあ説得力は生まれないですよね。
――まさしくビート職人ですね。でも、自身でラップをすること自体には抵抗はないと。
illmore:そうですね。他のアーティストさんと一緒にやってる時に、「めちゃくちゃヤバいビートができた! これに対してどういうラップを乗っけてくれるんだろう」ってワクワクしながら待ってても、色々な理由で半年くらい返ってこないとか、結構そういうのもザラにあって。そういう時に自分でラップできれば、一番フレッシュな状態で世に出せるなって思うことはありますね。ただ、やっぱりラッパーとかシンガーみたいな立場には自分はなれない。下手にワルぶるのも違いますし。なので、リリックだけ書いてもらって、それを自分でラップして、素材のように使う。そうやってビート・メイクの一部みたいな感じにするのは、自分的に結構アリなのかなって思いますね。
――自分の声ネタをサンプリングのように使うことはあるのでしょうか?
illmore:実は絶対にバレないようなレベルで一時期やってたこともありますね。どの作品に使ってたのか自分でも忘れてるんですけど、クラップのように聴こえる音が、実は自分の声だったり。そういうこともやってました。
――illmoreさんの作品って、結構声ネタを使うことも多いなって思っていて。ああいうのはどうやって探しているんでしょうか? やはり映画とかで?
illmore:いや、自分の場合はほとんどYouTubeですね。映画って基本的に1時間半とか2時間くらいあるじゃないですか、その時間ジッとしてるなら、その時間でビートを作りたくなっちゃうんですよ(笑)。
――ハハハ(笑)。本当に一貫してますね。
illmore:ジッとしてられないし、もっと効率よく色々な情報を取り入れたいんですよね。なので、ネットで色々な映像や作品を早回しで観たりして。使えそうなところを取り入れていきます。そうやってサンプリングした素材、声ネタとかフレーズとかトランペットとか、そういうのを全部コード毎にフォルダ分けしてストックしています。パッといつでも取り出せるように。自分、整理整頓は苦手なんですけど、ビート・メイクに関することだけはちゃんとやろうと思って。
――なるほど。今作でいうと、「Infinity feat. BUPPON」のサンプリングは映画からですよね。
illmore:そうですね。あれは日本の古い、白黒時代の映画からですね。
――そういう風にサンプリングを使った曲って、客演の方とはどういう風に詰めていくんでしょうか?
illmore:あの曲に関しては、最初からサンプルが入っている状態で送って、「こういう感じで考えてます。(サンプルは)カットもできますけど、どうでしょうか?」ってお聞きして。そしたら「全然大丈夫。これでいこう」って言ってくれたので。
――今作に限らず、illmoreさんが「一緒にやりたい」と思うラッパーの特徴を挙げるとしたら、どういう要素になると思いますか?
illmore:僕は洋楽から入ったので、基本的に英語の内容は聞き取れない。だから、必然的にビート先行で聴いてしまうし、ラップも音として捉えてしまう。こんな根っからなビート・メイカーな自分なんですけど、それでも聴いてるうちにスッとリリックの内容が入ってくる日本語ラップっていうのがあって。唾奇とかはまさにそうなんですけど。自分はそういうラッパーはリスペクトしますし、一緒にやりたいって思いますね。BUPPONさんもまさしくそういうタイプの、“言葉が入ってくる”ラッパーさんですよね。あとは、結構メロディを作れるラッパーさんにも惹かれますね。
――確かに。Kojoeさんとかもそうですし、サトウユウヤさんとかも当てはまりますね。
illmore:本当にシンプルな、武骨なラップっていうのも好きなんですけど、色々なことを器用にこなせる人の方が自分に合うのかなって。今回のアルバムでも、別に僕からは言ってないんですけど、結果として全員歌ってくれて。
――個人的にはBASIさんが参加した「Drunk」の2バース目で、illmoreさんとの出会いを歌っていて。個人的にはそこも胸アツなポイントでした。
illmore:BASIさんはさっき言った僕が始めて作ったビート・テープを聴いていてくれたんですよ。
――リリックにもありますよね。「ずっと落としてループしてたよビート・テープ」と。
illmore:はい。KojoeさんとかOlive Oilさんに出会う前の、本当に何者でもない頃からInstagramとかでも連絡してくれて。そこから5年とか6年を経て、僕たちのイベントに出て頂いて。その時のことを歌ってくれているんです。出会った時からこれまでの、この6年くらいが全部表現された曲になっていて。
illmore:あとは、その僕たちのイベントに来てくれた友達とかからも、「あの日のことが曲になってる!」って連絡してきてくれたり。僕らだけじゃなくて、あの日、あの場所で時間を共有した人たちの曲にもなってるんです。だからこそ、MVも会場になった(東京・日本橋)CITANで、またお客さんに集まってもらって、自然なイベントみたいな感じで撮りました。みんなの思い出みたいになる曲にしたかったんです。
――最後に、今回1stアルバム『ivy』をリリースしましたが、今後の展望があれば教えてください。個人でも、〈Chilly Source〉としての動きでも。
illmore:バチッと決まってるわけではないんですけど、とりあえず個人としてはプロデュース・ワークというものをもっとやっていきたい。それは自分のビートじゃなくてもいいのかなって思っています。
――今のお話を聞くと、ある意味Nao’ymtさんとも繋がるものがあるような気がして。
illmore:Nao’ymtさん、大好きです。
――ですよね。Nao’ymtさんって、安室奈美恵さんとかもそうですし、Foxxi misQとかの作品で知られていますよね。そういったメジャー・フィールドでも活躍できそうだなと。
illmore:もちろんそういう機会があればやりたいです。でも、やりたいことが多すぎて、「次はこれ!」って絞れないんですよね。制作に関して言えば、フックだけ自分で歌ったりとか、そういう新しいスタイルも試したい。さっき言わなかったんですけど、アーティストさんに送る時に、自分でメロディ作って、仮歌入れて渡す時もあるんですよ。「こんな感じで作ったけど、どう?」って。
――それは聴いてみたいですね。
illmore:ライブでも自分で歌えたらいいですよね。全部自分で完結しますし。ちょっと落ち着いたらそういうこともしてみたいです。一歩一歩、成長していきたいです。

【リリース情報】

illmore 『ivy』
Release Date:2018.11.07 (Wed.)
Label:Manhattan Recordings
Cat.No.:LEXCD18020
Price:¥2,300 + Tax
Tracklist:
1. ivy
2. BOYS! feat.サトウユウヤ
3. Bullet Proof feat.KOJOE
4. 思い出す feat.おかもとえみ
5. Nonfiction feat.JIVA Nel MONDO & kiki vivi lily
6. 怒らないで feat.15MUS
7. Rain feat.18scott
8. Parade feat.SHOHEY from THREE1989
9. Potpourri
10. Infinity feat.BUPPON
11. Still Living feat.MuKuRo
12. Compass feat.CHICO CARLITO
13. Drunk feat.BASI
14. Chilly Source
客演:
BASI
BUPPON
CHICO CARLITO
JIVA Nel MONDO
kiki vivi lily
KOJOE
MuKuRo
SHOHEY from THREE1989
15MUS
18scott
おかもとえみ
サトウユウヤ
(A to Z)
■illmore:Instagram / Twitter / SoundCloud
【イベント情報】

Manhattan Records × Chilly Source Presents “Vibin’Out”
日時:2019年6月21日(金) OPEN 18:00 / START 18:00
会場:東京・渋谷WWW
出演:
DJ HASEBE
AKLO
FNCY
illmore
KOJOE
CHICO CARLITO
SHOHEY from THREE1989
pinoko
ケンチンミン
15MUS
DJ KRO & Chilly Source
……and more!
主催:Manhattan Records / Chilly Source
お問い合わせ:WWW TEL 03-5458-7685 / マンハッタンレコード TEL 03-3477-7166
・チケット
マンハッタン・レコード限定チケット(チケット+DJ KRO MIX CD)
チケットぴあ(Pコード:152-194) ※電話予約あり:0570-02-9999
ローソン・チケット(Lコード:71358) ※電話予約なし
e+