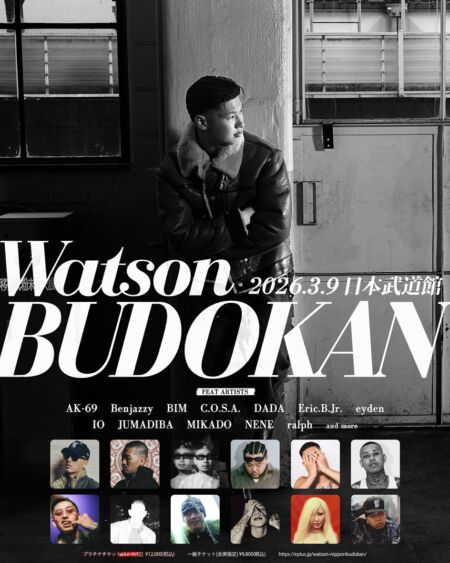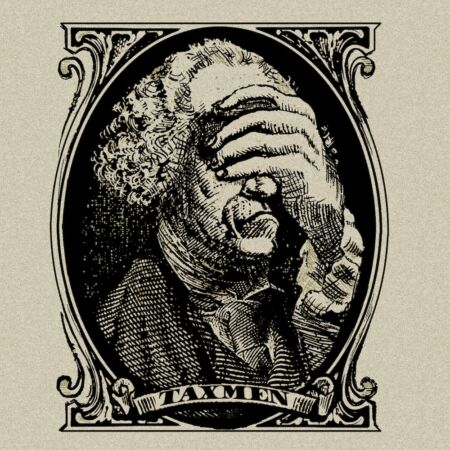痛快なファンクアルバムだ。BREIMENの新作『AVEANTIN』には、暗い時代のムードに抗する溌剌としたダンスの魅力がある。高木祥太が「踊ってなきゃやってられない時代」だと語っている通り、本作に込められているのは、「移ろう時代」を「型のないムーヴで踊り」生き抜くための生命の煌めきなのだろう。
もちろん、前作『FICTION』で設けられていた生楽器縛りや、メンバー以外の音を入れないという制約を解除したことも、本作の開放的な気分と無関係ではないはずだ。間口は広く、それでいて奥には5人の冒険心があり、メンバーをして「ノンジャンルの殴り合い」と語るような活気のある作品になっている。メジャー移籍後初のアルバム『AVEANTIN』について、ざっくばらんに語ってもらった。
Interview & Text by Ryutaro Kuroda
Photo by Tamami Yanase

「ミクロ単位の違和感」──再考するバンドの本質
――『AVEANTIN』、素晴らしいファンクアルバムだと思います。
サトウ:やったー!
高木:僕らもそう思ってまーす!
――改めて、どんな作品になったと思いますか?
高木:でき上がったのが2、3日前なのであまり客観的に見れない部分はあるんですけど、今回は裏テーマとして「踊れる」というのを意識して作りました。1個前の『FICTION』は情念のこもった非常に重みのあるアルバムで、「映画を1本見たようなアルバム」という感想もいただいたり、いい意味で聴き終わった後に疲れるような作品だったんですけど。それに対して『AVEANTIN』はすごく楽しいアルバムになったと思います。
So Kanno:これまでに出した3枚のアルバムで培った技術や気づきが、今回のアルバムに総動員されている気がしますね。ドラムだけを見てもいろんなことをやっていて、生ドラムを叩いている曲もあれば打ち込みだけの曲もあるし、スネアとバスドラとハイハットだけを生で録って、タムの音だけ打ち込みにしたハイブリッドな曲もあるし、いろんなバリエーションのあるおもしろいサウンドになりました。
いけだ:前作の反動がここに全部詰まっている気がします。『FICTION』は生楽器しか使わないとか、いろんな制限があったんですよ。
高木:生楽器縛り、クリックを使わない、デモを作らない、5人の音しか入れないとかね。
いけだ:そういう制約を設けて作ったので、今回はその反動でなんでもあり、ノンジャンルの殴り合いみたいな作品になっていて、その上で一貫してダンスのアルバムでもあるという感じです。
――なるほど。
高木:BREIMENには制約の美学みたいなのがあるんですよね。たとえば1枚目の『TITY』では、“By my side”のギターソロでは1弦が切れてしまったけどそのまま弾いていたり、意図的に制約を設けてやるようにしてたんです。そうやって制約を増やしていった結果、3枚目にして複数の制約を設けた“重いアルバム”ができた。それはそれで満足しているんですけど、今度はそれを一回全部取っ払ってみようかなと思ったのが今作『AVEANTIN』ですね。

――制約を取っ払ってみて、どんな気づきがありましたか?
高木:どんなツールや楽器を使っても自分たちの音になるなって思いました。たとえばアコギとエレキは本来違う楽器だと思うんですけど、どっちの楽器を弾いてもカツシロの音になるし、全然違う音のするベースを弾いても俺の音になるみたいな、そういうのがバンドという単位でできている気がします。
ジョージ:なのですごくミクスチャーというか、ジャンル感がバラバラな作品なんですけど、アルバム通して聴くとちゃんとBREIMENのサウンドとしてまとまっていると思います。
――BREIMENらしさってなんだと思います?
ジョージ:「違和感」じゃないですかね。よく言えば「違和感」だし、悪く言うと「ちょっと気持ち悪い」。
高木:悪く言うな!
ジョージ:(笑)。
So Kanno:でも、祥太の変な声は……。
いけだ:だいぶ特徴だよね。
――高木さんはどこにBREIMENの特徴があると思いますか?
高木:“LUCKY STRIKE”の歌詞でも似たようなことを書いているんですけど、今は技術が発達しすぎて、トリートメントしようと思ったら全部できるじゃないですか。曲もそうだし、ピッチも完璧なものが作れるし、たぶん全部を整えることができる。で、俺はそこに抗いたいというよりは、ちゃんと意識的にそれを使いたいんです。たとえばメロダイン(※1)でも、「ここは使うけどここは使わない」とか、「ここはベースのタイムも直さない」とか、そういうのをどれだけ意識的にやれるかだと思っていて、それによって違和感が生まれてる気がするんですよね。
いけだ:雑味って言うよね。
高木:そう。雑味とか、いなたさとか。昔のファンクなんて、直しがきかない時代だからよく聴くとズレてたりするけど、それをズレとするかグルーヴとするかみたいな話で。僕はテクノロジーをちゃんと意図的に使いたいし、そういうところでミクロ単位の違和感が生まれている気がするんですよね。いきなり違う展開にいくとか、そういうわかりやすい違和感もあるけど、意外とBREIMENの本質はそこなんじゃないかなという気がします。
※1:オーディオ編集ソフトウェア。主にピッチ補正で使用されることが多い。
ストリップで感じた自己の開放、突き破るパワー
――各楽曲についてお聞きしたいと思います。“乱痴気”はどんな風にできていったんですか?
高木:“乱痴気”は曲のテーマと《乱痴気乱乱痴気》という歌詞、あとはベースリフがあって、そこからみんなで作っていきました。で、Bメロは平成感というか、SOUL’d OUTっぽさを意識しましたね。
サトウ:平成いいよね。
高木:今までは近すぎたけど、そろそろ平成をイジってもいいかなって。サビも5通りぐらいコード進行を試したんですけど……途中めっちゃRIP SLYMEっぽくなったよね?
サトウ:というか、今のコード進行がRIP SLYMEの“熱帯夜”と同じだから。
――ジャズファンク風のテイストを感じる“寿限無”は、サックスの音が特にカッコいいです。
ジョージ:“寿限無”はコード進行だけが決まってて、祥太から「俺が寿限無、寿限無って言うから、その後のメロを作って」と言われて。リファレンスはJoshua Redmanというサックスの人の“Jazz Crimes”です。
高木:“Jazz Crimes”って曲には俺らもセッションで出会ってるんですけど、一部の界隈でセッションミームのようにこすられている曲なんですよ。俺の身内でも、あれでくすっとなる人が13人ぐらい思い当たります(笑)。
ジョージ:それで“寿限無”はあの曲の雰囲気を感じつつ、もうちょっとファンクに寄ったメロディが作れたらな、という感じで作っていきました。
――ジョージさんは自分のプレイで気に入ってる曲はありますか?
ジョージ:“ブレイクスルー”ですね。イントロのシンセみたいな音があるんですけど、あそこはサックスで作っていて。というのも、去年末に出たWill Vinsonというアーティストのアルバム(『Trio Grande: Urban Myth』)が衝撃的で、サックスの音をかなり攻めて作られていたんですよね。彼はそもそもめちゃくちゃジャズの人だし、普段はコンテンポラリーなことをやっているのに、そのアルバムでは結構エレクトリックなことをやってたのがすごくカッコよくて。
祥太が上げてきたデモにはシンセの音でイントロが入っていたんですけど、Will Vinsonのアルバムを聴いたこともあって、サックスで似たような感じの音を作れたらおもしろいんじゃないかと思って。自分のエフェクトボードをイジってみたらたまたまあの音が出てきて、そこは結構気に入っています。

――“ブレイクスルー”は曲としても素晴らしいですよね。Curtis Mayfieldの“Move On Up”的な勢いを感じるというか。
高木:おお!
――すごいエネルギーのある曲だと思います。
高木:“ブレイクスルー”は初めてリード曲を作ろうと思って作った曲です。渋谷のホテルを取ってもらって4日間スタジオに籠もったんですけど、最初の3日間は本当になんもできなくて。それで街ブラしたり、初めてストリップショーを観に行ったりして……できました。
――その過程をお聞きしたいです(笑)。
高木:(笑)。でも、本当にこの曲はストリップが効いているんだよね。ストリップってめちゃくちゃカッコよくて、やっぱり自己の解放なんですよ。コロナ禍を経て僕の周りでも会社を辞めたり鬱になった人がいっぱいいて。今の社会にはすごく生きづらいムードが蔓延していると思うんです。俺自身で言えば、結構社会から隔離されて生きてきたタイプなんですけど、ソニーという事務所に入ったことで社会に対峙せざるを得ない場面も増えてきて、病んではないけど頭に膜が張ってる感じがあったんですよね。
そんなことも相まって、ストリップを観たら本当に突き破りまくってるし、パワーがすごくて。そこから「ブレイクスルー」っていう単語が浮かんできて、BREIMENの「ブレイ」にもかかってるし、まあダジャレなんですけど「ブレイクする」にもかかっているし、俺的にその単語でハッとなったところがあって。そこからは爆速でワンコーラスのデモを作って、あとはバンドと一緒に作っていきました。
――最初にダンスアルバムということも言われてましたが、なせ踊れる作品にしようと思ったんですか?
高木:踊ってなきゃやってらんない時代じゃないですか。あと、俺らはバンドのタイプ的に初期衝動というのとはまた違うけど、1枚目の『TITY』にはなんか純真さがあったんですよね。言ってしまえばダンスアルバムみたいなところがあったと思ってて、俺的にはいろんな実験を経たBREIMENで、『TITY』のような真っ直ぐさのあるアルバムを作ろうとしたというか。原点回帰的なところがちょっとあるかもしれないです。
――《変わりたい訳じゃない 殻破りたいだけ》という歌詞が象徴的ですが、高木さん自身、解放感を求めていたところがあるんですか?
高木:俺らの状況をちょっとメタで見てます。BREIMENって(曲は)ずっといいんですけど、世の反応に関しては着実に段々とやってきてたバンドなんですよね。“ブレイクスルー”の歌詞の通りですけど、そろそろもう一段階行きたいとは思っていて。それはメジャーに迎合するとかではなくて、やっぱり長く続けたいバンドだし、長く続けるためには何かしらの下地が必要だから。
僕たちが健康的な状態でクリエイティブを続けるためのパトロンを増やしたいなと思っているんですよね。それだけの魅力があるバンドだと思ってるし、BREIMENは昔から長くファンでいてくれる人が多いんですよね。お客さんを飽きさせない自信があるからこそ、そのためにちょっとだけ裾野を広げないといけないな、という感じですね。
各楽曲のアレンジと、プレイヤーとしてのこだわり
――“魔法がとけるまで”はちょっと80’sっぽいというか、ディスコ感もある曲かなと思います。このテイストはどういう発想から生まれてきたんですか?
サトウ:ストリップ?
高木:ストリップじゃない! ストリップで何曲も書いてない(笑)。
――(笑)。
高木:ぶっちゃけると、これはタイアップ用の曲だったんです。去年の1月に合宿で制作したときに、Soちゃんが病欠したことがあって。でも、納期があったし、ドラムテックのKokichiってやつは来てたので、一旦Kokichiに味のないテンプレみたいなハウス風のビートを作ってもらって。結局タイアップの件は流れてしまって、新たにテーマを設けて作っていったんですけど、その過程でビートは後から生に差し替えようという話もあったんです。でも……結局残ったよね?
So Kanno:残ったというか、そのビートを元にみんながフレーズをつけていったので、そのビート以上のものを俺は作れないなと思ったんですよね。なので俺の体感としては、病気でお休みしている間にいい曲ができてた、という感じでした。
――なるほど。
高木:あと、2枚目(『Play time isn’t over』)からずっと佐々木優というエンジニアにやってもらっているんですけど、今回は新たにもう2人エンジニアを入れていて。“魔法がとけるまで”は、コロンビア出身のアレックスというエンジニアと一緒に作ったんですよね。彼はめちゃくちゃ現代的なトラックメーカーというか。
So Kanno:いわゆる現代の洋楽の打ち込み音楽のノウハウを持っている人ですね。
高木:全然発想や方法論が違うからおもしろかったです。ソフト内の新しいシンセを使ったりして、結果どんどん踊らせる方向に行きました。俺はBREIMENの曲って大きく分けたら5パターンぐらいに分類できると思っていて、そのひとつに「4つ打ちダンストラック」みたいのものがあるんですけど。たとえば『FICTION』だったら“チャプター”で、『Play time isn’t over』だったら“ツモリツモルラバー”とか。
いけだ:“魔法がとけるまで”は、その世界線を刷新した曲ですね。
――いけださんはご自身の鍵盤で、特に納得のいく曲を選ぶとしたらどれになると思いますか?
いけだ:“ラブコメディ”です。今回のアルバムでは生のピアノからエレピ、シンセサイザー、打ち込みなど色々使っているんですけど、実機のクラビネットを使う機会にも恵まれまして。たとえば“LUCKY STRIKE”でも実機のクラビを歪ませて、フィルターをかけて「みゃんみゃんみゃん」という音を出しているんですけど、“ラブコメディ”ではStevie Wonderの「Superstition」に則って、クラビを3つくらい重ねて録りました。なのでこの曲では生の豊純な響きのクラビが重なっているんですよね。これをやるバンド、最近ではなかなかいないんじゃないかなと思います。
高木:シンセとかのエレピ類って、全部パソコンで作れちゃうからね。
いけだ:一応ソフト音源も試してみたんですけど、弦を引いたときの空気を含んでるような音が全然違くて。“ラブコメディ”にはそこでしか出せないような音を詰め込められたので、そこはぜひ聴いていただきたいですね。

――『AVEANTIN』の中でもキュートな魅力がある曲だと思います。
いけだ:かわいい感じですね。
――ゴスペルっぽいコーラスも楽曲をよく彩っています。
高木:これはヴァイブスとしては『天使にラブ・ソングを…』(1992年/原題:Sister Act)です。ゴスペルクワイヤを入れたいという気持ちはずっとあったんですけど、R&Bやゴスペルフィールなグルーヴにクワイヤを入れると割と安直な感じになっちゃうんで、これまではちょっと敬遠してたんです。でも、“ラブコメディ”というタイトルや、この曲の持ってる温かさとかハッピーな感じにはそぐうなと思って。それで今回満を辞してコーラスの方をお呼びしてやっていただきました。
――サトウさんはご自身のギターに関して、どんな手応えを持っていますか?
サトウ:俺の考えるギターのフレーズって、めっちゃキャッチーだなと再認識しました。別にポップじゃないんですけど、変にキャッチーなんですよね。
たとえば“ラブコメディ”のリフも、音色を含めてちょっと馬鹿っぽいじゃないですか。“魔法がとけるまで”のサビでも、後ろの方でEDMのサイレンっぽく鳴っている音があるんですけど、あそこはシンセじゃなくてギターを弾いているんですよね。大好きなJeff Beckが亡くなったとき、彼みたいなおもしろいことをやりたいと思って弾いたフレーズなんです。

高木:確かに! 言われてみるとあれ、めっちゃJeff Beckだね。
サトウ:あと、個人的に1番染みるのは、“眼差し”のサビの裏で鳴っているバッキングしてるギターです。なんかこう、ほっこりするんですよね。ギターソロをやってる“LUCKY STRIKE”とかもいいんすけど、今回はああいう感じの方が気に入ってる。
高木:わかる。
いけだ:各楽曲のアレンジが光るアルバムだよね。
高木:ある意味、今までのアルバムで1番手を抜いてる部分もあって。録ったギターをそのままコピペしたり、「その方がいい」って判断したら何のためらいもなくそういう編集をしました。
サトウ:“yonaki”なんてもう、俺は最初の方しかギター弾いてないもんね。でき上がってく中で、「そういえばこんなギター録ってたよね?」って引っ張り出してきた素材を貼りつけて、転調したらピッチを変えて対応させて。でも、“yonaki”ってめっちゃ音いいんですよ。
高木:音いいね。グルーヴを感じるズレの部分と、トラックメイク的なループ感の両方がある。それは“魔法がとけるまで”もそうだし、たぶんそういうループ感が合う曲っていうのは今までにない選択肢だったと思う。
――Kannoさんがドラムのプレイで気に入ってる曲はなんですか。
So Kanno:気に入ってるとかではないんですけど。
高木:いや気に入れよ(笑)。
So Kanno:(笑)。今回全面に押し出していきたいのは“LUCKY STRIKE”です。この曲ではツインドラムをやってるので、おもしろいことができたなと思います。
高木:これはマジで新しいよね。“LUCKY STRIKE”の音像は、たぶんBREIMENの中でも完全に初めての感じがある。
So Kanno:ツインドラムのアイデアは以前からちょくちょく話してて、元ネタを言えばThe RH Factorがツインドラムでレコーディングしていたことでした。RH Factorの目的としては、ふたりのドラマーを呼んで一緒に叩かせることで、お互いのドラムを聴き合って走ったり遅くなったりしないような引力が生まれると。

――なるほど。
So Kanno:それによって重たくはないけどずっしりとしたビートができるという、そういう狙いがあったみたいなんです。“LUCKY STRIKE”ではツインドラムの両方を自分が叩いているので、Royがやった本来の意図とは違うんですけど、サウンド的な部分を真似したいと思ってやってみました。LとRから違うドラムが聴こえてくるように振ってあるので、聴いたときにちょっと違和感があると思います。
高木:現代の音楽ではドラムは基本的に真ん中に配置するじゃないですか。でも、“LUCKY STRIKE”では2つのドラムをはっきりと左右に振っていて。昔のカップルみたいにイヤホンを分けて聴いたら、それぞれ聴こえてくるドラムが違うんです。ベースもシンセベースとベースで分かれているし、ギターとクラビも全部左右に分けているので、真ん中にすごいスペースがあるんですよね。
――そうした斬新なサウンドデザインを施した曲に、《オレは死んでもタバコをやめないゾ》と歌おうと思った理由はなんですか?
高木:元々はおっきいファンクの曲、テンポがゆったりとした音の世界観の広いファンクの曲を作りたいと思っていました。で、それとは別に俺は昔からタバコの曲を書きたいと思っていて、それが合わさった結果ですね。
だからこのサウンドで歌ったことに意図はないですけど、歌詞はトラックができてからだんだんと付け足すように書いていったので、ビートがおっきくなったから気も大きくなったのかな。「ひっそりと喫煙所でタバコを吸っています」というような歌詞ではなく、「俺は絶対タバコやめねえぞ」って歌っているのは、もしかしたらこのドラムのせいかもしれないですね。
バンドだからこそ生まれる有機的な反応
――“眼差し”も本当に素晴らしい曲だと思います。
高木:“眼差し”を書いたのは、去年のサマソニ大阪に出た頃ですね。そのときはずっと曲が書けなくて、サマソニの後そのまま大阪でスタジオをやっている友だちのところに2泊3日ぐらいで泊まりに行ったんです。そこで制作する日を作ったんですけど、色々なデータフォルダを見ているうちに、俺本当に泣きながら作ってて。
ジョージ:そのスタジオが寺なんですよね。
高木:そう。お寺の蔵をスタジオに改造してるようなとこで。
ジョージ:それでほっこりするというかね。
高木:浄化されるというか、そういう「気」はあったよね。
――それってTAMIWのメンバーさんが運営されているスタジオですか?
高木:そうです。TAMIちゃんのスタジオです。そこでママの曲を作ろうと思いました。2番の歌詞の《色味のない弁当 薄めの味付け 何故か恥ずかしくって隠して食べた》というところとか、めちゃくちゃ個人的な思い出です。
――母への無垢な眼差しを、こんなに素直な言葉で書いてるのがすごいと思いました。
高木:押見修造の『血の轍』という漫画があって、ちょうどその時期に完結した作品なんですけど、それは母との思い出のもっとグロテスクな部分、言ってしまえば(“眼差し”とは)全く逆サイドの部分を書いてる漫画なんですけど……なんて言うんだろうな、(子供の頃って)母親を馬鹿にされるのが1番キツくなかったですか?
――すごくわかります。
高木:あの気持ちって、その時期特有のものだなって思うんです。たとえば今でも母親を馬鹿にされたら怒ると思うんですけど、あの頃は自分と母親に明確な境界線がない時期だから、もっと根深い感情なんですよね。かと言って母親の自慢もできないし、母親に対しての苛立ちもある、みたいな。俺は押見さんの漫画ほどではないにしろ、ちょっとその感情を入れたいなと思って2番の歌詞に書いたところはありましたね。
――そして最後の“L・G・O”ですが、この曲は本作でも唯一メロウな音色で、侘しさを感じる曲になっています。
高木:まあ、歳を取ったよね、というところじゃないですかね。当たり前だと思っていたことがいつの間にかなくなったりすることっていっぱいあるし、日常すぎて思い出せもしないようなこともいっぱいあって。そういうことが年を重ねるごとに増えていく。この曲の歌詞はなるべく添削しないで、一筆書きみたいに書きました。1番素で書いた曲ですね。
――素の言葉に対してこのサウンドというのは、何か必然性を感じますか?
高木:俺はシンガーソングライターではないと思ってるんです。やっぱりBREIMENというバンドで曲を書いているから、みんなと共有していく中で変わっていく部分がいっぱいあるんですよね。“L・G・O”はデモの印象は全体的にもっと無機質な感じだったんですけど、Soちゃんがドラムをもっと生っぽくしたいと言ってきて。それからマネージャーのジュンペイってやつのお父さんがサンバをやっているんですけど、そのサンバの楽器を借りて太鼓の音を入れたり、ギターも最初はアコギで弾いていたんですけど、うちのお父さんの12弦を借りてカツシロか弾いたりしてて。なんか図らずしてお父さん曲になっているんですけど(笑)、そうやって制作の中で変わっていくんですよね。
――なるほど。
高木:今回のアルバムで思ったのは、デモを作るとワンクッション考える時間があるってことで。俺が手紙のようにみんなに渡したデモをそれぞれ読んで、まあ読まない人もいますけど(笑)、各々の解釈で受け取ることで厚みが生まれるんですよね。
「5人が楽しくないとダメだと思う」――予測できないバンドの未来について
――このアルバムをリリースした後、どういう活動したいと思っていますか。
一同:……。
高木:そんな考える?(笑)。
ジョージ:あんまり先を考えて生きてないから。昔はそういう考え方もあった気がするんですけど。
高木:絶対思った通りに行かないもんな。
ジョージ:そう。BREIMENをやり始めてからは、先を予想して生きるのって本当に無意味だなって思うようになりました。
高木:メンバーも変わってるしね。バンドって社会の縮図でもあると思うし、ひとりの事情だけでは進んでいかないから。たとえば一昨年初めてのフジロックだったんだけど、だーいけがコロナになって出られないってなって、結果TENDREに鍵盤を弾いてもらったんですけど、うちらってそういうことばっかりなんですよ。そしてそれを割と楽しんでやれてるから、たぶん先のことを考えるのは無意味だなって思ってますね。
サトウ:まあ5人が満場一致で楽しいと思うことで、やりたくないことはないから。そこだけかな。楽しいことをやりたいです。さっきの撮影で俺が虫探そうぜって言ったら、だーいけが「大人になったら虫探すこともないっすもんね」みたいなことを言ってて。そういうことかなと思った。
――童心に戻れるということですか?
サトウ:それともまた違うんですけど。
高木:わかるよ。
――いけださんはどうですか?
いけだ:僕としては関わってくれるチームが増えたわけなので、そいつら全員幸せにならないといけないという使命は感じてます。僕らの活動を通して、とりあえず関わってくれてるチーム全員がプラスになるような1年になればいいかな。
高木:そのためには俺たち5人が楽しくないとダメだと思う。
いけだ:もちろんそうですね。
サトウ:だから虫探しに行こうぜっていう。
いけだ:結構ありだねそれ。
高木:2024年は虫を探しに行こうと思います(笑)。
【プレゼント企画】
SpincoasterのX(ex. Twitter)アカウントをフォロー & 下記投稿をリポストでBREIMENのサイン入りチェキを3名様にプレゼント。発表通知はXのDMにて行わせていただきます。
キャンペーン期間:4月9日(火)19:00〜4月16日(火)19:00
【プレゼント企画】
BREIMENのインタビューを記念し、サイン入りチェキを3名様にプレゼント‼️
応募方法は当アカウントをフォロー&このツイートをRTするだけ✍️
期間は〜4月16日(火)19時まで。注意事項など詳細はこちらより👀https://t.co/dDxREVs1L3 pic.twitter.com/vQhEbcAGIw
— Spincoaster/スピンコースター (@Spincoaster_2nd) April 9, 2024
※3枚の中からランダムでの発送となります。
※当選のお知らせに対して48時間以内に返信がない場合、誠に勝手ながら辞退とさせていただきます。
※住所の送付が可能な方のみご応募下さい。頂いた個人情報はプレゼントの発送以外には使用いたしません。
※発送先は国内のみとさせていただきます。
※フリマサイトなどでの転売は固く禁じます
【リリース情報】


BREIMEN 『AVEANTIN』
Release Date:2024.04.03 (Wed.)
Label:Ariola Japan
[初回生産限定盤] BVCL-1370~1 ¥5,980 (tax in)
[通常盤] BVCL-1372 ¥2,980 (tax in)
Tracklist:
1. a veantin
2. ブレイクスルー
3. 乱痴気
4. ラブコメディ
5. 眼差し
6. LUCKY STRIKE
7. T・P・P feat.Pecori
8. 寿限無
9. 魔法がとけるまで
10. yonaki
11. L・G・O
※Blu-ray(初回生産限定盤のみ):BREIMEN ONEMAN TOUR『COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023』東京公演ライブ映像、LA滞在ドキュメンタリー収録
【イベント情報】
『BREIMEN MAJOR 1st ONEMAN TOUR』
2024年4月19日(金) at 東京 人見記念講堂
2024年4月26日(金) at 北海道・札幌 sound lab mole
2024年5月10日(金) at 宮城・仙台 Rensa
2024年5月18日(土) at 大阪 なんばHatch
2024年5月24日(金) at 石川・金沢 AZ
2024年5月31日(金) at 福岡 BEAT STATION
2024年6月1日(土) at 広島 LIVE VANQUISH
2024年6月7日(金) at 愛知・名古屋 ボトムライン
料金:
[東京公演]
一般 ¥6,000 / 学割 ¥4,500 (各1D代別途)
[その他公演]
一般 ¥5,000 / 学割 ¥3,500 (各1D代別途)
※学割は小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。
※予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります
※学割チケットは上限に達し次第終了となります
※会場で学生証の提示が必要となります