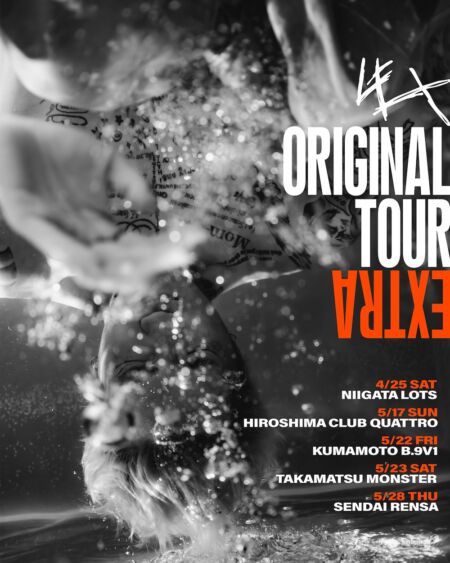愛知出身のSSW、碧海祐人が1stアルバム『表象の庭』を12月22日(水)にリリースした。
昨年〈ULTRA-VYBE〉が立ち上げた新プロジェクト『S.W.I.M.』にも参加し、9月には1st EP『逃避行の窓』をリリースした碧海祐人。そのミニマルかつメロウなトラックや、独特の言語感覚を有するリリック、そしてヒップホップやR&Bの影響も感じさせる今日的なフロウはシーンにおいても異質な存在感を放っている。
ドラマーの石若駿や注目のシンガー・さらさも参加し、エンジニアの葛西敏彦が共同プロデュースで参加した今作は、そんな音楽性をより深化/洗練させたような、ウェルメイドな作品だ。どこを切り取っても“碧海祐人”な記名性の高さ、オリジナリティも湛えているが、それと同時にどこか懐かしい、不思議な感覚も想起させる。
今回はそんな碧海祐人にインタビュー。今作の制作背景やコンセプトについて、そして前作リリース以降に起こった変化など、話題は多岐にわたった。(編集部)
Interview & Text by Reina Murakami
Photo by fukumaru

「各々の曲が各々の向きたい方を向いている」
――まずは『表象の庭』というアルバム名やコンセプトができた経緯をお伺いしてもいいですか?
碧海:結構ぼんやりとしているんですけど。以前、兄の友人に「無意識に自分が出してしまう言葉はとても大事な言葉だ」と言われたんです。僕は曲を作るときに“忘れる”っていう言葉がすごく出てくるんですけど、そのときに記憶とか表象みたいなことって大事なものなのかなっていうのが念頭にあって。その頃に村上春樹さんの『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読んだんです。その中に夢の中の世界がでてくるんですけど、内と外があって、それでいてすごく自分と近いみたいな、そういうものを作りたいなと思ったのが最初かなと思います。
そこからいろんなものを見たり聴いたり作ったりする中で、少しずつ質が変わっていってコンセプトに辿り着いたのかなって感じがします。
――“忘れる”という行為は過去の記憶だったり過去のものと結びついていると思うんですけど、そういったご自身の過去の記憶を歌詞にすることが多いんですか?
碧海:そうですね。僕の言葉ってすごくわかりづらいと解釈されることが多いんですけど、自分が生きてきた中で経験したこととか、味わったことのある感情を元にして歌詞を書いていて。確かにわかりやすく書いているつもりはないけれど、僕としては全部心当たりがあるんです。だから過去を元にしているというか、経験の上にちゃんとある言葉を歌詞にしていますね。
――今回のアルバムは全体的にボーカルやコーラスはもちろん、それぞれの楽器も含めて響きの柔らかさ、豊かさを感じました。そういう空気感は意識していましたか?
碧海:それはどちらかというと、僕が作りたかった空気感をミックス・エンジニアの葛西さんが的確に、そしてときには僕が意図してない形で付与してくれたものです。葛西さんは今回ミックス・エンジニア兼共同プロデューサーっていう形でクレジットさせてもらったんですけど、僕以上に楽曲に対して迫ってくれるというか。ときにそれは僕が思っていたのと違うこともあるんですけど、そうやって内と外から輪郭線を綺麗に定めていった感じがあって。なので音の空気感などは葛西さんの力が大きいと思いますね。
――葛西さんとの共同作業で、特に印象深かったことはありますか?
碧海:1st EPの『逃避行の窓』のときは「こういうものが作りたい」というものが溢れ返っていたときだったので、僕が好きなものを意識して作っていたんです。それもあって、今回のアルバムは作り始めた段階で「こういう展開にしたら僕が好きなものになる」っていうのがある程度掴めた気がしていて。そんな矢先に、葛西さんに「好きなものといいものは違う」と言われたんです。僕は好きなものをただひたすらに作っていればいいっていう発想でこれまでやってきたけど、その曲が正しく響くためにはとか、コンセプトにとってよいかどうかは別っていう。なのでそれからは僕の好みは置いておいて、その楽曲が持つ意思みたいなのをすごく意識するようになったんです。
碧海:だから、今回のアルバムは各々の曲が各々の向きたい方を向いていると思うんですよ。それが葛西さんとやったときに一番印象深い体験でした。最近は友達と曲を作ったりすることもあるんですけど、「こっちとこっちの音、どっちがいい?」とかっていう話になって、「こっちがいい、俺が好きじゃないから」みたいな選び方もするようになって。好きじゃないものを選ぶことが楽曲の方向に合っていることもあるっていうのはすごく得難いというか、これまで全くしなかったことでしたね。
――曲ごとに違う方向を向いているっていうのはアルバムを聴いていて感じたことでもありました。そういう体験をしながら作っていって、最初に想定していた完成形とはかなり異なった曲もあったんですか?
碧海:そうですね。全然違うものばかりです。

コロナ禍を経て揺らいだ価値観、考え方
――1曲目の「熱」はボコーダーを使用しているんですね。ボーカルを言葉を発するものとしてじゃなくて、ひとつの音として扱っているという印象がありました。
碧海:ボコーダーとボーカル・シンセを使って、半分遊びというか、あのエフェクトにしか出せない極めつけみたいなことをやろうと思ったんです。僕は元々声をひとつのトラックとしか思っていない節があるんですよね。もちろんあえてそうじゃなくしているものもあるんですけど。この曲はこれまでやってこなかったことをしようと思ってて、切って貼ってするような作り方を遊びながらやっていました。
――「夜風」は曲の構成がポップスっぽいと感じたんですけど、これは意識的にそうしたんでしょうか。
碧海:これは意識的です。あざといもの作ってやろうと思って(笑)。でもそこで拍子抜けにならないように、いろんな背景との繋がりを持たせたまま、展開はすごくポップにっていうのを狙って作りました。
――1曲目から通して聴くと余計にそれがわかります。他のポップスの曲に続けて聴くと目立たないであろう構成が、この流れだと目立つのがおもしろいなと。3曲目は「不揃い」という曲名が気になりました。碧海さんの曲の名前は自然のものだとか情景が多いと思うんですけど、「不揃い」というタイトルには特別な理由があったんですか?
碧海:この曲はデモの時点で「不揃い」という名前で。なんで付けたのかわかんないんですけど、楽曲から受ける印象が完全に「不揃い」だって思ったんです。「不揃い」の漢字とひらがなの並びの印象が完璧に合致していて。歌詞を何回か書き換えているんですけど、それでもずっと「不揃い」だったので、そこから変わることはなかったんだろうなと必然性みたいなものを感じています。
――曲名ってそういった印象から付けたりすることが多いんですか?
碧海:そうですね。タイトルから膨らませていくときもありますし、後で見つけ出すみたいなときもあります。今回だと「空白む」は結構見つけ出した感じですね。あと「馨り」も探しました。
――探したっていうのは中々決まらなくてということですか?
碧海:そうですね。「馨り」は4回くらいタイトルが変わっています。未だにタイトルがわからなくなるときがあって。

――先ほど曲の空気感とか響きが豊かなものが多いという話をしましたけど、「馨り」の響きは逆に自然な部屋っていう感じがあって。それぞれの楽器が演奏している情景がすごく伝わってきたんです。この曲は意図的にそういう空気感を目指しているのかなとも思ったんですが、いかがでしょう。
碧海:僕が当初狙っていた通りの感じ方をしてくださっていて嬉しいです。「馨り」は言葉が入ってこないようにしてて、その曲を聴いたあとに何も残らないというか、どの演奏もこれが主役っていうものがいないみたいなものを目指して作っているんです。各々の演奏とか録り音の処理の仕方を葛西さんにこういう風に聴こえるようにお願いしますってお願いして、空気がそのまま伝わってくるのを目指しましたね。
――聴いたあとに何も残らないようなものを目指したのはどうしてですか?
碧海:この曲で表したかったものが、コロナ禍に入ってからの空気だったんです。ただ、それは「僕はこう思います」とか「コロナ禍だけどこういう風に頑張ろう」というものではなくて、聴いて、少しだけいい風が吹いてくれた、みたいな。何にも残ってないけど少し変わったっていうものを作れたらおもしろいなと思って。だから「馨り」というタイトルには「香り」や「薫り」ではなく難しい漢字を使ってるんですけど、これは“遠くまでいい香りが広がる”や“いい結果”という意味を持つ漢字をあえて使っているんです。
――コロナ禍を経たことによって楽曲に反映されている部分などは他にもあったりしますか?
碧海:このアルバムの発端というか背景的な話になってくるんですけど、今年の4月くらいからコロナによって価値観とか考え方が大きく揺らいだ気がしていて。色んな人が自分に対する不安を感じていて、その不安に対して少しずつ歩みだしたというか。「私はこうだ」っていう価値観を色んな人が生み出してそれがぶつかり始めたりした時期に、自分がよくわからなくなったんですよね。
春から一人暮らしを始めたんですけど、ひとりでいる時間が増えて考える機会も多くなって、本当に自由になった分制御するものが何もないから、自分が何かを考え出したり不安になったときに、元の生活に戻す術がないっていう状態になったんです。色々悩んで苦しいなっていうときにいろんなものが信じれなくなって、そのときに残ったものが自分の経験と記憶だけだったんですね。それで改めて、自分って曲の中でたくさん「記憶」って言ってるなということに気付いて。コロナ禍というかその後の話ですけど、そういう側面はすごくあると思います。
――なるほど。4曲目の「顰蹙」は軽快でそれまでの曲とはかなり趣向が違うなと感じました。
碧海:これはそうですね。先ほどお話ししたような好き嫌いっていう話を置いておいて、作りたいものを作るかっていうモードに入ったときがあって。そのときにできたのが「顰蹙」ですね。この曲は言葉もそうですし、プレイヤーも各々が好き勝手やってるんですよ。好き勝手やりながら空虚なものに対して悪態をつきましょうっていう大会みたいな。
最初はこういうお洒落な曲がアルバムに1曲、2分くらい入っててもおもしろいよねっていう感じでできたんですけど、それが好きな曲作るかっていうフェーズに入ったときに化けました。自分でも聴くとテンション上がりますね。好き勝手やっていいよっていう空間になったのかなと思います。
過去と今、ふたりの自分による往復書簡
――8曲目の「往復書簡」は唯一のインタールードです。
碧海:アルバムをちゃんと説明している曲が意外にないなと思って作りました。僕は元々インタールードを作るのが好きなんですけど、このアルバムを端的に音だけで説明するために必要な要素を汲み取って並べたというか。一番アルバムのコンセプトに近い曲だと思っています。
――どうしてアルバムの説明が「往復書簡」という4文字に委ねられたんでしょう。
碧海:アルバムのキーワードである「表象」っていう言葉が生まれたときに、表象がどういう形をしているかっていうのがすごく気になっていて。表象って、過去の記憶と今の自分との関わりだとか、今の自分が過去の記憶をただ見ているんじゃなくて、記憶を思い出すときに自分に起こる変化だとか、そういう側面も含んだ言葉なんです。それってどういう形なんだろうっていうことをすごく悩んでいて、対面していない、吟味された対話のようなものだなと思ったんです。時間も空間も違うところにいる過去の自分と、それに対して今いる自分、そのふたりが手紙のやり取りをしているみたいな。そういう意味で「往復書簡」ですね。僕なりの表象の形なのかなと感じたので、そのままタイトルにしました。
――この曲を聴いて、言葉がないからこそ景色を想起させる力ってすごいあるなと感じて。アルバムに11曲ある中で、一番視覚として情景が浮かんだのがこの曲のような気もしたんです。言葉以外の表現の力を感じました。
碧海:ありがとうございます。でも、だからこそ言葉って危険だなって思いましたね。
――「天象」ではさらささんが参加しています。さらささんを迎えることが決まっている状態で曲を書いたんですか?
碧海:いや、最初はそうじゃなくて。元々は僕がこれまでにやったことのない作り方で作ってみたいなって思ったんです。「天象」は以前の2枚のEPとは“ここを見てください”っていうポイントが全く違うんですよ。これまで僕が作ったものって複合的というか、「この面とこの面を見るとおもしろいでしょ」っていう見せ方だったんですけど、「天象」は全部見なくていいからここだけ見てっていう。それで「この部分の質がものすごくいいでしょ」っていう見せ方をしていこうと思ったんです。
でも、自分で歌を入れてもしっくりこなくて。これはだめだなって思ってたら「女性の声を入れませんか」とスタッフさんが言ってくれて、じゃあ入れるかと。仮歌をさらさちゃんに入れてもらったタイミングで“できたな”って思いました。さらさちゃんがいないと「天象」は世に出てなかったと思います。
――さらささんが最後のピースをはめてくれたというか。
碧海:そうですね。最後のピースであり全部でもあるみたいな。
――最後の「氷雨」は終わり方が不思議ですね。
碧海:「氷雨」はアルバムの最後の曲としてちゃんと作ったんですけど、締まらないって思ったんですよ。何も解決していなくて。なんだろうな……何か飛び立っていくんですよね。飛び立っていって終わったときに何も残ってなかったってなっちゃったので、最後の部分を付け足しました。
――歌詞を見ると、ほとんどの行が“て”か“に”で終わってるっていうのが音の響きとしてまとまりがある作りになっていると思ったんですよね。そこもなにか意図があるのかなと思ったんですが。
碧海:それは気付かなかった。
――そうだったんですね。
碧海:おもしろいですね。全然意識してなかったです。でも、それかもしれないですね、最初に思った“飛んでいった感”。文節が終わってないってことかもしれないですね。ちょっと納得しました。

音楽は“小さなきっかけ”であり“誰かにとっての逃げ場”
――おもしろいですね。今後の動きですが、2月には初のワンマン・ライブが予定されてるんですよね。
碧海:そうですね。おもしろいことができたらなと思っています。僕がやれることというか、やりたいことをあくまでアルバム・コンセプトから外れない範囲で色々やってやろうと勝手に思っています。まだ準備段階なんですけど。
――アルバム・リリースがあって来年にはワンマンがあってという今年から来年の動きになると思うんですが、来年やそれ以降、音楽を通してどういうことをしていきたいかという展望などはありますか?
碧海:音楽を通して僕は「みんな、音楽いいよ」って言いたくて。音楽って楽しいじゃないですか。さっき言葉が危険っていう話もあったように、言葉によってすごくわかりやすいものが生まれていって、「それって本当に音楽である必要はあるのか?」って問うことも僕の中で少しずつ増えていったんです。
でも。それは決して消極的な気持ちではないんですよね。もっとおもしろいものが世界中に“音楽”という形を成して転がっていて、僕はそれを食いつまんでアルバムの中にもリファレンスみたいな、こういう形を成したいっていう形で取り入れたりして。「この人、こういうの聴くんだ」って思ってもらえたらおもしろいし、「こういうところのこういう部分を活かしてるんだ」みたいなことを知るのもおもしろい。もっと音楽に興味を持って頂けるように、僕はインディとJ-POPの窓口であれたらっていうのはずっと思っていることですね。そのためにどうするか、みたいなことは具体的には難しいなと思っているんですけど。でも、楽しんでやれたらなと。
――以前のインタビューで「自分の音楽は『逃避行の窓』であり続けたい」とおっしゃっていましたが、その考えは今も変わらず?
碧海:そうですね。先ほどの「馨り」の話に繋がるかもしれないんですけど、僕はものすごく音楽が好きだとは思うんですけど、期待はそんなにしていなくて。例えば音楽を聴くことによって世界が変わるとか、ものすごい大きなことができるとは思っていないんです。例えが変ですけど、せいぜい奥歯の向きをちょっと変えるみたいな(笑)、噛み合わせがちょっとよくなるくらいの本当に小さなことなんだけど、実はそれによって本人が大きく変わっていた、みたいな。そういう小さなきっかけみたいなものでしかないと思っていて。それは誰かにとっての逃げ場であって、直接的な手段ではないけど少し変えられたらいいなっていうような意味で、『逃避行の窓』でありたい。そういう感覚はずっと持っていますね。そういう聴かれ方をしていたいし、そうあるべきじゃないかなと思っています。

【リリース情報】

碧海祐人 『表象の庭で』
Release Date:2021.12.22 (Wed.)
Label:ULTRA-VYBE, INC.
Tracklist:
01. 熱
02. 夜風
03. 不揃い
04. 顰蹙
05. 午睡
06. 沈む春
07. 馨り
08. 往復書簡-interlude-
09. 空白む
10. 天象 (feat.さらさ)
11. 氷雨
【イベント情報】
碧海祐人 ONE-MAN LIVE『窓下に氷雨、箱庭の熱』
日時:2022年2月11日(金・祝) OPEN 16:30 / START 17:00
会場:東京・新代田FEVER
料金:ADV. ¥3,000 (1D代別途)
出演:
碧海祐人
・先着チケット
オフィシャル2次先行(ローチケ):12月22日(水)12:00〜1月10日(月・祝)23:00