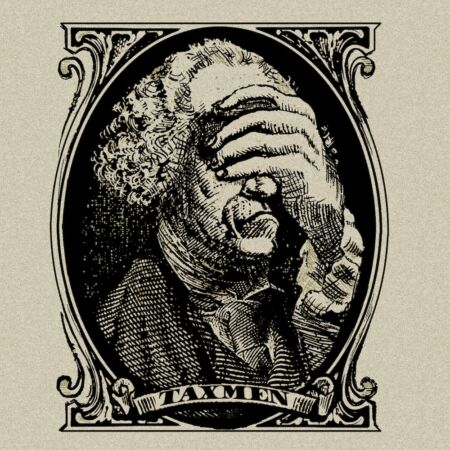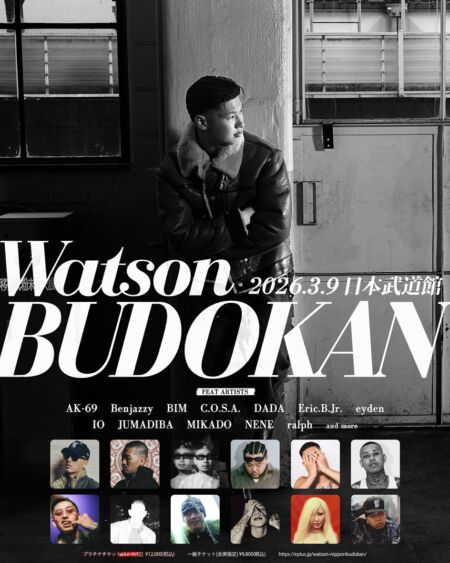12月25日(金)、キミノオルフェが新EP『Then, the Curtains Open』をリリースした。
リリース当日、なんと、インドのiTunes J-POPアルバムチャートでTWICEやReolなどをおさえて突如1位にランクイン。これまでは「言葉」「歌詞」を最重要視していたキミノオルフェだが、本作では、プロデューサー/コンポーザー・EXPCTRによるサウンド・プロデュースのもと「音」に重きを置いた楽曲作りへとシフト・チェンジしたゆえに、言語の壁を越えて音楽が持つ力が遠い国に住む人たちの心を揺らした結果だとも言えるだろう。
本人いわく「右脳音楽」(=右脳から生み出して、右脳を刺激する音楽のことだそう)は、新型コロナウイルスがアーティストたちの精神をも襲う中、どのようにして作り上げられたのか。さらに、サウンドを重視しながらも歌の中で色濃く表現されているキミノオルフェの哲学、スガシカオにもらった言葉から広がっていった「自由」な歌の作り方や生活について、キミノオルフェ・蟻にたっぷりと話をしてもらった。
Interview & Text by Yukako Yajima
Assistant:Ai Kumagai
Photo by 遥南碧

リリースするのがちょっと怖い
――バンド(蟲ふるう夜に)時代からずっと「言葉」「歌詞」を大事にされてきて、今は作詞の講師もやられている蟻さんですが、新作『Then, the Curtains Open』はサウンドを重視した曲作りになっています。まず、そういった作り方へと方向転換したのはなぜかを話していただけますか。
蟻:自分が「右脳音楽」を作ったらどんなことになるのかなっていう興味ですよね。Spincoaster(Music Bar)にいる時間が増えて、世界には自分の知らない素晴らしい音楽がいっぱいあるんだなって単純に思ったので、今まで避けてきたものを避けないと決めることで不自由さを取っ払おうとしたのかな。
――「右脳音楽」とは、理屈とかではなく感覚で音楽を作って、音に合わせて自然と身体が動くような音楽だって、前の対談でも話していましたよね。
蟻:好きな人に好きって言いたい時、いろんな言葉とか仕草を使うじゃないですか。今までの自分の曲は言葉が強かったし、オブラートに包んだ詞は書かないって決めながらも、ひねくれてたから(笑)、「絶対好きとは言わない!」みたいな印象だったんですよ。
今回は、聴く人の耳を無理やりこっちに向けるんじゃなくて、その人に寄り添う形の音楽を作ってみようかなと。歌詞の書き方もかなり変えました。
――そうですよね。EXPCTRが作るメロディは決して日本語を乗せやすいものではないと思いますし、いろんな工夫や苦労があっただろうなと。
蟻:EXPCTRから送られてくるデモは、彼が作ったメロディ・ラインに、彼の独特な言葉の使い方――英語みたいなんだけど、宇宙語みたいな感じ(笑)――を彼の声で歌ったものが乗っていて、そこから実際に私がどう歌詞を当てるかという作り方だったんです。前にChocoholicちゃんたちともこういった作り方をやったんですけど、その時もかなり苦戦して、「自分には合わないな、難しいな」って思っていたんですよね。でも、難しいからって後回しにしてたらダメだなと思って(笑)。今回は「ふたりで」以外はEXPCTRがメロディを作って、ほぼほぼ曲先ですね。
作編曲にChocoholicが参加した「君が息を吸い僕がそれを吐いて廻せこの星を」MV
――しかも今までの曲は言葉数が多かったのに対して、今作ではかなり削ぎ落とされていて。言葉数を少なくすると、自分の考えや生き様の表現が歌の中で薄まる可能性もあっただろうけど、決してそうはなってないのが、さすが作詞の先生もやられている蟻さんのすごさだなと思いました。その辺りは、どういったことを意識されていましたか?
蟻:とにかく自由を意識してましたね。メロディが先に決まってる分だけすでに縛りがあるから、その中でさらに自分自身が縛りのある人間だと、めちゃめちゃつまらなくなるなと思って。自分の生活から自由でいようと思って、生活から変えましたね。
――例えばどんな風に?
蟻:駅のホームで爪を切ってるおじさんがいたから、真似してみたりとか(笑)。駅のホームで爪切るって、どんな気分なんだろうと思って。緑道の脇にある小さいベンチで寝てみるとか。あと、KALDIでコーヒー豆を全種類ちょっとずつ買うとか(笑)。プチやってみたいこと、でも「面倒臭いから」とか「他の人が見てるから」とかの理由でやってこなかったことをやっていく。小さな制限を外していく。そういうことをやってたかな。あと、最近は白を着てます。

――今日もですね。それはなぜ?
蟻:下北沢MOSAiCという、バンド時代にすごくお世話になったライブハウスがあるんですけど、そこは壁とか地面が真っ白で。昔、店長に、「なんで白なんですか?」って聞いたら、「アーティスト色に染めて欲しいから」と言ってて、いいなあと思ったんですよね。それで最近は自分も白にしてます。自分自身に染められるんじゃなくて、周りからの影響とかに勝手に体が動いちゃう自分に期待してる。
――そうやって生活を変えることが、自分から生まれる音楽や歌詞の変化に繋がる、というのは、作詞の先生をやっている時も生徒へ教えることですか?
蟻:そうですね、教えますね。やっぱり、私以上に縛られている生徒さんが多いから。真面目で一生懸命で努力家な人が、頭いっぱいいっぱいになってガチガチになっちゃってると、「そんなに頑張らなくいいよ」って言いますね。鎖みたいなものを外してあげることばっかりやってるかな。制限をかけられている世界を突破したくて苦しみを書くのは、それはそれでいいんだけど、スランプとかがきたら「その枠から出ていいんだよ」っていうことは言いますね。そうだ、昔、スガシカオさんに詞を見てもらった時に「枠がある」って言われたんですよ。その時はその意味はわからなかったんですけど、今ならちょっとわかるなって。
――「枠がある」?
蟻:なんというか、「額縁があってこそ自分です」みたいな。そういう頑なさが武器だと思っていたから、その枠を外した時に絵一本で勝負できないと思ってた。
――じゃあ、その枠を外した今作は、蟻さんにとってもかなりの挑戦だということですよね。
蟻:そうそう。だからね、(リリースするのが)ちょっと怖いんですよ。
――自分で自分の「枠」にしちゃっていたものって、具体的にいうと、どういうところだと自覚していますか?
蟻:私は否定的な部分で自我を保っていたから(笑)。今回は否定的な言葉を一切排除しようという試みでやってて、それはかなり難しかったです。あと、今までは「前を向く」とか、「一歩踏み出す」とか、そういうところを書いてきたけど、今回は雲みたいにふわふわしているところを書けたらいいよね、って思ってました。強い意味を持たせて人になにかを伝えようとするよりも、自分の中にあるふわふわした部分を言葉にするっていう。「伝えよう」とか「誰かのために」って思うのが私の枠だなという感覚があったので。
――キミノオルフェをスタートした時は「キミの吟遊詩人になる」「誰かの人生を歌う」がコンセプトだったから、かなりのシフト・チェンジですよね。
蟻:そうですね。自分の中にいるちっちゃな自分、みたいなやつを救い出そうとしてたから……まあ、でも、そのちっちゃい自分はこっちの詞でもいるわ(笑)。

これは自分の問題で、相手に問題を押し付けちゃいけない
――キミノオルフェを始めてからこの4年で、蟻さんが音楽活動に向けるモチベーションの根本って変わりました?
蟻:それは変わってないですね。たぶん、私、物を作ってないと死んじゃうから。なんのために音楽をやっているのかと聞かれると、やらないと自分がどう立っていいかわからなくなるからかもしれない。やめたことないからわからないんですけど。小学校の時から絵が上手いって褒められて友達にも教えて、小学校高学年から詞を書き始めたから、ずっと物作りをして生きてますし。
――そもそも、EP全体のサウンド・プロデュースを人に託すってかなりの決断だと思うんですけど、今作でEXPCTRにそれをお願いしたのはどういった理由からでしょう?
蟻:すっごく刺激的だったんですよね、自分にないものをEXPCTRが持ちすぎていて。今まで一緒にやったDYES(IWASAKI)くんとかioniくんとかは、近いものを感じるんです。でもEXPCTRの音楽には近いものを1ミリも感じないんですよ。だから教えてもらうことが多かったです。言葉の使い方もそうだし、歌い方とか音作りの考え方とかもそう。それらを吸収するためにも、長く時間をかけてたくさんの曲を作りたいなっていう気持ちもありました。
――声をどう使うか、声でどう言葉にならないものを描くか、という点も今作においてはとても特徴的ですよね。
蟻:そうですね。今までは殴り書いたような強さで、筆圧高めで詞を書いてたから、声の種類を使う余裕がなかったというか、腹から声出して大声で歌った方がいいと思ってたんですよ。でも今回は書ける文字数が少ない分だけ、声で背景を付けてる感じはします。
――例えば2曲目「Forget-me-not」は、地声とハイトーンが重なり合っていることで、この世の人とあの世の人がお互いに語りかけているように聴こえたり。
蟻:そこまで読み取ってくれるなんて、ありがたいですね(笑)。
――それは、意図してましたか?
蟻:今日、意図してることをあまり語らないようにしようって決めてここに来てて(笑)。なのでそこはご想像にお任せします。宇宙の果てには空気がないけど、でもすごく無限の自由を感じるから、そういう広さを描けたらいいなとは思ってました。「Forget-me-not」はかなり思い入れがある曲で。おばあちゃんの認知症が進んでしまって自分が忘れられてしまったことだったり、あとは亡くなった生徒のことも想いながら書いてましたね。

――その生徒さんのことを、少し聞かせてもらうことはできますか?
蟻:作詞の生徒の男の子なんだけど、彼とはものすごく話をして。不満がないことが一番の不満だって言ってた。幸せな子だったから。でも、尾崎豊に憧れてた。彼は本当に、詞を書くために生まれてきたみたいな人だったんです。二十歳まで生きてたらもっと違う道が拓けたんじゃないかなと思うけど、でも彼にとってはきっとそこが寿命だった。来世で彼にとってのおもしろい人生を期待したのかなって思う。ご家族にも会ったんですけど、すごくいい、優しいお家で。
その子が最期に待ち受けにしてたのが勿忘草の花で、作詞教室の下に同じ青い花が咲いてるのを見つけた時に、その子が近くにいるように思えたことが嬉しかったんです。それに加えて、この曲のデモができ上がった時、そんなエピソードを知らないはずのプロデューサーがタイトルを「Forget-me-not(勿忘草)」にしたいって言い出したんですね。そこから詞を書き始めたから引っ張られたのかもしれない。そんな気持ちもあって、「Forget-me-not」は私の中でかなり入り組んでますね。
――死別や忘れられることについて、蟻さんどのような受け止め方をされているのでしょうか。
蟻:おばあちゃんに忘れられてしまって思ったのは……びっくりはしたけど、本当に悲しくはなくて。KinKi Kidsの「愛されるより 愛したい」が頭の中に流れてきたんですけど、私はめちゃくちゃおばあちゃんのことを想ってるから、相手に忘れられたとしても悲しくないなって思いました。これは自分の問題で、相手に問題を押し付けちゃいけないなって。男の子が亡くなった時も、もちろん泣き腫らしたし驚いたけど、たぶん、誰よりも早く彼の決断を認めてる。私の考え方は特殊だと思うし、こんな考え方を誰にも押し付けられないけど、私はすぐに認めたんですよね。自分が覚えてるかどうかだなって。自分が忘れてしまった時が一番悲しいと思うから。

――EXPCTRが作る浮遊感やサウンド・スケープがあってこそ、音楽で描き切れた感情や出来事だったとも言えそうですね。
蟻:彼が言ってたのは……常に死を匂わせているんだって。アンティークって言うんですかね。言葉を過激にすると「腐っていく感じ」というか。木が朽ちていったりするような。そういう音をEPの全体に忍ばせてます。
――それは、「Forget-me-not」からの発想?
蟻:いや、どうでしょうね? オンライン・ライブ(11月28日に開催)の前に、バンド・メンバー全員にこのEPよりも前の曲も含めて全部1曲ずつ詞の説明をしたんです。これはこんな想いで書いてるよ、って。時間をかけて丁寧に説明したつもりなんですけど、それをたぶん、汲んでくれてますね。
――なるほど。レコーディングの仕方に関しても、今作はこれまでと違う部分が多かったのでは?
蟻:そうですね。プリプロの段階で、EXPCTRはかなり口を出してくるので(笑)。「ここはこういうメロディの流れ方で」とか、「そこでしゃくらないで」とか、こだわりがすごく強くて。でも今回、宅録(事務所の一画をスタジオ仕様にして録音)なんですよ。マイクも、ライブハウスでみんなが使ってるようなもの(SHURE BETA 58)で録りました。
――そうした理由はなんですか?
蟻:やっぱりコロナも意識せずにはいられなかったから。「Then, the Curtains Open」のMVも家で撮ったんです。そもそも「Then, the Curtains Open」には、自分が歌い出せばどこだって幕は開く、そこがステージになる、という意味を込めていて。それは、自分も周りのアーティストも音楽に携わる人たちも今苦しんでいるから、どこでも歌を歌ったり楽器を鳴らしたりすれば、それはステージの上になるよ、という想いで。今思えば、だからレコーディングも部屋の中にしたのかな。狭い部屋の中で、耳元で囁かれているようなゾクっと感が、今回は特にできたんじゃないかなって思ってます。
「聴こう」という強い意志がなくても聴ける音楽
――今回、蟻さんとしては珍しくラブソングが多いじゃないですか。「Tender」、「ふたりで」、「When I Need Your Love」。ラブソングが増えたのは、蟻さんの心境変化の表れですか?
蟻:めちゃめちゃ心境の変化はあります。
――……恋してますか?(笑)
蟻:まあ恋してるかどうかは置いておいて(笑)。「Tender」の歌詞をずっと書けなくて、EXPCTRに相談したら、「蟻ちゃんの詞は小学生の時の男子とか女子とかがなかった、性がまだ生まれてない状態のまま大人になった感じなんだよね」って言われて、それはすごく自分の中でしっくりきて。経験を経て、歳を重ねて大人になった自分が書けるのはどんな言葉なんだろうと思って、そのイメージで「Tender」を書き始めたら、本当にあっという間に書けたんですよね。
――「When I Need Your Love」は、オンライン・ライブで最後の曲として演奏したシーンもとても印象的でした。無観客ライブは実際にやってみてどうでしたか?
蟻:無観客ライブのおもしろさを実感できました。こんな世界になってなかったら無観客ライブはやってなかっただろうなと思うと、これはいい経験だったから、コロナ禍でもプラスな面がひとつでも見つけられたのはよかったなって思いました。
――無観客ライブは寂しい、というアーティストの意見をよく耳にしますけど、蟻さんにとってはなにがそんなにおもしろかったですか?
蟻:より「1対1」なんですよね。通常のライブの時も、いつも私は「お客さん一人ひとり対 私」の2人の空間だって思ってるけど、でもやっぱり、隣にいる人の存在を消すことはできないから。オンライン・ライブを観てくれた人って、きっとイヤホンをして画面に向かっているだろうから、より2人きりになれた感じがしたんですよね。


――蟻さんのリスナーに対して「大丈夫だよ」と言ってあげる聖母みたいな佇まいを、今までで一番強く美しく感じられるライブでした。
蟻:美しくしてもらいました、ありがとうございますという感じです(映像は東市篤憲監督率いるA4Aが手がけた)。子どもの時から弟と妹に、根拠もなく「大丈夫だよ」って言ってきたから、その延長線上にあると思いますね。でも、あのライブ、怖くてまだ自分で観れてないんですよ。そろそろ自分の気持ちが落ち着いてきたので、今日観ようと思ってます(笑)。
――最後に、改めて、EXPCTRと一緒に音楽を作ることで、どういった新しいキミノオルフェを生むことができたと実感していますか?
蟻:今回は、技術を磨くことがおもしろかったんです。曲を作る過程でそういう感覚になるのは初めてかも。歌詞を勉強しながら、新しい歌い方を編み出して、レコーディングも実験的に宅録をやって、というのがおもしろかったですね。「聴こう」という強い意志がなくても聴ける音楽にチャレンジしてみたかったから、生活の中にそっと溶け込むような存在の音楽であって欲しいという願いがあるかな。その上で、そばにいるっていうことを感じてもらえたらいいなと思います。

【リリース情報】

キミノオルフェ 『Then, the Curtains Open』
Release Date:2020.12.25 (Fri.)
Label:
Tracklist:
1. Then, the Curtains Open
2. Forget-me-not
3. Tender
4. ふたりで
5. That Never Goes Out
6. When I Need Your Love