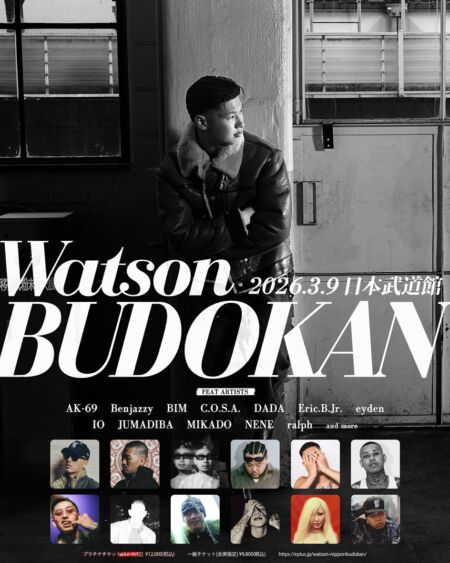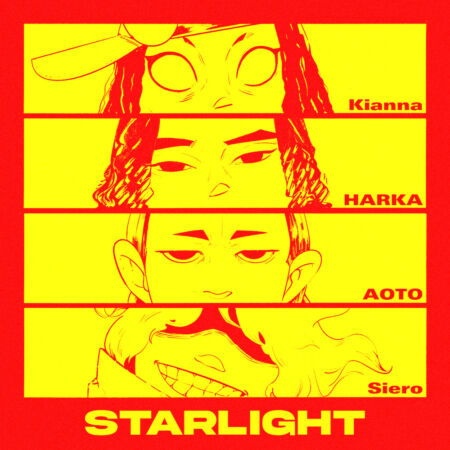昨年2ndアルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』をリリースし、”FUJI ROCK FESTIVAL”をはじめとした大型フェスにも複数出演。同時にライブハウスを中心に年間100本を超えるライブを重ね、バンドとして着実なスキルアップとステップアップを見せるHomecomings。
また、「映画上映 × ライブ」を掲げた自主企画イベント”New Neighbor”をイラストレーターのサヌキナオヤと共催するなど、新しい取り組みもスタートさせた。さらにはTV出演やラジオ番組のレギュラー起用、ファッション雑誌への特集掲載など、精力的な活動も行う中、2017年7月5日に『PLAY YARD SYMPHONY EP』をリリースした。本作は、これまでの彼らを深く知る者にとっては、バンドとして一皮も二皮も向けたことがすぐさま感じられる作品となっているだろう。今回Spincoasterでは、この作品に辿り着くまでの、Homecomingsのこの1年間の成長の歩みと、そこから導き出した答えを訊いてみた。本記事から、急成長を遂げるバンドのリアルを感じて頂ければ幸いだ。
なお、今回インタビューとの連動企画として、音楽アプリ『TYPICA』のオリジナル・プレイリスト企画”#NOWLISTENING”にて、Homcomingsの畳野と福富による「今、一番聴いている音楽」7曲を掲載。アプリをダウンロードして、是非ともこちらもチェックしてみて欲しい。
TYPICAをダウンロードする
Interview by Kohei Nojima
Photo by Takazumi Hosaka

―昨年5月にセカンド・アルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』をリリースし、その後も”FUJI ROCK FESTIVAL”や”RUSH BALL”など大型フェスへも出演を果たし、その他にもワンマン・ツアーや自主企画なども敢行するなど、2016年はかなり精力的に活動してきた1年となったと思います。まずはその昨年1年間を振り返ってみていかがでしたか?
福富:とにかくライブの本数をこなすっていうのが去年1年間の目標としてあったので、2ndアルバムを出した年っていうよりは、めちゃくちゃライブをやった年っていう感じなんですよね。自分らのツアーもそうやし、地方とかにも色々呼んでもらって、たぶん昨年は100本近くのライブをやったんじゃないですかね。
―バンドとして、そういうモードになったのはなぜなのでしょうか?
福富:うーん、なんだったんでしょうかね。でも、やっぱりライブが上手くなるためにっていうのはあったと思います。
畳野:そうですね。
―特に印象深かったライブやイベントなどはありますか?
福富:やっぱりさっきおっしゃっていた”RUSH BALL”みたいなでかいフェスは印象に残っていますね。バックステージにBRAHMANのTOSHI-LOWさんがいたりして、「わ〜!」みたいな(笑)。
その一方で、次の日には地元京都の100人くらいのキャパのライブハウスでのイベントに出演したりして。そういうのが新鮮でしたね。大きいフェスも、ライブハウスでのイベントも同じようにこなしていくっていう。
畳野:ツアーも多くて、土日はほぼ毎週どこかしらに遠征してるっていう感じで。地方にも色々行ったんですけど、そういう記憶がすごい残ってるんですよね。「特にここ!」っていうことではないんですけど、色々な所に行って、色々な景色を見たっていう記憶が。あとは、その土地土地で触れ合った人の感じとか。
福富:それこそ島根とかはライブハウスじゃなくてカフェみたいなところでの出演だったんですけど、それでもちゃんと地元のDJさんがいたり、オーガナイザーさんがイベントをしっかりと仕切ってくれていて。
畳野:「こんな遠く離れた所にも私たちを待っててくれてる人たちがいるんだ」っていうのを実感できたツアーだったよね。やっぱりそれが印象に残ってますね。
―また、昨年はそのようにしてライブを多数こなす一方で、同時にラジオのレギュラー出演も決まりましたよね。これは中々に大きい出来事だったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
畳野:そうですね。今も週1でやらせて頂いてるんですけど、大分……というか、やっと慣れてきて(笑)。何か意外とこのラジオへの出演がライブに影響したりしていて。
―MCのネタになったり?
畳野:はい。話のネタになったりとか、あとはちゃんとした喋り方みたいなものがだんだんわかってきたんですよね。「それで〜」みたいに、相槌を入れたりして、途切れずに喋り続けるっていう。それがいいのか悪いのかはわからないんですけど、どんどん喋っちゃうようになりましたね(笑)。
4人で出てるラジオもあるんですけど、結構最初の方は戸惑うこともあって。「この後どうしよう……」みたいな間があったりとか、話しが下手な部分もあったんですけど、最近はなんとなく形になってきたなって思うようになって。基本的にはダラダラと喋ってるだけなんですけど、誰かが進行役みたいなのを担当したりして、みんなで上手く話題を回していく、みたいな。そういうやり方をみんなわかってきたので、上手になってきてるなって思ってます(笑)。
福富:あと、ライブとかでも「ラジオを聞いて来ました」って言ってくれる方がいたりして。
畳野:そうそう。お笑い好きの人がラジオで知って来てくれたりとか、FM802っていう関西の放送局でちょっとしたコーナーをやらせていただいているんですけど、それを聞いて来てくれる人も結構いて。
福富:結構僕ら1stアルバム(『Homecoming with me?』)をリリースした時からラジオに出させて頂く機会が多くて。普通に生きてたらラジオって中々出演する機会なんかないし、僕らもバンドとかやってなかったら絶対出てないし。そんなに世代的にも身近なわけじゃないんですけど、それでもラジオをやってるからこそなんか見えてくるものもあるなって。
畳野:意外と……って言っちゃ失礼かもしれないですけど、「ラジオっていっぱい聞いてる人いるんやな」って改めて実感しましたね。自分たちが普段発信できないような範囲の人たち、私たちのことなんか全然知らない人たちにまで届く可能性があるというか。しかもそういう層って、普段わたしたちが接しているような音楽好きな層よりも、母数が圧倒的に多いんですよね。ラジオに出させて頂くことで、そこに改めて気づけた。
福富:この前、タクシーの運ちゃんにも「日本語の曲やれ」って言われたんですよ(笑)。
―ホムカミのラジオを聞いてる運転手さんってことですか?
福富:そうです。今MBSラジオで放送されてるんで、運ちゃんとかが夜中に聞いてるんですよね。
畳野:この間一緒に帰った時か。そんなこと言ってたっけ?
福富:いや、僕がひとりになってから。「僕は日本語でやってほしいんですけどねー」って(笑)。
畳野:私がいた時は気をつかって言えなかったのかな(笑)。
―日本語詞の曲を歌うってことは、Homecomingsとしては今後あるのでしょうか?
福富:Homecomingsとしてはやってないんですけど、平賀さち枝とホームカミングス名義とかではやっていて。元々この4人は洋楽しか聴かないわけでもないんで、私たちは普通にスピッツも好きやしシャムキャッツとかミツメとかも好きで仲良いし、共演もよくしてるし。だから日本語っていうもの自体には抵抗はないんです。ただ、これまではなんとなくやってないだけ。自分たちとしては日本語詞の音楽も大好きだけど、自分たちのバンドとしてその時々で理想の形をアウトプットしていくと、それが今みたいな英詞の曲になるっていう。
―そういえば2015年末にはENJOY MUSIC CLUB「クリスマスをしようよ」のカバーをリリースしていますよね。あれも日本語詞でしたが、すごい合っていました。
畳野:本当ですか。「こんなことしたら怒られるぞ」って思ったこともあるんですけどね(笑)。あの曲は武蔵野公会堂で開催されたENJOY MUSIC CLUBの”エンジョイスーパーライブ”で一回だけライブで披露しました。後にも先にもあれ一回きり(笑)。
―話を戻して、去年にはイラストレーターのサヌキナオヤさんと企画した映画と音楽のイベント、”New Neighbor”も開催しましたよね。あれはHomecomingsにとってもかなり意味のある企画だったかなと思いました。あの企画がスタートした経緯を教えて頂けますか?
畳野:まず、私がたまたま『アメリカン・スリープオーバー』を観て、すごく感動しちゃったんですよね。その時は下北沢の小さい映画館で観たんですけど、物語自体ももちろんだし、あとはエンディングにも私たちが昔カバーしていたThe Magnetic Fieldsの「The Saddest Story Ever Told」が流れたっていう部分にも運命を感じたんです。で、元々サヌキさんとは映画の話をよくするんですけど、その時にも「『アメリカン・スリープオーバー』めちゃくちゃよかったよ〜」っていうLINEを送って、その会話の延長線上で、「何かできないかな?」、「上映会とかやりたいね」っていう話になり、そこから徐々に構想を固めていきました。なので、本当に『アメリカン・スリープオーバー』があったからこそスタートした企画ですね。
―映画を上映するに辺り、権利関係をクリアするのは中々に難しかったのではないでしょうか?
福富:Gucchi’s Free School(グッチーズ・フリースクール)っていう日本に未公開の映画を紹介しているサイトがあって、そのサイトを運営している方が全面的に協力してくれたので、意外とすんなりと話が進み。
畳野:すごい協力してくれたので、思ってたよりも大変じゃなかったんですよね。
福富:本当にあのイベントはやってよかったですね。自分らがなんで未だに英語詞でやってるのかとか、そういうことに対する答えじゃないですけど。
畳野:色々と綺麗に繋がったよね。
―ちなみにライブは映画の後に?
畳野:映画の前ですね。アコースティック・セットでやりました。
福富:すごいよかったよね。
畳野:私たち的にはライブを観て、その後に映画も観るっていうのは、結構お客さんからしてみたらしんどいんじゃないのかなって思ってた節もあるんですけど、いざやってみたら「すごいちょうどいい!」って言ってくれて。映画も1時間半くらいでサクッと観れたし。
福富:僕たちが普段京都で観に行ってる単館系の映画館が3つくらいあるんですけど、その映画館の人たちも観に来てたりして。さらにその繋がりでまた大阪でやる映画のイベントに誘われたりして。
―なるほど。では、あの企画は今後も続けたいと。
畳野:そうですね。次も絶対やりたいです。また京都で。
福富:東京でも会場を探してたんですけど、場所的にちょうどいい感じのところがなくて。でも、逆に京都やからできてることなのかもって思うようになり、それはそれでいいのかなって。
―ちなみにホムカミの皆さんは映画好きであることを公言していますよね。ここ1年くらいで良かった映画は?
福富:本当最近のやつなんですけど、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』がすごいよくて。やっぱりこういうのが好きなんやなって思いましたね。僕がよく行く京都シネマっていう映画館は普通に新しい映画も上映してるんですけど、同時にちょっと昔の名作も『名画リレー』っていうシリーズで上映していて、そこの会員は500円で観れるんです。それで観た『スモーク』もよかったですね。ポール・オースターが原作と脚本をやってて。
―では、いよいよ今回リリースされる新作EP『SYMPHONY』についてお聞きしたいと思います。今回は2ndアルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』からおよそ1年ぶりのリリースとなりますが、制作はどういったところからスタートしたのでしょうか?
福富:まず、これまで僕らはずっとコンセプト・アルバムみたいなものを作ってきたので、今回はそういうのじゃない作品でいこうと、そういう話からスタートしたような気がします。1年くらい期間も空いていて、その間にできた曲とか湧いてきたアイディアをとりあえずワーッと書き出してみて、それをどうやって曲に当て込むかを作りながら考える、みたいな。本当にバラバラのアイディアが4つなり6つなり出てきて、それを形にするっていう作業でしたね。
―1曲目の「PLAY YARD SYMPHONY」はホムカミ史上初のストリングスを導入した楽曲ですが、これはどういったキッカケで?
福富:昨年リリースされたThe Avalanchesの2ndアルバム『Wildflower』にめちゃくちゃハマって。彼らみたいなことをバンドで、しかも不自然じゃない感じでやりたいな〜っていうところからですね。ギターは「スマパンか!」っていうぐらいの感じでジャーンって鳴らして、それにストリングスを付けたら結構新しいんじゃないかなと。どっちにも寄り過ぎないようにバランスを取りつつ。
―また、その「PLAY YARD SYMPHONY」だけでなく、本作では全体的により立体感のある音作りになっているところも深く印象に残りました。
福富:そうですね。自分らでも何か音がのっぺりしてるなーっていうのは昔から感じていた部分で。だから今回はドラムとベースだけ大きいスタジオで録ってみるとか、立体的にしたいっていうのは確かに考えていたことで。音域の話になっちゃうんですけど、今までは真ん中くらいの帯域がボーンって出てたと思うんですけど、今回はもっと全体的にレンジの広い感じを意識していて。それでギターも変えましたし。のっぺりとしないように、ギターのリフもより張るようにしたし、曲の構造とかもそこを意識して変えていった部分がありますね
―あとは、ライブ感があるというか、どの曲もライブ映えしそうだなと。
福富:そうですね。ただ、演奏するのは難しいですけどね(笑)。今までの曲は結構目を瞑っててもバーってできる感じやけど(笑)、今回のはシッカリとキメがあったりとかして(。
―ブレイクというか、そういったキメる部分も随所に配置されていますよね。
福富:本当に4曲ともそういうキメがあって。そこが今までと違うなって思いますね。
畳野:あと、どの曲もカップリングじゃないんですよね。聴いていると、どの曲もなんかこう、全部目立ってるというか。
福富:1曲1曲がシングルにもなりうるよね。だから、リード曲とカップリングっていう構造ではなく、本当に全部で1個の作品、一枚のEPなんですよね。去年ライブをめちゃくちゃやりまくって、そこで物足りないじゃないですけど、もうちょっとこういうのも欲しいな〜っていう部分が自然とアレンジとして反映されているのかなと。ライブでずっとやってきた曲ではないんですけど、ライブで盛り上がるようにっていうのは意識していて。ライブ感っていうのはそういうところから出てるのかなって思いますね。
―ライブを数多くこなしてきて、バンドとしての演奏スキルも上がってきたからこそ新しいチャレンジができると。
畳野:そうですね。あと、これまでの作品も制作する前からの理想像みたいなものが頭の中にあったんですけど、今作はその理想を実際の作品として最も綺麗に形にすることができたんじゃないかなって思うんですよね。例えばPixiesとかWeezerとかBuilt to Spillとかを参考にしたり、そういう理想というかテーマを決めて、実際に作り込んでいくんですけど、結局作品ができた後に「そこに近づけたか?」って言われると、毎回「何か微妙に違う気がするな〜」っていうか。なんだかんだHomecomingsになるっていう。もちろんそれはいいことなのかもしれないんですけど、作ってる側としては「またこういう感じになったか」っていう感情もあって。
でも、今回はその感覚から一歩進んで、確かにHomecomingsなんだけど、ちゃんと自分が思い描いていた要素をたくさん、そして綺麗に詰め込むことができたなって思うんです。実はいざ完成した時点ではまだなんとなく自分の中でモヤモヤしていたんですけど、マスタリングが終わって何回か聴いたら、「これはすごいぞ!」って実感できたんですよね。
―過去のインタビューではネオアコやシューゲイザーなど、そういった括られ方にあまりシックリきていないといったこともおっしゃっていたと思いますが、そういった話は、そのモヤモヤしていた部分に通ずることなのでしょうか。
畳野:いや、別に言われることは嬉しいんですけど、「あ、そうなのかな」みたいな。「そんなつもりじゃないんだけどな」っていうのは内心あって。もちろんそういう音楽も私たちは大好きなので、そういった括り方も全然間違ってはないと思うんですけど。たぶん要素として自然と出てしまってるのかなっていう気がしますよね。
―色々なチャレンジをしつつも、そういった枠組みから中々離れられなかったこれまでとは違い、今作では現在進行系のHomecomingsをハッキリと強く打ち出せたと。
畳野:そうですね。基本的にはこのふたり(畳野と福富)で曲作りをしてるんですけど、お互いの好きなThe Avalanchesとかそういう好きなものをちゃんと入れることができたなって思います。
福富:たぶん1番最初の出発点はギター・ポップで、その後徐々に自分たちの好きなものを色々と詰め込んできたつもりなのに、未だに「ギター・ポップ」って言われちゃう、みたいなね。でも、最近では1周回ってまたそのギター・ポップに回帰したいなっていう気持ちもあったりするんですけどね。まぁこれは次の話なんですけど(笑)。
畳野:え、もう次の話してんの?(笑)
―(笑)。では、今回のEPで新たに挑戦したことや、制作方法を変化させた部分があれば教えてください。
福富:細かいことを言えば、ギターやアンプといった機材も変えました。
畳野:あと、曲作りも今回はいつもと違うやり方をしていて。
福富:今までの、ネタやアイディアだけスタジオに持っていって、そこからセッションで組み立てるっていう形ではなく、今回はもうちょっとDTMでデモっぽいものを固めてから肉付けしていくっていう方法になりましたね。
畳野:これまではレコーディングに臨む段階では毎回歌が乗ってない状態だったんですけど、今回はレコーディング前に歌も込みで一度完成させたんです。そうやってしっかりとプリプロをやって、そこからレコーディングに臨むっていうちゃんとしたレコーディングのプロセスを踏みました。なので、レコーディングに入る前の段階から結構完成系が見えてたんです。
福富:ちゃんと全体図が見えてる状態で録るので、「ここをこう弾いたらもっと立体的になるな」とか、「ここはちょっと足らんから付け足そう」とか。そういうことがよりわかるようになったんですよね。
畳野:今回は結構制作期間も多めにあって、たぶんそれも影響してるよね。今まではレコーディングまでがバタバタしていて、そのまますぐにミックスに入る、みたいな感じだったんです。でも、今回はゆとりがあったから、同じ曲を何度も何度も聴いて、どうしたらもっとよくなるかってことを考える時間が取れた。そしてその分細かい所まで手を加えられたし、より凝った作品にすることができた。
―本作のイントロ部分ではフィールド・レコーディングのような歓声から始まりますよね。それもホムカミの作品としては新鮮でした。あれはどこで録音したものなのでしょうか?
福富:フィールド・レコーディングとかを入れようと思ったのは、やっぱりThe Avalanchesの影響が大きくて。最初は無数の映画からサンプリングして曲を作ろうかなって思ってたくらいなんですけど(笑)。
畳野:最初にそれを言われた時はとうとう頭おかしなったんかと思いました(笑)。
福富:なので、せめてイントロの部分だけでも色々な映画からサンプリングして作ろうと思ったんですけど、それは流石に権利の関係上、難しいだろうということになり、フィールド・レコーディングで音を集めました。ケータイのアルバムの中に入ってた昔の動画とかからも取ってきたり。
畳野:大学の頃にふたりでボートを漕ぎに行ったんですけど、その時にたまたま近くにいた外国の親子が歌ってて。
福富:その様子を収めた動画が残ってて、それを使ったり。あとは『ゴーストワールド』のイーニドのセリフとかを、これそのまんまやと使えんから、その代わりに「ハイ! イッツミー」って言ってもらって録ったり(笑)。
今作のエンジニアの荻野(真也)さんって方は1つ前のアルバムも手がけてくれた人で、結構前から僕らのライブのPAもやってくれているので、そういうアイディアを共有しやすいんですよね。なので、みんなで楽しみながら色々と試してみたりして。
畳野:そうですね。荻野さんは普段からバンド・メンバーって言っても違和感ないくらい近い距離にいる人なので、うちらがその時に聴いてる曲とか思ってることとか、ハマってること。そういったことを全部共有できてるので、なんとなくポロって言っただけのアイディアでも、「オッケー」って言って全部汲み取ってくれて形にできる。それくらいチーム感が固まっているんですよね。
―「PLAY YARD SYMPHONY」の歌詞の中に「The remains of the wet ghosts(湿った幽霊たちの跡)」という一説が出てきます。前作は裏テーマに「幽霊たち」というものを掲げていたそうですが、今作もその裏テーマのようなものは継続しているのでしょうか?
福富:はい。前の作品から幽霊的なものを捉えようとするっていうテーマみたいなものは引きずっていて。あと、実はもうひとつのメイン・テーマみたいなものに、「芝生」っていうのがあって。映画の『ヴァージン・スーサイズ』とか『バッド・チューニング』に出てくる朝の芝生、夜明けの芝生のあの感じ。夜露で湿った芝生のあの感じが……すごい素敵やなって(笑)。
畳野:そういうことちゃんと言ってくれないんですよね(笑)。最初に作品作る時に、「今回はどうする?」って感じで毎回テーマみたいなものを決めるんですけど、今回は「芝生」って言われて、「ん?」って(笑)。
本当に「芝生」しか言わないんですけど、まぁなんとなくはわかるので、「はい、わかりました」って言って作って。「芝生」とだけ言われてたから、今回はジャケットにも芝生が描かれてます。
―なるほど(笑)。ちなみに、歌詞を書くときはどういった物事からインスパイアされ、どういった手順で固めていくのでしょうか?
福富:一応日頃から気になったフレーズとかはメモしたりしていて。あと、今回は曲が先にあって、『PLAY YARD SYMPHONY』っていう作品全体のイメージだけはあったので、それに沿って考えていきました。前のアルバムは先に歌詞があったりしていたんですけど、今回は結構ギリギリまで練ってましたね。
―2曲目「SLACKER」の歌詞はストーリーテリングな作風ではなく、珍しく抽象的な世界観となっていますよね。
福富:あの曲はリチャード・リンクレイター監督の映画『スラッカー』からタイトルを付けてるんですけど、あの作品のように、ひとつの物語じゃなくて、色々な世界がぶつ切りでバーっと連なっていくっていう表現方法をやりたくて。だから1行1行には自分の中で固まった世界観があるんですけど、それをまとめないで全部バラバラのまま並べてある。前のアルバムはストーリーとかを描き出すことに重点を置いていたんですけど、それとは全く違う手法ですよね。
福富:そういうバラバラのものが並べてあるっていうイメージも、「シンフォニー」っていう言葉に繋がっていくのかなって思うんですよね。4曲それぞれが群像劇のような作用をもたらすというか。これまでは作品を通して1人の主人公を立てて、曲ごとに色々動かしていくって感じだったんですけど。
―リミックスを除いたオリジナル楽曲4曲が群像劇のように機能しているからか、今作は作品全体として統一感を感じさせつつも、明らかに4曲とも異なるカラーを放っていますよね。
福富:そうですね。ただ、曲に関しては本当に湧いてきたアイディアを試してみようっていう感じで作っていって、その中から形になったものを集めたんです。こういう曲にしようとか、こういう曲が足りないから作ろうとか、そういうことは一切考えずに。
畳野:本当に自分たちの欲求に忠実に、作りたい曲を作ったって感じだよね。
―また、今回はBUSHMINDさんによるリミックスが収録されています。ロック・バンドありながら、リミックスを収録するということに対してはどのような意識を持っていますか?
福富:僕らは昔からリミックスっていう文化自体がめちゃくちゃ好きで。僕らが所属している〈Second Royal〉っていうレーベルにはHALFBYさんとかHandsomeboy Techniqueさんみたいなトラックメイカーも在籍していて。なので、これまでも平賀さち枝とホームカミングス名義の作品とか、7inchシングルにもリミックスを収録したりもして。それで味をしめたというか、やっぱりすごいおもしろかったんですよね。自分の曲が新たな解釈で生まれ変わる感じが。あと、初期の頃の曲はギターもガチャガチャしててリミックスしづらい曲ばっかだと思うんですけど、ここ最近の僕らの曲なら、案外リミックスしてもらえるんじゃないかなって思ったっていうのもありますね。
―実際に仕上がったものを聴いた時、どのような印象を受けましたか?
畳野:今回もめっちゃめちゃよかったですね。
福富:去年出した7inchに収録したHALFBYさんとHandsomeboy Techniqueさんのリミックスもすごくよくて。なんか恵まれてるなって思いますね。
畳野:自分たちの曲のリミックスを初めて聴いた時のあの感情はどう表現したらいいのかわからないんですけど、自分たちの曲が新たに人の手が加わって新しい曲になって帰ってくるっていうのがすごい感動的で。リミックスにはそういう作ってる側の私たちも楽しみに待っている感じがあるので、出来上がってくるとすごいテンション上がるよね。
―今作のリリースに際したアー写を写真家・川島小鳥さんに撮ってもらっていますが、あれはどのような経緯で実現したのでしょうか?
畳野:元々知り合いとかだったではなく、1回挨拶させてもらったぐらいだったんですけど、私は銀杏ボーイズがすごい好きだったので、自然と川島小鳥さんの写真も好きになり。あんなに女の子を可愛く撮る人はいないなって思って、いつか撮ってもらいたいっていうのは結構前から思っていて。それで今回、意を決して依頼させてもらいました。
福富:想像以上に僕まで可愛くなって、男の子でも可愛くなるんだと思いましたね(笑)。
畳野:すごい楽しい撮影でしたね。
福富:すごいいっぱい枚数を撮るんですよ。
畳野:でも、小鳥さんがふわっとしてる方だからか、すごい気を使わない撮影だったんですよね。撮影自体も公園で1日中撮ってたんですけど、疲れたりとか顔がこわばったりすることもなく、「ハイ、次」って感じでどんどん進んで。ディレクションも「その遊具で遊んでみたら?」とか「そこで寝てみたら?」、「ここに3人頭乗っけてみてよ」とか、そういう感じで。「えー?」て思いながらやってみるとすごいいい写真が出来上がって、流石だなって。あと、出来上がった写真を200枚とかものすごい量送ってもらったんですけど、どの写真も確かに全部小鳥さんの写真なんですよ。アングルと色味とか。そういうところがやっぱりプロだなって思いました。
―なるほど。では最後に、Homecomingsとして今後の展望、目指していることを教えてもらえますか? 個人的にホムカミはこれまでもいい意味で野心的ではなく、自分たちのやりたいことや好きなことを追求するバンドだと思っているのですが。
福富:いや、野心はすごいんですよ(笑)。
畳野:まだやれていないことも色々あるので、例えば日本語詞だったりとか、音楽的な面でも。
福富:「ロックで天下取る」とか、「世界をひとつに」とかじゃなくて、その時その時に思いついた自分らのやりたいこと、おもしろいってと思うことを1個1個実現させて、そしてそれがまた作品や違うアイディアへと繋がっていくのが一番いいなって思いますね。例えば映画館でイベントをする、っていうのもそういうことのひとつだと思うし。
畳野:Homecomingsっていうバンド自体が、「こういうバンド」って一言で言葉に表せられないと思っているんですけど、でも、それが魅力なのかなってちょっとずつ思うようになってきて。曲もそうなんですけど、ライブとかでもなんとも言えないよさみたいなものが4人の中でもそれぞれ感覚として共有できていて。今後もそういう部分をすごい大事にしていきたいなって思うようになりました。そういうことに気づけたっていうこともでかくて。今回の作品『SYMPHONY』がキッカケでなんとなくのよさ、絶対に言葉じゃ表わせられないよさがあるっていうことが、ホムカミの強みなんだなって気づけた。今回出来上がったEPを5曲通して聴くと、「あ、なるほど」みたいな。自分で自分たち自身の何とも言えない魅力を感じられるというか、そういう作品を作れたっていうことがとても嬉しくて。
―「これが今の私たちだ。これがホムカミだ」って胸を張って言えるような作品に仕上がったと。
畳野:そうですね。「シンフォニー」っていう言葉も結構ハマっている気がしていて。色々な要素を詰め合わせて、ひとつの効果を発揮するみたいなことが、そんまんまバンドにもイコールで繋がってくるんじゃないかなっていうことに気づいたんです。なので、今後もそういった感覚を大事にしていきたいなって思いますね。
【リリース情報】

Homecomings 『SYMPHONY』
Release Data:2017.07.05 (Wed.)
Label:felicity cap
Cat.No.:PECF-1144
Price:¥1,500 + Tax
Tracklist:
1. PLAY YARD SYMPHONY
2. SLACKER
3. PAINFUL
4. WELCOME TO MY ROOM
5. PLAY YARD SYMPHONY (BUSHMIND Remix)
【イベント情報】
Homecomings presents “BOWLER’S DELIGHT”
08.18[金] 京都・京都 磔磔 w/ おとぎ話
08.27[日] 石川・金沢 vanvan V4 w/ COMEBACK MY DAUGHTERS
Homecomings “PLAY YARD SYMPHONY” TOUR
09.07[木] 愛知・名古屋 TOKUZO ※ワンマン
09.08[金] 大阪・梅田 シャングリラ ※ワンマン
09.09[土] 東京・渋谷 WWW ※ワンマン
09.15[金] 福岡・天神 the voodoo lounge ※ワンマン
09.16[土] 広島・広島 BANQUET (SPACEO92) ※ワンマン
■Homecomoings オフィシャル・サイト:http://homecomings.jp/