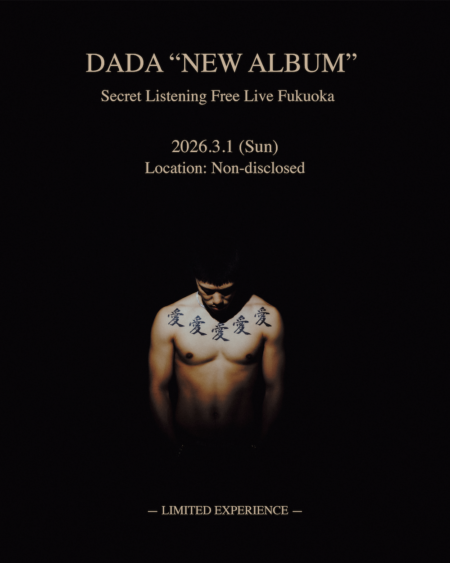Jon Hopkins(ジョン・ホプキンス)は最新作『Immunity』で、ホワイトノイズの中でビートが深く響くテクノの世界と、閑寂なアンビエントの世界をひと繋ぎにして、異空間を作り上げた。この空間ではピアノとグリッチ・ノイズが等しい美しさを持っている。
そんなクラブミュージックの深層部を突いた『Immunity』が、David Bowie、Arctic Monkeys、James Blake、Jake Bugg、Disclosureといったアーティストたちの作品と共に、2013年のマーキュリー・プライズにノミネートされたのだから驚きだ。最終的に最優秀賞を受賞したJames Blakeは、「なぜ審査員が僕のレコードをノミネートしてくれたのか、全く分からなかったよ」と言っていたが、僕もなぜ『Immunity』がノミネートされたのかが未だによく分からない。他とは明らかに毛並みの違う作品だ。しかしそれは、彼の音楽が権威ある賞に評価されたという、喜びと混同した特殊な違和感である。
彼の作曲のプロセスと、テクノの特性に触れながら『Immunity』の魅力について聞いたところ、彼はひとつひとつ丁寧に語ってくれた。
Jon Hopkinsインタヴュー
(Interviewer Hiromi Matsubara)
ーご出身は南ロンドンですよね?
そうだよ。
ー東京はいかかがですか?
これまで東京には2~3日ぐらいしか滞在したことないんだけど、こうしてまた戻ってくることができて嬉しいよ。
ー今は東ロンドンを拠点にしてるんですよね?
うん。
ースタジオの近くに住んでるんですか?
公園を突き抜けて、10分から15分歩いたところに住んでるよ。
ーではそのスタジオでレコーディングされた『Immunity』について伺います。テクノ的で、強いビートが印象的な前半と、ピアノが特徴的なアンビエント的な後半とが対をなす構成になっていたり、“Abandon Window”は東日本大震災をモチーフにした楽曲だったり、細かいポイントを挙げていくと様々ありますが、アルバム全体のコンセプトは何ですか?
実際は抽象的なことだから言葉にするのは難しいんだけど、アルバムの中心にターニングポイントを据えて、ビートの激しいセクションと静かなセクションのコントラストをはっきりとさせることで、お互いのサウンドが持っている特徴をより引き立たせたかったんだ。最初は、フェスティバルとかパーティーへ行って高揚したところから一気に覚めていく、みたいな感情の起伏を表現したかったんだ。でも実際にトラックを作って作品になってみると、パーティーよりももっと広いもの、例えば感情を含んだ作品になったと思うよ。動と静みたいな感情の動きは、場所も時間も問わないものだと思うからね。
ー前作『Insides』よりも、ビートを一定に保ったテクノ寄りのトラックが増えているんですが、ビートはどのようなプロセスで変化したでしょうか?
意識的に変化させたというわけではないんだよね。アルバムを作るっていうこと以外には、何をアルバムでやろうみたいな具体的な音像は持たないで作り始めるから、とりあえず作ってみて、出来上がった時に始めて自分でも変化が分かるんだ。でも、『Insides』のツアーをやった時にクラブ・ミュージックと接する機会が多くて、ツアーをしていく中で自分のセットもレイヴィーになったし、たくさんのヨーロッパのテクノDJと共演することで自ずとテクノのビートを吸収していった、っていう部分が大きいと思う。吸収してみて、テクノのビート特有のヒプノティックな部分、恍惚とさせられる効果が面白いと思ったよ。『Insides』はメリハリがあって、次々と展開していく感じだったけど、今回(『Immunity』)は同じビートを繰り返していく中で徐々に世界観に浸っていく感じが表現したくて、だから自然とトラックが10分、12分って長くなっていったんだ。テクノのリズムは僕にとってはキャンバスみたいなもので、リズムが早かろうと遅かろうと、そのキャンバスの上に自分の思ったような絵を描ければ良いと思うし、ビートよりもそっちの方が重要かな。
ーでは、テクノにおいてヒプノティックな感じを生み出している一番の要素は何だと思いますか?
スティーヴ・ライヒ(Steve Reich)の『18人の音楽家のための音楽』みたいな、何も変化が起きていないようで実は少しずつ変化しているっていう音楽と同じだと思うんだけど、繰り返しをすることが何か脳に刺激を与えているんじゃないかな。時間がゆっくりと進んでいくように感じたりね。8分ぐらいの長さのテクノ・トラックで、初めの2~3分は同じビートが繰り返されているだけで何も展開はないけど、その後に何か1つの要素、例えばハイハットが加わるだけでも「お、ハイハット!」って、それが大きなインパクトを伴った変化になると思うんだ。『Immunity』では、そういった効果を、ピアノとか自分なりの音楽的要素に置き換えて、繰り返しの中にちょっとした変化を重ねるようにしてトラックを作っていったよ。
ー『Immunity』では、ビートに重ねる要素として音波のようなうねりとかエコーを効果的に使っているように思ったんですが、これは意図的なものですか?
そうだね。もともと生楽器を加工して音を作るのが好きなんだ。『Immunity』ではピアノを多用したから、ピアノサウンドを加工したり、他の音を足したりしてアトモスフィアリックな音像を作っていったよ。“Open Eye Signal”でも、アナログシンセの音の裏で、ふわっとした音を出してよりアトモスフィアリックな音像を作っているのは、僕が歌ったのを加工したものなんだ。ただシンセを使って音を作るよりも生楽器に手を加えていく方が面白いと思うよ。
ーフィールド・レコーディングの音も各所で使われていますが、先ほど仰ったような生楽器と比べて、フィールド・レコーディングの音の担っている役割や特徴は何だと思いますか?
僕は「空気を与える」って言ってるんだけど、デジタルの世界から音楽を抜け出させて、理に適ったプロセスで日常の空間に音楽を持ってくることができて、日常と同じ環境に音楽が存在しているような感覚にせてくれるのがフィールド・レコーディングだと思う。日常の音とエレクトロニック・サウンドは相性が良いから、自分が音楽を作っている部屋の音をレコーディングして曲に重ねることによって、エレクトロニックなサウンドがより地に足の着いたものになると思うんだ。
ー少年時代からピアノを弾いていて、クラシックの勉強もしていたそうですが、なぜクラブ・ミュージックと言われる領域の音楽に入り込んでいったんですか?
ピアノを始めた頃は、何にも習わずに独自で弾いて、自分なりに曲を作って遊んでたんだ。7歳か8歳の時に、「ピアノが好きなら」って両親が僕をレッスンに通わせ始めたんだけど、初めはあんまり好きじゃなかったな。でも、12歳ぐらいになって上達してきたら弾くのがどんどん楽しくなってきたんだ。あと、ラヴェル(Maurice Ravel)、プーランク(Francis Poulenc)、ドビュッシー(Claude Debussy)といった20世紀の作曲家たちの素晴らしい音楽に出会えたことも本当に良かったよ。ただ、それと並行してエレクトロニック・ミュージックも大好きだった。とはいえ、12歳ぐらいの時はコンピュータを使って自分で曲を作るわけにはいかなかったから、ラジオでエレクトロニック・ミュージックがかった時に夢中になって聴いていたぐらいだったけどね。14歳の時に初めて買ったコンピューターがAmiga 500っていう機種で、それを使ってサンプリングのプログラムを独学で覚えて、学校を離れた18歳の時から本格的にエレクトロニック・ミュージックの作曲を始めたよ。
ー幼少期からしばらくピアノを弾いてきて、初めてシンセを弾いた時はどういう感じでしたか?
一番最初は……家にあったYAMAHAのミニキーボードだったかな(笑)。18歳の時に行った音楽学校に、自習室みたいな自由に楽器に触れる部屋があって、そこにYAMAHAのDX7があったよ。本格的なシンセを触ったのはそれが初めてだったかな。凄くエキサイティングだった記憶があるよ。しばらくして今度はYAMAHAのSY99が学校に入って、それが凄い気に入ったから、後に自分でSY77を買ったよ。あとは、RolandのD-20を使ってたよ。
ーリンデン・グレッドヒル(Linden Gledhill)とクレイグ・ウォード(Craig Ward)による結晶を顕微鏡で撮った写真作品を『Immunity』のアートワークに使用していますが、その理由について、あなたが音楽を作る過程と結晶ができていく過程に近いものを感じたから、という話をあるメディアで読みました。その辺りについて詳しく教えて下さい。
これは全然加工を加えていない写真なんだけど、まず写真そのものが素晴らしいよね(笑)。最初にクレイグ・ウォードの方にコンタクトしたんだ。彼の、ガラスで言葉を作って、それを壊す瞬間を写真に収めた作品や、煙で言葉を作って薄くなっていくところを写真に収めた作品を面白いと思ったんだ。でも今作のこととはあまり関係なくて、ただデザイナーとして彼を気に入って、何かを一緒にしたいと思ったからなんだけど。今作に関しては、彼が自分の代わりにリンデン・グレッドヒルを僕に紹介してくれたんだ。彼は生化学者なんだけど、もとは趣味で結晶の顕微鏡写真を撮っていたそうなんだ。ひとつの音を作ったらそれを顕微鏡で見るかのように細かい部分まで追求していったり、この音のこの部分を広げて、取り出して、またそこをサンプリングして、ってどんどん繋げていくような作り方をしている部分は、結晶ができていく様子やリンデンの作品と似ていると思うよ。でも、何より僕がリンデンの作品を素晴らしいと思たからアートワークに使ったんだ。
■Biography
ロンドンを拠点に活動するプロデューサー。08年、ブライアン・イーノと共にコールドプレイの『美しき生命』に楽曲提供/プロデューサーとして参加。コールドプレイの世界ツアーのサポート・アクトとして初来日。イーノやキング・クレオソートとのコラボ作品を発表。13年に発表した4作目『イミュニティ』が英国最高峰音楽賞マーキュリー・プライズ2013にノミネートされた他、ミュージック・マガジン2位 (ハウス/ブレイクビーツ部門)、Qマガジン5位、英ラフ・トレード・ショップ6位、NME11位と名立たる音楽メディアの年間ベスト・アルバムで上位を獲得!米ピッチフォーク8.5点&ベスト・ニュー・ミュージック獲得した。