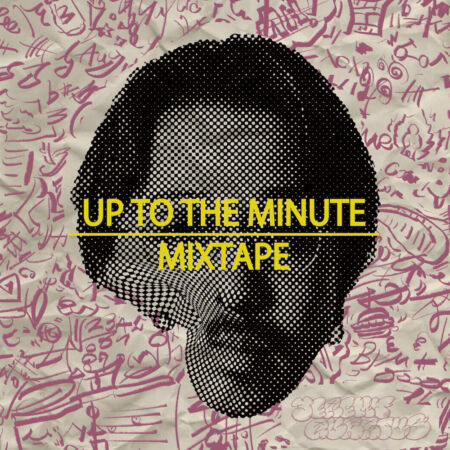残念な話であるが、納得のいく優れた作品を世にリリースすることとバンドや作品自体が売れることは、多くのミュージシャンにとってイコールでないことが現実である。また、バンドとして充実した活動を送っているからといって、ミュージシャンとして充実した日々を送れているとは限らない。そして、「売れたい」――言い換えれば「自分たちの音楽を沢山の人に届けたい」と思うことはミュージシャンとして、至極真っ当な欲求である。そんなミュージシャンであれば誰もがぶち当たる葛藤や苦悩に、DATSは同世代の若いバンドの中でも、取り分け真摯に向き合ってきたバンドであると言えるだろう。
結成して間もなく、彼らはオーディション企画から”SUMMER SONIC”のステージに立ち、[Alexandros]やArt-School、BIGMAMAと言った人気ロックバンドを擁するUKプロジェクトとの契約を早々に結ぶ。さらにオーストラリアのLast DinosaursやポルトガルのNortonと言った自身の音楽性と近い海外アクトとの共演も果たし、DATSはバンドとして順調にステップを重ねているように見えていた。しかし、それは幸か不幸か、大人が用意したレールに早い段階で乗ってしまったとも言えるのではないだろうか。例え、そのレールが自分たちの望んだものから多少距離があったとしても、大きな野望に向かって進みつつある列車から降りることは容易なことではないだろう。
しかし、DATSはついにその列車から降りることを決断した。〈Rallye Label〉に移籍し、ロゴ、アーティスト写真、WEBサイトを一新。そして公開された新曲「Mobile」は、これまでのギター・ロックを軸にしたバンド・サウンドとは大きく異なり、エレクトリックでビートの強い打ち込みを主体とした、ピアノ・リフの印象的な先鋭的なダンス/ビート・ミュージックとなっている。
そして、もう一つDATSの変化を紐解く上で重要な要素がある。杉本亘(Vo./Gt.)と大井一彌(Dr.)が所属するyahyelの存在だ。2016年に入った頃から徐々にシーンをざわつかせ、METAFIVEのオープニングアクトや”FUJI ROCK FESTIVAL”内の”Rookie A Go Go”への出演を経て、yahyelへの注目度と存在感は昨秋頃から一気に加速していった。特に杉本は、DATS、yahyel双方のサウンドの中核を担う人物なだけあって、今回のドラスティックな変化に何かしらの影響を与えたと考えるのはごく自然なことだろう。
筆者はこれらの極めて特殊な状態の中にいたDATSの4人が考えていたこと、そしてバンドとして導き出した答えを問うべくメンバー4人にインタビューを実施。しかし、彼らが抱えていた葛藤はミュージシャンとして決して特殊な話ではない。本稿は悩める全ての若きミュージシャンに捧げる記事と言ってもいいのかもしれない。
Text by Kohei Nojima
Photo by Yuma Yamada

L→R:早川知輝(Gt.)、杉本亘(Vo./Gt.)、伊原卓哉(Ba)、大井一彌(Dr.)
―今回のシングル『Mobile』のリリースに際して、レーベルを移籍し、同時に音楽性も大きく変化しました。これはDATSにとって大きな決断があった上でのことだと思うのですが、率直になぜこういった変化に至ったかを聞かせてもらえますか?
杉本:まず去年の1年間、DATSとしてどのような音楽を作っていけばいいのかというところですごい悩んでいました。売れるためにはどうしたらいいのかという思いもありましたし、やりたいこともすごく多くて、とにかく試行錯誤を繰り返していました。一時期は本当に何をやったらいいのかわからないくらいの状況も続いたりして。あと、自分たちが以前に在籍していた〈UK Project〉の先輩バンドとかを見ていて、自分たちもああいう風にやっていかないとレーベルからちゃんと扱ってもらえないのかな、とか。そういういうプレッシャーもありました。そういう、本来アーティストとしてはあまり考えなくていいことで悩んでいたなって。でも、そこから「もうそんなこと考えなくていいや」って振り切ることができたっていうことが、今回の変化に対して一番大きい要因だと思います。
―なるほど。では、もう少し活動の時間軸に添いつつ、外から見たDATSと内側から見たDATSを照らし合わせていくことで、その変化のターニング・ポイントを探って行けたらなと思います。まず、2013年〜2014年頃に、ざっくり言うと海外のインディー・ロックの文脈を擁した日本の若手バンドがたくさん出てきました。その中だとHAPPYが少し先行していて、その後に続くような形でThe fin.やYkiki Beat、PAELLAS、YOUR ROMACE、そしてDATSなどが新しい流れを作っていくような機運が感じられたのですが、当時のシーンをどう捉えていましたか?
杉本:確かにあの当時は自分たちが活動しているシーン自体が、ちょっと盛り上がってきているなっていうのは感じていましたね。先ほど挙げて頂いたようなバンドに対しても、本当純粋にカッコイイなって思ってましたし、エッジの効いたことをやってあれだけ評価されていることに対して、すごいリスペクトの気持ちもありました。なので、そういった中で自分たちもドンドンおもしろいものを出していけたらなっていう思いでやっていましたね。でも、当時のシーンにいた周りのバンドたちには、同時に少し排他的な雰囲気も勝手に感じていました。
―そこに違和感を感じていた?
杉本:そうですね。本人たちがどう思っていたかはわからないですし、排他的な雰囲気があること自体を否定するつもりもないんです。ただ、僕らはどちらかと言うと、よりたくさんの人々――日本の多くの音楽リスナーを巻き込んでいくっていうことに意識が向いていたんです。なので、同じような時期で同じような場所で活動していたので、同じシーンで括られることは自然なことだと思うんですけど、自分たちの中ではちょっと線を引いていたような気がします。
―そうやって線を引いていた結果なのかもしれませんが、2014年には”出れんのサマソニ!?”、そして2015年には同フェスのソニックステージへの出演を果たし、先述の〈UK Project〉と契約を結ぶに至りました。バンドしては順調なステップを歩んでいるように見えていましたが、内心ではいかがでしたか?
杉本:今言ったように、自分たちは多くの人々を巻き込んでいくことを目指していたので、〈UK Project〉と契約したことも自分たちにとっては大きなことでしたし、そんな中でLast DinosaurやNortonとも共演させてもらって、バンドとしての活動は充実していました。ただ、作品に対しては納得しきれていなかったというか、「まだまだいけるよね」とは思っていました。

―僕が初めてDATSのライブを見たのは2014年の11月で。FoalsやTwo Door Cinema Clubのような2010年前後の海外の踊れるロック的な要素と、わかりやすいギター・リフや高速4つ打ちなど、当時国内で売れていたギター・ロック的な要素を併せ持っていて、洋楽のインディー・ロック好きと、邦楽ギターロック好きのどちらにも刺さりうる音楽性だなと思っていました。なので、大きく売れる可能性を強く感じる一方で、そのバランスとポジショニングにはかなり気をつけた方が良さそうだなとも思っていました。
杉本:まさしくその通りです。バランス感は凄い意識していました。当時は理想論が先にいっていて、やりたい音楽と結果を出すことの両立を急ぎ過ぎていたと思います。
―その欲や迷いみたいなものが、今振り返ってみると当時の作品やライブには出ていたようにも思えます。
杉本:そうですね。なので、今では考え方が完全に振り切れましたね。ただ単純に自分たちが鳴らしたい音を鳴らして、楽しいと思うことをやって、その後に結果を出す。っていう考え方にシフトできたと思います。
―2016年2月に自主企画で実施したTempalayとyahyeを招いた自主企画と、2nd EP『FRAGMENT』のリリースがある意味、初期DATSの最後だったのではないかと思います。それ以降リリースもなく、対バン相手や出演するイベントなどにも変化し、これまでに身をおいていたシーンやリスナーから自ら距離を取るようになった印象を持っています。これはレーベルの方針なども関係しているのでしょうか?
杉本:レーベルの方から特に言われていたということはなかったんですが、レーベルの担当の方が思い描いているビジョンが僕らのそれとは違っていたっていうのは事実としてありました。もちろん〈UK Project〉の先輩方の活動を見ている中で得た知見や、ノウハウなどを教えてもらったり、勉強になることもたくさんありましたし、正しいこともおっしゃっていたとは思うんですが、心の中ではどうしても腑に落ちないことも多くて……。
伊原:〈UK Project〉の先輩たちはめちゃくちゃ売れているし、僕らが高校生の時から聴いていたバンドもたくさん在籍していて。なので、「〈UK Project〉に在籍しているからには、おれたちも先輩たちみたいにならなくちゃ」って、勝手に思い込んでいたんですよね。そこから一旦立ち止まって、「おれたちが本当にやりたいことって、どういうことだったのかな?」って何度も自問自答していた時期っていうのが、去年1年間だったと思います。
―外から見ていたらレーベルへの帰属意識も感じられていたのですが、その裏ではとても大きな葛藤があったと。
杉本:ありましたね。”UKFC on the Road 2016″みたいな大きいイベントに出させて頂けたのはとても光栄だったし、(〈UK Project〉に所属したことで)バンドとしてのチーム力は間違いなく上がったと思います。ただ、やっぱり僕らにとっては作品が一番大事なので。自分たちも出口が見えていない状況の中、一緒に良い答えを見つけられなかったというか。なので、自分たちでどうにかしなきゃいけないという想いが強くありました。
―そんな中、同時並行で活動をしていたyahyelが2016年に入って注目を浴びてきました。そこでの活動や世の中の反応はかなりDATSにもフィードバックがあったのかなと思うのですが。
杉本:今回yahyelがちょっと話題になった後にDATSもレーベルを移籍して、音楽性も一新して作品を出します! って流れになっているので、yahyelからインスピレーションを受けたサウンドって解釈されがちですよね。結果としてそれ自体は間違いではないんです。でも、どちらかというとyahyelの音楽自体が元々DATSからインスピレーションを受けてやっていたものなんです。というか、僕からしてみれば本当はDATSでやりたかったことだった。
―DATSでできなかったことを、yahyelでやっていたと。
杉本:そうなんです。なので自分にとってはめちゃくちゃ複雑なんですよね。yahyelが話題になるにつれて「DATSはどうした?」、「DATS。もうやんなくてよくね?」みたいな声も増えてきて、これはなんとかせんとあかんな、と。ある意味そういう声も新しいDATSへの起爆剤になりましたけどね。
伊原:そういう話も去年の1年間の話の中には含まれています。今は去年1年分の積もり積もった葛藤をこの1年でぶちまけようとしているって感じですね。
―「Mobile」に関しては本当に迷いがなくなったというか、強い意志が感じられました。これまでの作品とは強度が別物というか。この曲はいつ頃から、どういった形で作り始めたのですか?
杉本:去年の10月頃ですね。
伊原:「Mobile」の他にも新しい曲はあったんです。でも、それはこの4人の意見をふんだんに盛り込んだ曲たちで、それはそれで悪くはなかったんですけど、何かしっくりこなくて。それで改めて亘に「一度全部作ってきてくれ」って振ってみたんですね。今はそれくらいの振り切れ方が必要なんじゃないかなって思って。元々は亘のことが好きで集まってきたようなメンバーなので、ここは一度彼に全て託してみようって。
大井:あとは活動スタイルの価値観も少しづつ変わっていると思います。今の時代は作品とライブの違いが顕著であればあるほどおもしろいと思っていて。音源は音源、ライブはライブとして魅力の違いを出して行くという考え方にシフトしました。それこそyahyelはライブは生ですが、音源はガッチリ打ち込みでやっていますし、そういうスタイルの魅力を、yahyelの活動を通してわかるようになってきたのかなって思います。
杉本:yahyelでやりたいことと、DATSでやりたいことそれぞれをちゃんとやれるタイミングがやっと来たなって感じだよね。
―では、その「DATSでやりたいこと」というのをもうちょっと具体的に教えてもらえますか?
杉本:たくさんの人々を巻き込んでいきながら、音楽シーンを盛り上げて行きたいってことですね。
―目指すところは最初から変わってないけど、手段が変わったってことですね。
伊原:はい、そこは結成した時からブレていないと思います。
―例えば、ジャンルなどは違えどSuchmosや水曜日のカンパネラのような同時期に出てきたアーティストが、DATSが目指しているような大きなフィールドに出ていったことは、みなさんの考え方に影響を与えたりはしていますか?
:そうですね。作品ありきでやってきた人たちが上に行ける時代になったっていう意味では、本当に大きいことだと思います。
伊原:界隈やシーンに帰属することで売れていくのではなく、自分たちのスタイルと作品をしっかりと打ち出しているアーティストが上に行けるってことを確認できたって感じですね。考え方がシンプルに戻ったというか。これって当たり前のことだと思うんですけど、僕らは考えすぎてたんだと思います。
杉本:本当、何してたんだろって感じだよね(笑)。
大井:人目とか他人の意見を気にしすぎてたよね。
杉本:そういう意味で、何もかも一新したかったんです。レーベルが変わったのもロゴや音楽性が変わったのも、新しくゼロからブランディングしていくっていう想いが込められています。
―では、今回その〈Rallye Label〉へ移籍した経緯というのは?
大井:僕はDATSやyahyel以外にもプレイヤーとしてのサポート業をしていて、その一環でニカホヨシオとも一緒にやってたんですけど、彼を担当していたのがRallyeの近越さんだったんです。そこで知り合って、「DATS、最近どうなの?」って声をかけてくれたり、すごく気にかけて頂いて。何か僕らが抱えていたジレンマとかストレスとか、何も話していないのに理解してくれている感じで。僕たちとしてもまたゼロからやりたいことやる、っていうマインドもガッチリ固まってきていた時期だったので、もう2つ返事で移籍を決めました。
伊原:なんの迷いもなかったよね。

―それって「Mobile」が出来る前の話ですか?
大井:全然前ですね。なので、近越さん的には完全に見切り発車なんですよ(笑)。
伊原:僕、近越さんには会ったことがなかったんですけど、LINEでやたら長くて熱いメッセージが送られてきて(笑)。かしこまったメールだったらそんなに心動かされなかったと思うんですけど、何も考えずにただただ思ったことを言ってくれるっていう、その姿勢に安心したというか、こういう人とやってみたいなって思わされましたね。
―後ろにいる近越さんの顔が真っ赤になってますね(笑)。それでは、「Mobile」の作品としての話を伺いたいのですが。まず、海外の現行のトレンドをすごく意識していますよね。
杉本:そうですね。簡単に言うと今、世界のオーバーグラウンドでブイブイいわせているような音を作っていきたいっていう意識がありました。なのでビルボード・チャートTOP10とかに入っているような音楽も散々聴きましたし、同時にクラブでかかっているディープ・ハウスとかとにかく今、自分がカッコイイと思うものだけを聴いて、自分が今カッコイイと思うものを追求したらこういう音になったって感じですね。
―マスタリング・エンジニアに砂原良徳を起用されていますが、どういったサウンドを求めていたのでしょうか?
杉本:実は以前から砂原さんにお願いしてみたいって思っていたんです。というのも、知り合いのLicaxxxと宅録マスタリングの話をしていた時に、砂原さんの名前が挙がって。「砂原さんの家の機材に音を通すだけで、かなり良くなるらしい。低音めっちゃ締まるらしいよ」っていう話を聞いて。で、砂原さんの音源とか色々聴いたてリサーチしていく中で、砂原さんにこの曲をお願いしたら絶対いい感じになるわ!っていうイメージが自分の中で湧き上がってきて。ただ、実際の作業の際には細かいオーダーはしていないですね。「この音を聴いて湧いてきたインスピレーションでやって下さい!」とだけお伝えしました。
―ちなみに、杉本さんの中ではどういったイメージを持っていましたか?
杉本:ミックスの時点で相当Hi-Fiな音源にしたかったんですね。そういうものをたくさん聴いてインスピレーションを受けているので。なので、あんまり日本っぽくなく、思い切った感じでミックスをしました。その若さの勢いだけで作り上げた音源に対して、ベテランの経験とかインテリジェントな要素を加えてほしいなと思っていました。ただ音圧が上がるだけじゃなくて、低音の膨らみやパンチを出しつつ、なおかつボーカルも気持ちよく聴こえる音になったと思います。どの帯域も締りがよくて耳が痛くない……「品の良い音」っていうのが一番しっくり来る表現かもしれませんね。
―ミックスはご自分で?
杉本:荘子itっていうyahyelのRemixやyahyelのライブにも共演してくれた友達がいるんですけど、今回は彼にお願いしました。
―使用楽器もこれまでとは全く異なるものだと思うのですが、これまでのオーソドックスなバンド編成からシフトすることに抵抗はなかったですか?
杉本:「やれる!」っていう自信があったので、抵抗は全くなかったですね。きちっとしたバンド編成である必要性はまったくないというか。どちらかというとそういうスタイル面の方がyahyelから影響を受けているのかもしれません。とはいえ、弦楽器も全然使うのでそこまで大きくシフトしたという認識もないですね。
―ライブのスタイルもかなり変わりますよね。
早川:そうですね。音源を良くするために、必要なものを演奏して肉付けしていくという感じですかね。ギターが不要であればギターは弾かないし、逆にギターが活きるのであればギターを弾く。サンプラーを叩くこともありますし、エレキ・ベースを使うこともあれば、シンセ・ベースを使うこともあります。曲を良くするために、その都度最適な方法で演奏をするっていう感じですね。
大井:かなりフレキシブルな感じになりますね。
―音楽性もスタイルもガラッと一新することになりましたが、これまでのDATSのファンに対して不安に思ったりすることはなかったのでしょうか?
杉本:全然なかったですね。そんな余裕もなかったし、自分たちがカッコイイと思う音楽をやるんだから、きっとまたカッコイイと思ってくれるに違いない、っていう感じです(笑)。
―実際「Mobile」を公開した後はどういった反応がありましたか?
早川:ネガティブな反応はほとんどなかったですね。
伊原:彼(杉本)は過激派なんで(笑)、僕は少なからずそういった昔からのファンの方がどう思うだろうって、気にしている部分はありましたけど……。
早川:特に僕と伊原はyahyelのメンバーでないし、これまで生ベース、生ギターでやってきた人間なので、スタイルについては最初あまりピンと来てなかった部分もあったんです。でも、実際演奏してみたら全然変わらんなって感じでしたね。
杉本:楽器とか編成に縛られて曲作りをしている時点で、クリエイティビティを制限してしまっているというか。それがイケてないことなんだなって思うようになりました。「いい曲を作って、それをどう演奏するか?」ってことだけを考えればいいだけというか。
伊原:生のギターとベースとドラムだけがバンドだっていう概念はもう僕らにはないですけど、ただ僕らがやっていることは絶対にバンドだと思っています。
早川:この4人で演奏することがバンドであり、DATSだっていう。

―なるほど。そういえば今回のシングルには「Mobile」のyahyelによるリミックスも収録されていますよね。これは杉本さんがやられたんですか?
杉本:バレてますね。そうです(笑)。これはただシンプルに、DATSとyahyelの違いを明確に示しておく機会だと思って、そういう意図を込めました。
―DATSとyahyelの違いを音で説明しようってことですね。
伊原:あと、単純におもしろいしね。俺たちにしかできないことだと思うし。
―今後DATSはどういった動きを予定していますか?
杉本:「Mobile」をシングルで出した後は、初夏にアルバムのリリースを目指して動いています。
―そのアルバムについても少し聞かせてもらえますか?
杉本:フル・アルバムに一つ大きなテーマを設けているんです。「SNS世代のリアル・日常・生活」っていうのをテーマに、1曲ずつ書いていっています。今回は作詞は僕だけでなくみんなで行っているんですけど、4人それぞれのテーマに対して見え方や、世の中に向けた問いかけが表れていています。僕ら世代ならではの表現や作品にできたらないいなって。
伊原:そういう意味でも、「Mobile」っていう曲名もあんまり聞いたことないんじゃないかなって。
早川:そういうメッセージやアルバムに入る要素が、実はMVの中にも伏線として張られているんです。
―あのMVには皮肉のようなメッセージ込められているように思えました。
伊原:ただ単純な皮肉という訳ではないですね。単純にリアル、「僕らってこうだよね」っていうのを表しているというか。
杉本:もちろんちょっとは皮肉みたいなものもありますけど、自分たちへの戒め内包した上での、他者への警鐘や問いかけですね。
伊原:それを当事者である僕らがやるから、あんまり皮肉っぽくならないんじゃないかなって。
杉本:どちらかというと自分たちのリアルをおもしろがっているって感じですかね。壮大なようで壮大じゃないというか、メッセージがあるようでない、みたいな。最終的には「楽しんだもの勝ちじゃん?」みたいなアルバムになると思います。
伊原:そういう意味でも色んな人に聴いて欲しいですね。若い人たちはもちろん、デジタル・ネイティブ世代ではない大人たちにも聴いて欲しいですね。幅広い人に興味を持ってもらえる内容になるんじゃないかなと。
杉本:あとSNS世代と言っても日本だけじゃないんで、「東京の若者がこのテーマ(SNS世代のリアル・日常・生活)をどういう風に捉えているんだろう」っていう目線で、海外の人にも興味を持ってもらえたらおもしろいなと思っています。サウンド的に言えば、「Mobile」を軸にしつつ、本当にカッコイイと思ったものだけを統一感持たせてパッケージしていくつもりです。
―アルバム、とても楽しみにしています。先程ようやくスタートラインに立てたとおしゃっていましたが、最後に改めてDATSとして導き出したバンド論というか、バンドとしての哲学のようなものがあれば教えてください。
杉本:今、自分たちが鳴らしたい音やカッコイイと思った音を表現すれば、憧れていた景色や想像もしていなかった景色が必ず見れる、ということを信じてやっていくってことですかね。
―なるほど。本当に今はバンドがとてもいい状態にあるんですね。
伊原:レーベルの話もyahyelの話も、今思えばいい経験だったなって思います。今はとにかく、すごい楽しいっす!(笑)

【リリース情報】

DATS 『Mobile』
Release:2017.03.08 (Wed)
Cat.No.:RYECD270
Price:¥500 + Tax
Tracklist:
1. Mobile
2. Mobile (yahyel Remix)
※タワーレコード限定発売 / 数量限定生産